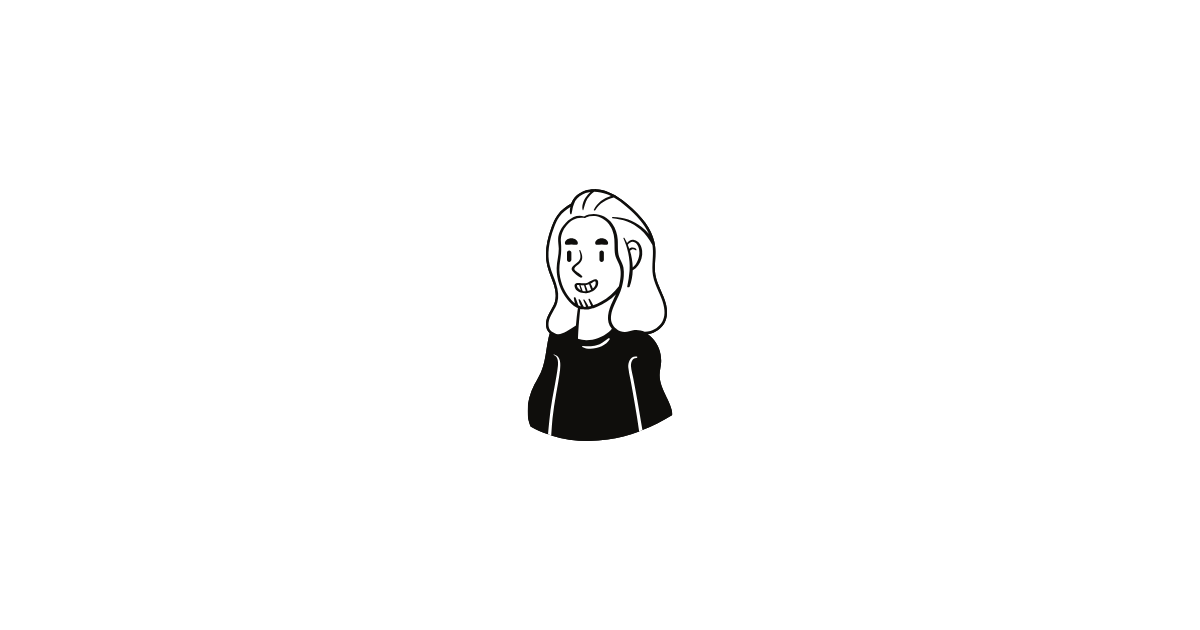
はじめまして。エンタープライズ第二本部、1年目の藤城龍之介です。
本記事では、ITほぼ未経験の状態から応用情報技術者試験において入社半年で上位約0.1%に食い込んだ体験談と10の戦略を紹介します。
私が実際に行った学習方法や反省点も含めて、応用情報の戦い方を記しますのでぜひ参考にしていただければと思います。
なお、本記事では応用情報技術者試験を取り上げていますが、その他の資格試験の対策に活用できるところもあるかと思いますので、応用情報以外を受験する方もご一読いただければ幸いです。
目次
当時の私のスペックと状況
- ITほぼ未経験(電気系の理系大卒)
- 社会人1年目
- IT系資格保有なし
- 理系科目は割と得意
- 暗記はかなり苦手
私が応用情報を受けようと思ったのは、ただ資格を取りたいというわけではなく、自社の研修とは別に自身でもIT系の知識をつけていきたいと思ったからです。
そこで、ITに関する体系的かつ使える知識を得られそうな応用情報を受験することにしました。(基本情報か応用情報が取得必須資格だったのもあるが...)
資格は取ることを目標にするのもいいですが、知識が体系的にまとめられており、効率よく知識を習得するのに最適だと考えています。
また、自身の知識を増やし、理解を深めることを目的に取り組むと気持ちも入りやすくなると思います。
応用情報技術者試験の概要
応用情報技術者試験は午前試験と午後試験があり、どちらも60点以上で合格です。
なお、午前試験で60点以上取らないと、午後試験は採点されないそうです。
- 午前試験
| 試験時間 | 9:30 ~ 12:00(150分) |
| 出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) |
| 出題数 | 80問 |
- 午後試験
| 試験時間 | 13:00 ~ 15:30(150分) |
| 出題形式 | 記述式 |
| 出題数 | 11問(解答は5問:1問必答、4問選択) |
| 試験科目 | 1. セキュリティ(必答) 2. 経営戦略系 3. アルゴリズム 4. システムアーキテクチャ 5. ネットワーク 6. データベース 7. 組み込みシステム 8. システム開発 9. プロジェクトマネジメント 10. システムマネジメント 11. システム監査 |
勉強方法
それではここから勉強方法について紹介します。
スケジュールと勉強時間
入社と同時(4月)に勉強を開始しましたが、すぐにペースが落ちました。
結局7月末まではダラダラと勉強を続けていたため、この期間は平均するとおそらく1日あたり1時間くらい勉強していました。
8月になってさすがにマズいと思い、平日3時間、休日5時間くらいの勉強に切り替えました。
休日少なくない?と思った方もいると思いますが、趣味などに時間を使ったりして適度なリフレッシュをすることで勉強時間内にしっかりと集中することができました。
戦略①:適度なリフレッシュで勉強時間の効率を上げる
→ 特に休日は1:1くらいの割合でリフレッシュする
というわけで、結局学習時間としては約400時間ほど取りました。
しかし、今思えば4~7月の勉強ではほとんど身に付いていない気がするので、実際には約300時間くらいだと思います。
もっと後から勉強開始して集中して取り組めていたら良かったと考えています。
戦略②:勉強開始は集中力を保てる期間を見据えてから
→ 応用情報は3, 4か月前がオススメ
使用した教材
使用した教材は3つで、以下で紹介する3つのフェーズごとに使い分けておりました。
インプット(~ 9月中旬)
インプットで使ったのは合格教本で、暗記が苦手な私は以下のようにインプットしました。
ちなみに、私はテクノロジ系の知識が欲しかっただけなので、この教材のマネジメントとストラテジは飛ばしました。
→ 後のアウトプットで何とかなりました
⇒ 丸暗記ではなく、原理や考え方などを他の要素と結び付けながら理解することで暗記量をできるだけ減らしました。
・2周目:自身が書いたノートを読み返して復習 → 理解できていないところは再度書きながらチェックする
⇒ 1周だけでは完璧に理解できないので、分かりづらいと感じたところはインターネットも併用しながらさらに理解を深めました。
・3周目:さらにノートで復習 → 暗記するしかないところを覚える
⇒ とにかく丸暗記するという行為が嫌いなので、2周してできるだけ丸暗記の量を減らし、最後の最後で暗記するしかないところを覚えました。
このように、体系的に繋げて理解することを念頭に学習を進めることで、丸暗記の量を減らすことができる上、内容も十分に理解することもできました。
当初の目的であった、体系的かつ使えるITの知識を得ることができたと思います。
暗記が得意な方も、応用情報の範囲は莫大で丸暗記するにはかなりの根気がいると思いますので、ぜひ「繋げて理解する」ことを念頭に勉強していただければと思います。
戦略③:丸暗記をやめて体系的に「繋げて理解する」ことに専念する
→ 繋げて理解することで、使える知識へと昇華できる、かつ最終的に時短にもなる
アウトプット(午前試験 / 9月下旬)
インプットで9月中旬くらいまで使い、ここでやっとアウトプットに入りました。
まずは午前試験対策です。
9月末を使い、過去問道場で午前試験の過去問を3年分(6回分)、解きました。
ここで意識したことは以下の3点です。
2. 知識の抜け漏れを補完し、インプットで得た知識を確認すること
3. マネジメントとストラテジ(インプットをしなかった科目)について知ること
まず意識することは、試験で問題がどのような形式で出て、どのような時間配分で解けばいいのかを確認することです。
これは6回分もやれば十分につかめると思います。
次に、知識の抜け漏れを補完することです。(これが重要!)
インプットで入れたものは100%定着するわけではないので、ここでさらに思い出すことによって知識を補完・確認していきます。
また、試験では多少合格教本に書いていないことも出題されるので、そこについてはインプットフェーズのように新たに知識を入れていきます。
なお、マネジメントとストラテジについてはここで問題を解くことで十分に解けるようになりました。
* 欲しい知識には個人差があるので、おすすめしているわけではありません。
戦略④:アウトプットはあくまで試験の形式の確認と知識の補完・確認
→ インプットで得た知識を確認すると共に抜け漏れをなくす
過去問はたくさん解いた方が良いとは思いますが、IT業界の知識は日々アップデートされていくのでそこまで古い過去問に手を出す必要はないと思います。
再度になりますが、実際にやってみて6回分も解けば十分だと思いました。
戦略⑤:過去問を解くのは適度に終わらせて良い
→ 6回分で十分
アウトプット(午後試験 / 10月上旬)
10月に入り、午後試験の対策を始めました。
午後試験は1回分が長く、自分で問題を厳選するのが面倒だったため、午後問題の重点対策を使って、どのような問題が出るのか掴むことにしました。
基本的には、解く問題をある程度先に絞ってからその分野だけ過去問を解いて慣れていくことがオススメです。
午後試験は4問が選択問題で、6問は解かない問題になるので、時間が十分にある方以外は選択する問題を絞って勉強するのが効果的だと思います。
私は以下のように午後問題を絞りました。
確実に解く問題は2, 3問決めておき、問題文を見て決める問題を1, 2問に絞っておくと学習も本番も余裕ができます。
あくまで私の特性(長文を読むことが苦手)とこれまでの学習方法に対する選定方法なので、自身の特性と学習状況に応じて選定してみてください。
△:本番の問題文読んでから決める問題
✕:絶対に解かない問題
△ → ✕:問題集を解いてみた結果、絶対解かないように変更した問題
| 科目 | 選択 | 説明・選定理由 |
|---|---|---|
| 1. セキュリティ | 必須 | 午前の知識がある前提で、問題を読めば解ける |
| 2. 戦略系 | ✕ | 文章が長く、知識も浅い |
| 3. アルゴリズム | 〇 | 変数の説明をしっかり読み、具体例や図を用いて明確化すれば解ける |
| 4. システムアーキテクチャ | △ → ✕ | 計算問題が多く、ミスもしやすい傾向があった |
| 5. ネットワーク | △ | 記述が難しいことがあるが、ある程度の得点源になる |
| 6. データベース | △ | いかついER図などが出てきてタイパが悪い回がある |
| 7. 組み込みシステム | 〇 | 知っているモノが出ることが多く、事例が理解しやすい |
| 8. システム開発 | 〇 | 事例を理解することに専念すれば、あとは自社の研修内容で解ける |
| 9. プロジェクトマネジメント | ✕ | 文章が長く、知識も浅い |
| 10. サービスマネジメント | ✕ | 文章が長く、知識も浅い |
| 11. システム監査 | △ → ✕ | 文章が長い |
このように、事例の文章も長く、インプットをしなかったマネジメント、ストラテジ系以外の問題(6問)を解いて検証し、自分にあったものをスタメンとしました。
できるだけ絞ることで、勉強の効率が大幅に上がるのに加え、本番で問題を読んで迷って時間を食うこともないので、学習の段階から絞って勉強するのはかなりオススメです。
戦略⑥:午後問題は思い切って絞る
→ 確実に解く問題を2, 3問に絞り、重点的に学習する
試験直前
2日前
試験2日前は、アウトプットに使っていたノートを見ながら復習をしました。
どのような問題でミスしたかを再確認することで、もう一度記憶を整理し、定着させました。
前日
前日はインプットに使っていたノートで復習をしました。
学んだことを確認し、知識の結びつきを再度整理することで、本番に向けて準備を整えることができたと思います。
それ以外の時間は趣味に充て、頭を休めました。
戦略⑦:試験直前は復習するだけ
→ 直前に詰め込もうとしても焦りでインプットできないため、やったことを復習し、あとは自由に過ごす
試験当日
試験前
会場は行ったことがない駅の近くの専門学校でした。
朝早かったこともあり、集合時間の 1 時間前くらいに会場の最寄り駅まで行き、集合時間ギリギリまで近くの公園で朝ご飯を食べながらノートで最終確認をしていました。(教室は空気が重く不自由だったのでこの選択は正解だった…)
ちなみに、持って行った教材は自分がインプットとアウトプットで使ったノート4冊です。
戦略⑧:試験日の朝は周りの空気に呑まれないように
→ 自分でその環境を作り出すことが大事
午前試験
午前試験では分からない問題はとにかく後回しにして、まず一通り解き終わることを目標にしました。
結局大幅に時間が余ったため、分からなかった問題も含めて 3 回くらい見直しをすることができました。
昼休憩の時間に過去問道場のサイトで解答速報が出るので、それに備えて問題に自分の解答を書き込んでおくことも大切です。
早く解き終わったら退出できるので、昼休憩を有効に使いたい人は退出するのもオススメです。
昼休憩
昼休憩時は、朝と同様の公園で昼ご飯を食べながら、解答速報を見て答え合わせをしました。
合格ラインに乗っていたので、心置きなく午後試験に臨むことができたと思います。
昼休憩は多少の復習もしましたが、公園で少し体を動かすことでかなりのリフレッシュになりました。
戦略⑨:昼休憩は頭を休める
→ 体を動かしたりして気分転換をする
午後試験
午後試験は立てた戦略通り、確実に解く問題である、以下の問題を先に解きました。
しかし、この年は組み込みシステムがとても難しく感じ、ここだけは一旦問題用紙に解答を書き込んでネットワークとデータベースを解くことにしました。
問題文を読み始めると、想定よりもネットワークが簡単だったため、その後の解答にかなりの余裕ができ、ネットワークとデータベース、組み込みシステムを全て解いて比較することができました。
結果的には、想定よりも簡単だったネットワーク、少しでも点が取れる見込みのあった組み込みシステムを解答として提出しました。
所感
過去問をあまり多く解いていないこともあり、見たことのない問題が多かったですが、繋げて理解することにフォーカスして勉強した結果、当日も考えながら解答を導出できたと思います。
また、午後試験で多少の想定外のトラブルがありましたが、落ち着いて別の解答を進めることで最終的には時間に余裕ができたため、この方法を取ってよかったと思っています。
戦略⑩:試験時に分からない問題は後回し
→ 分かる問題から解き進めることで時間と心の余裕を確保する
結果
結果は…

無事合格できました!
午前が85点、午後が90点です。

得点分布をみると、午前は上位約3%、午後は上位約0.1%でした。
IT ほぼ未経験からここまで得点を上げることができたのも、理解に専念したからだと思っています。
特に午後は過去問が出ることはないので、どれだけ理解しているかがものを言うと思います。
そのため、午前よりも午後の方が得点が高い結果となったのだろうと思っています。
まとめ
10の戦略まとめ
ここまでで紹介した10の戦略をまとめておきます。
人によって合う合わないがあるかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。
● スケジューリング
戦略①:適度なリフレッシュで勉強時間の効率を上げる
→ 特に休日は1:1くらいの割合でリフレッシュする
戦略②:勉強開始は集中力を保てる期間を見据えてから
→ 応用情報は3, 4か月前がオススメ● 学習
戦略③:丸暗記をやめて体系的に「繋げて理解する」ことに専念する
→ 繋げて理解することで、使える知識へと昇華できる、かつ最終的に時短にもなる
戦略④:アウトプットはあくまで試験の形式の確認と知識の補完・確認
→ インプットで得た知識を確認すると共に抜け漏れをなくす
戦略⑤:過去問を解くのは適度に終わらせて良い
→ 6回分で十分
戦略⑥:午後問題は思い切って絞る
→ 確実に解く問題を2, 3問に絞り、重点的に学習する● 試験直前
戦略⑦:試験直前は復習するだけ
→ 直前に詰め込もうとしても焦りでインプットできないため、やったことを復習し、あとは自由に過ごす● 試験当日
戦略⑧:試験日の朝は周りの空気に呑まれないように
→ 自分でその環境を作り出すことが大事
戦略⑨:昼休憩は頭を休める
→ 体を動かしたりして気分転換をする
戦略⑩:試験時に分からない問題は後回し
→ 分かる問題から解き進めることで時間と心の余裕を確保する
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございます。
応用情報はかなり出題範囲が広く、網羅するのは根気が必要ですが、「繋げて理解する」ことで効率的に学習を進めていきましょう。
あくまで私の学習方法と戦略ですが、今後応用情報を勉強する方の一助となれば幸いです!
執筆:@fujishiro.ryunosuke、レビュー:@handa.kenta
(Shodoで執筆されました)




