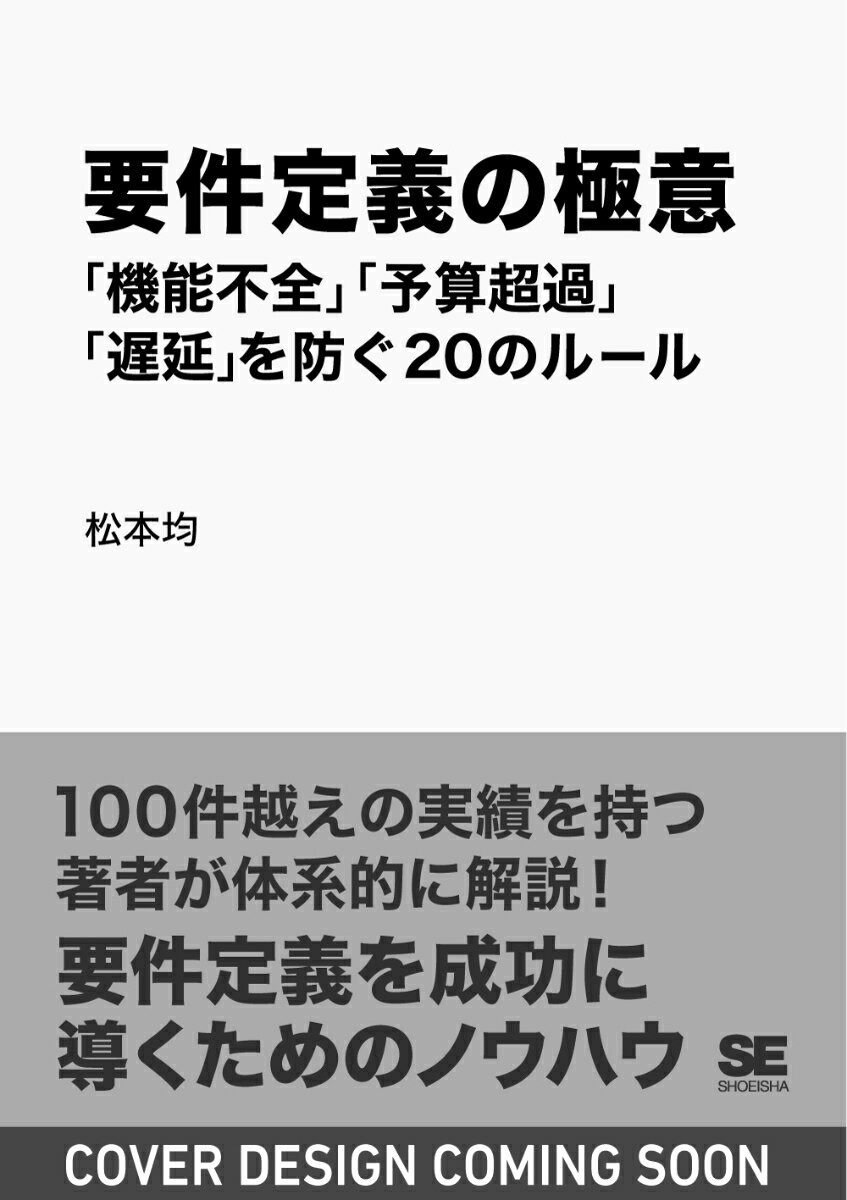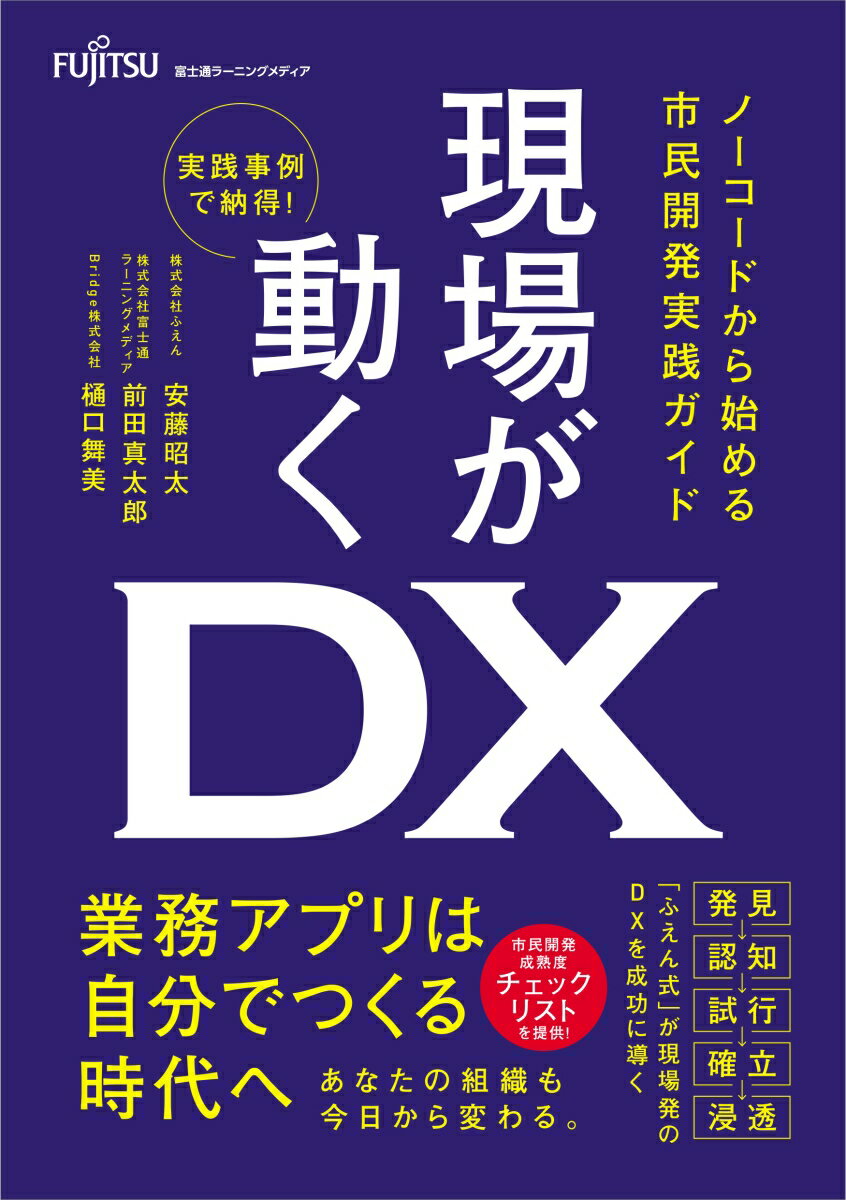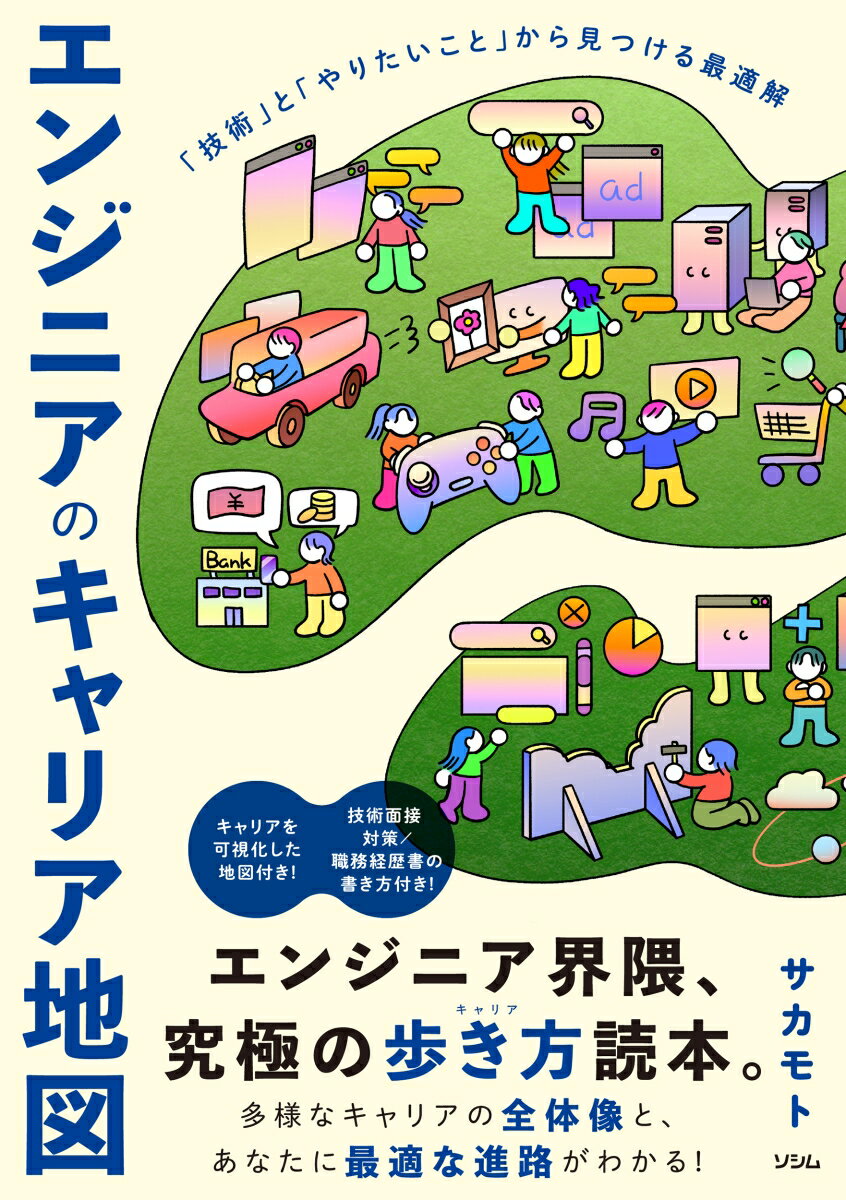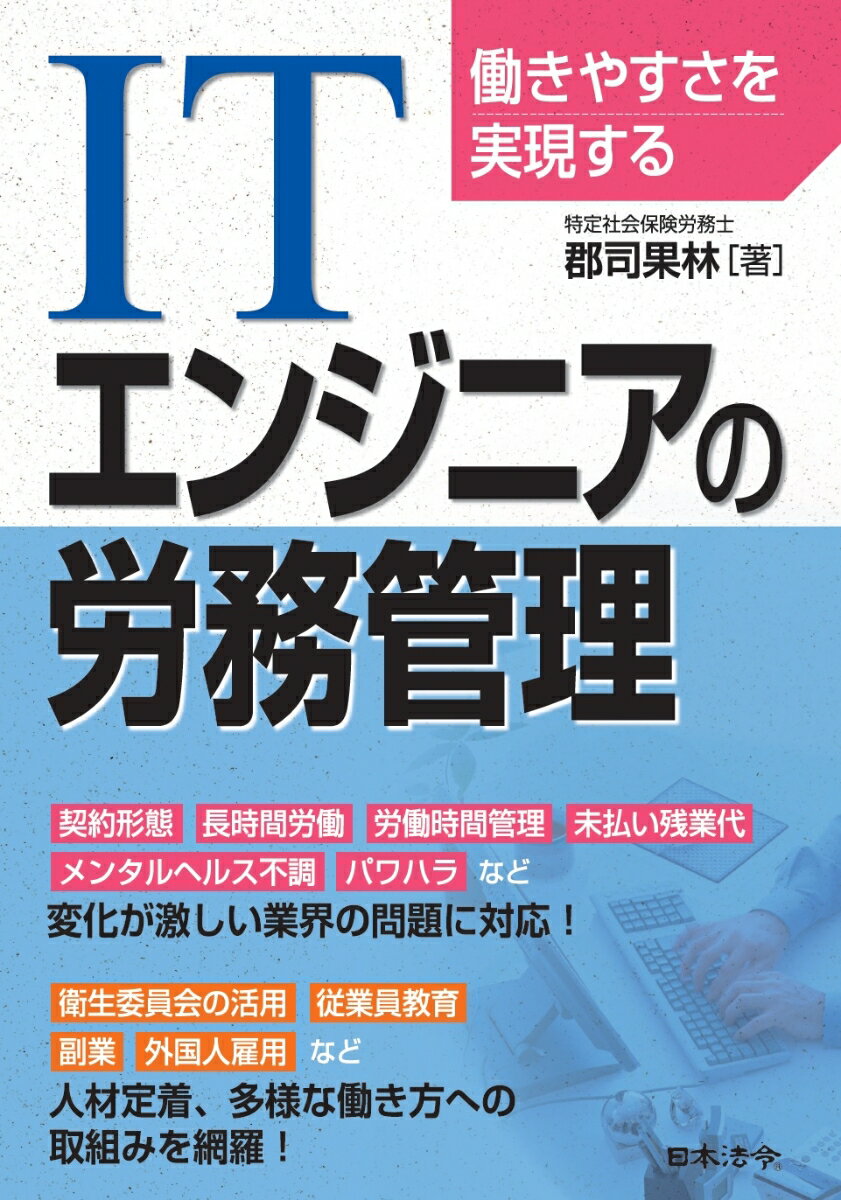
3,080円 (税込)
楽天働きやすさを実現する ITエンジニアの労務管理
書籍情報
発売日:
著者/編集:郡司 果林
出版社:日本法令
発行形態:単行本
書籍説明
内容紹介
契約形態、長時間労働、労働時間管理、未払い残業代、メンタルヘルス不調、パワハラなど変化が激しい業界の問題に対応!衛生委員会の活用、従業員教育、副業、外国人雇用など人材定着、多様な働き方への取組みを網羅!
目次
第1章 ITエンジニアが所属する情報システム開発業界の概要
1 ITエンジニアとは
2 ITエンジニアが関わる情報システム開発業界の種類
3 情報システム開発業界の特徴
4 システム開発の流れ
(1) 伝統的大規模システム開発の流れと多重階層構造
(2) 多重階層構造による開発の労務管理上の問題点
(3) 今後のシステム開発の流れと動向~ DX とシステム開発形態の激変と労働環境の変化~
(4) システム開発に携わる職種と特徴
第2章 ITエンジニアを取り巻く契約形態
1 システム開発における契約形態
(1) 会社間での人のやりとりに関する基本の契約形態
(2) 問題となる労務管理の形態(労働者供給、偽装請負、二重派遣)
(3) 派遣、業務委託の切り分け
(4) 業務委託契約における適正な労務管理のために行うべきこと
(5) SES が問題になりやすいのはなぜか
2 フリーランス(個人事業主)との契約
(1) フリーランスの契約形態
(2) フリーランスとの契約が好まれる背景
(3) フリーランスと労働者の判断基準
(4) フリーランスとの契約の問題点
(5) フリーランスとの契約において気を付けるべきこと
(6) 個人事業主契約が認められなかった例
(7) インターンシップとは何か
3 派遣契約において気を付けること
(1) 派遣受入期間制限に関すること
(2) 労働契約申込みみなし制度について
(3) 契約に当たって留意すべきこと
(4) 派遣先責任者の選任及び派遣先管理台帳の作成
(5) 派遣労働者の同一労働同一賃金(2020 年4 月から)
(6) 派遣先と派遣元の責任分担チェックリスト
第3章 長時間労働問題と労働時間管理の基本
1 ITエンジニアの労働時間管理が難しいのはなぜか
(1) システム開発の多重階層構造から発する構造上の問題
(2) トラブル対応
(3) 個々のエンジニアに対する教育、能力開発の問題
2 どうして長時間労働対策に取り組まなければならないのか
(1) こころと身体を蝕む長時間労働
(2) 脳・心臓疾患の労災認定基準
(3) 取引慣行の見直し
3 労働時間管理の基本
(1) 労働時間と休日の原則
(2) 三六協定(時間外及び休日労働に関する協定)
(3) プロジェクトマネージャーも罪に問われる⁉ 労働時間の管理
4 紛らわしい労働時間のカウント
(1) 法定労働時間と所定労働時間
(2) 土曜日や祝日に出勤したら「休日労働」?
(3) どうして月45 時間、80 時間、100 時間なのか
第4章 柔軟な働き方を実現するための時間管理制度
1 労働基準法上の制度
(1 フレックスタイム制
(2) 1か月単位の変形労働時間制
(3) 専門業務型裁量労働制
(4) 高度プロフェッショナル制
(5) 「柔軟」と「無秩序」は同じではない
2 ITエンジニア向けの独自の労働時間管理制度
(1) シフト勤務制(始業終業時刻の繰上げ繰下げ)
(2) 常駐先に応じた所定時間変更制度
(3) 私用外出、私用遅刻、私用早退制度
(4) 徹夜明け代休(徹夜明け勤務免除)
(5) 振替休日と代休の活用
第5章 未払残業代問題
1 未払残業代はどのように発覚し、請求されるのか
(1) 労働基準監督署からの是正勧告による場合
(2) 本人が弁護士等を通じて請求してくる場合
2 払っただけでは終わらない、未払残業代発覚の事後対応
(1) 未払残業対応の事後措置
(2) 賃金制度の改訂
3 未払残業代を発生させないための対応
(1) 客先請求時間と賃金計算に使用する労働時間は別々に管理する
(2) 固定残業代制度(みなし残業代)は正しく運用する
(3) 年俸制
(4) プロジェクトマネージャーには残業代がいらないのか
第6 章 労務トラブルを防ぐための労働時間の
把握と記録
1 時間外労働に対する教育、認識共有
(1) 在社時間=勤務時間ではないということを共有する
(2) 始業前、終業後に不必要に会社に残らないよう徹底する
(3) 時間外労働は会社の命令によって行うものだということを共有する
(4) 労働時間に該当するのかしないのか、判断の曖昧な時間についての認識を共有する
2 労働時間の正しい記録、把握
(1) 労働時間を正しく記録することの目的
(2) 労働安全衛生法で定める労働時間の記録方法
(3) ITエンジニアの労働時間の記録方法
3 時間外労働を行う際の手続きの明確化(申請、承認)
(1) 時間外労働を行う際の手続き
(2) 時間外労働申請の方法
(3) 現場から反発があった場合は
第7 章 メンタルヘルスケアへの取組み
1 ITエンジニアとメンタルヘルス不調
(1) データで見るメンタルヘルス不調
(2) ITエンジニアにメンタルヘルス不調が多いのはなぜか
2 メンタルヘルスケアに対応すべき理由
(1) 法律で定められているため
(2) 命を守るため
(3) プロジェクトの円滑な遂行のため
3 精神障害と労災認定基準
4 メンタルヘルスケアでやるべきこと
(1) 企業が行うメンタルヘルスケア対策とは
(2) ルール(就業規則)や休職に関するマニュアルの整備
(3) 有事対応のマニュアル化
(4) 体制整備、スタッフ割り当て
(5) 周知、教育、フォロー体制の確立
5 休職・復職を金銭面で支える制度について
6 休職制度の設計
(1) 休職制度とは
(2) 休職制度について決めるべきこと
(3) 休職に入る際の手続き
7 復 職
(1) 本人からの復職申請
(2) 復職判定
(3) 職場復帰プランの作成
(4) 職場復帰、フォロー
8 早期発見と予防のために
(1) 勤怠を確認する
(2) 現場プロジェクトマネージャー、リーダーから情報を募る
9 ITエンジニアにとっての本当のメンタルヘルスケアとは
第8章 労務問題解決手段としての衛生委員会の活用
と安全衛生管理体制
1 人事担当者と他部門従業員との信頼関係構築の重要性
(1) 物理的に距離が離れていることによる人間関係の隔たり
(2) 人事部門と現場開発部門の相互理解不足
2 安全衛生管理体制とは
(1) 労働安全衛生法とは
(2) 安全衛生管理体制の全体図
3 安全衛生管理体制を担うスタッフの役割
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生推進者
4 衛生委員会の活用
(1) どうして衛生委員会なのか
(2) 衛生委員会の効果的な運営方法
(3) IT エンジニアの労務管理独特の話題を取り入れる
(4) みんなで職場巡視をしてみる
5 職場改善と衛生委員会
(1) 職場環境アンケートの活用
(2) 就業規則の改定
(3) 長時間労働対策
(4) マネージャー教育・ミニ研修の場として
(5) メンタルヘルスケア体制のフォローの場として
6 従業員50 人未満の会社における安全衛生管理体制
(1) 従業員50 人未満なら安全衛生にかかわる取組みをしなくてもよいのか?
(2) 地域産業保健センターとは
第9章 人材育成、人材定着への取組み
1 コンプライアンスに基づいた労務管理と長時間労働の削減
2 リーダー層・営業担当者の労務管理教育
3 一般従業員への教育
(1) 2種類の教育
(2) 人材不足と人材余剰への対策
4 信頼関係の構築
(1) 制度が充実していれば人材は定着するのか?
(2) 給与が高ければ人材は定着するのか?
(3) 信頼関係を構築するには
(4) 良い仕事ができる人間関係
(5) 令和型の帰社日活用のすすめ
(6) 社員がつながる仕組み
(7) 家族参加型イベント
5 会社理念の共有と個人のキャリア支援
(1) エンジニアのキャリア支援
(2) あるエンジニアが転職をやめた話
第10 章 多様な働き方の実現と人材活用への取組みに向けて
1 リモートワーク
(1) 作業の特性がリモートワークに適していること
(2) 適切な評価が可能であること(アウトプットが見えやすいこと)
(3) 信頼関係が構築されていること及び社員の自主性が成熟していること
2 副 業
(1) 副業をめぐる世の中の動き
(2) 副業の3 つのパターン
(3) 過重労働と労災
(4) 副業を認める場合のチェックポイント
(5) 副業の活用
3 外国人労働者の人材活用について
(1) データで見る情報通信業における外国人労働者
(2) 外国人を雇用する際に確認すべきこと
(3) ハローワークへの届出
(4) 外国人労働者の雇用管理
(5) 英語による労働条件通知、就業規則の作成
(6) 文化の違いを理解する
第11章 作業員の問題行動への対応
1 従業員の問題行動への基本の対応
(1) 話を聴く
(2) 教育・指導を行う
(3) 行動が改まらなければ懲戒処分を検討する
(4) 雇用契約の解消(解雇・退職勧奨など)を検討する
2 雇用契約解消の4 つのパターン
(1) 解 雇
(2) 合意退職(会社からの申出による)
(3) 合意退職(従業員からの申出による)
(4) 辞 職
(5) 会社都合退職か自己都合退職か
3 パワーハラスメント
(1) パワハラの定義
(2) パワハラの6 類型
(3) 基本のパワハラ対策
(4) 協力会社との関係におけるパワハラ対策
(5) パワハラ対策の難しさとは
(6) 真のパワハラ対策とは
4 就業規則で罰則を厳しくすれば労務トラブルは防げるのか
巻末資料
1 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37 号告示)に関する疑義応答集(抜粋)
2 労働基準法研究会報告 労働基準法の「労働者」判断基準について(抜粋)
著者情報
郡司 果林
郡司, 果林, 1974-