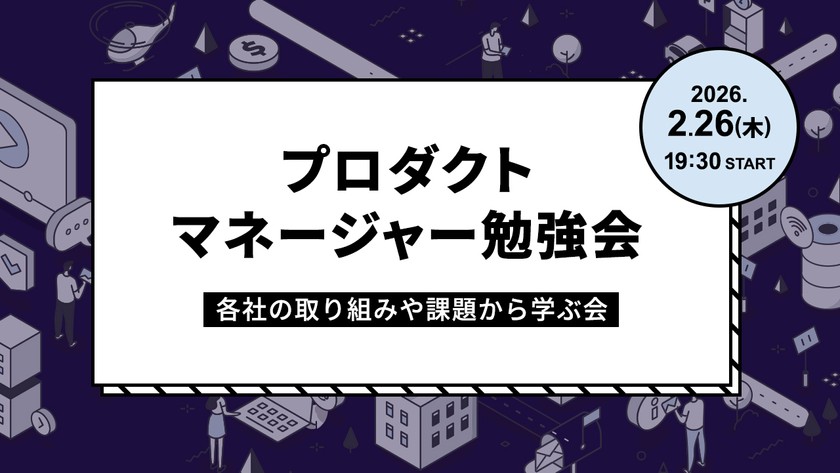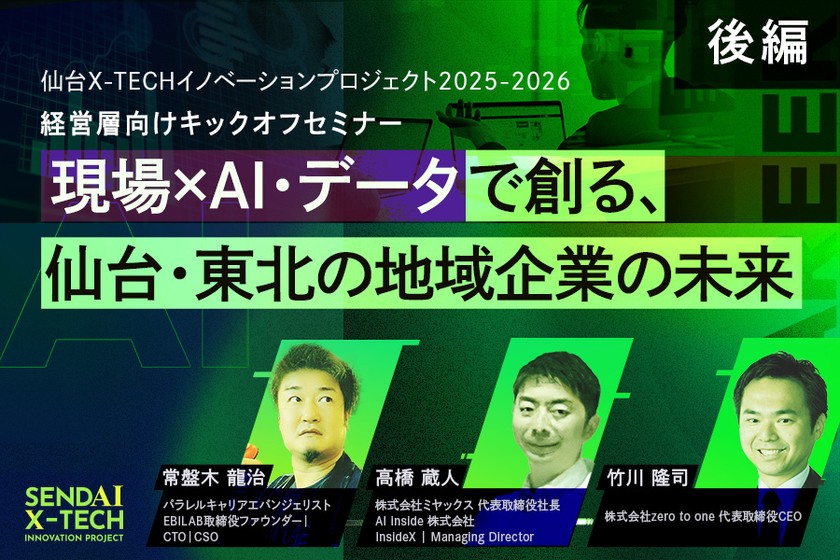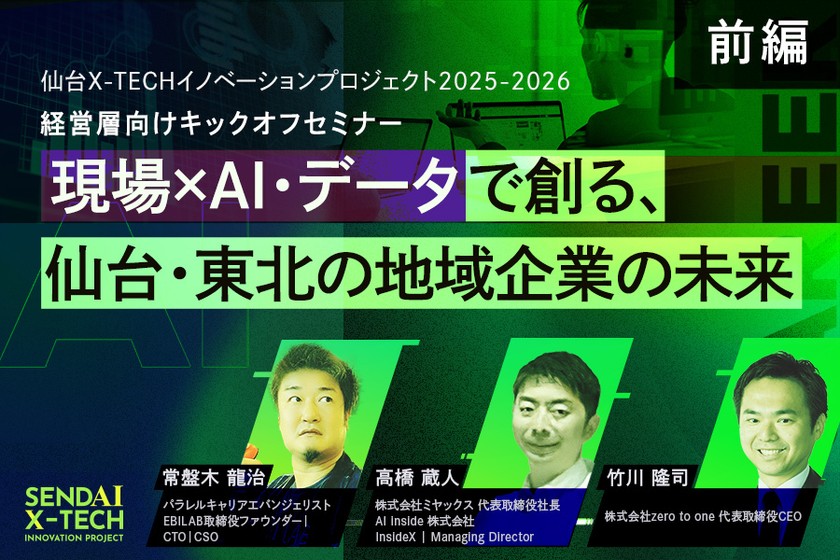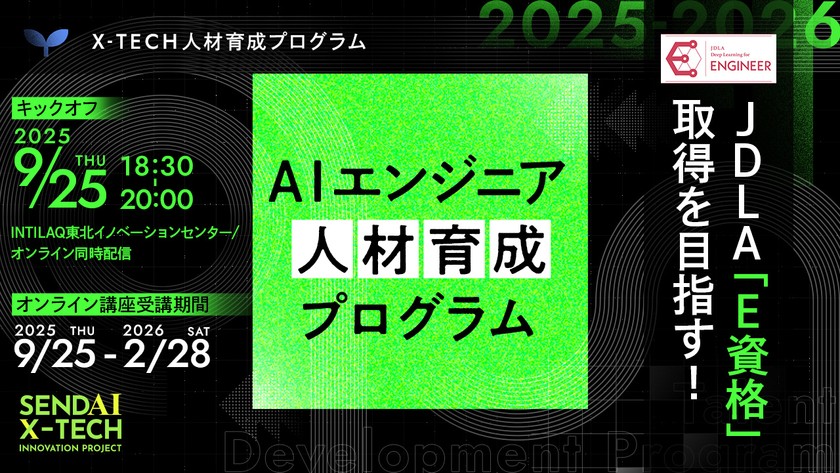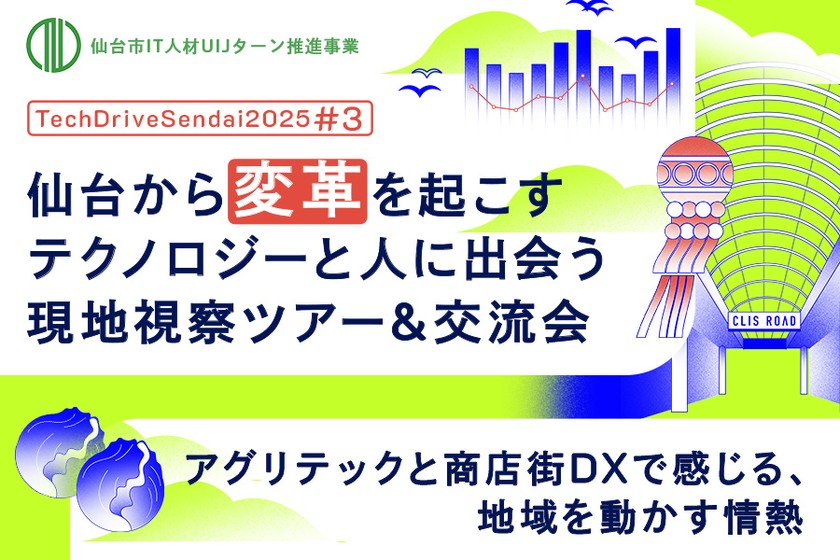仙台X-TECHイノベーションアワード2025──地域経済・社会活性化の基盤作り。PBLでAI・データ活用は実装フェーズに
新たなイノベーションが次々と生み出され、社会実装されることで地域経済の力強い成長はもとより、市民が心豊かに暮らせる社会の実現につながる──。技術横断型のイノベーションを軸に「日本一のAI-Ready都市・仙台を目指す」をミッションに2018年から進化を続けている「仙台X-TECHイノベーションプロジェクト」。2024年度の活動を締めくくるイベント「仙台X-TECHイノベーションアワード2025」が2月28日に開かれた。その全体をレポートする。すそ野が広がる仙台・宮城のAI・データ活用人材
アワード冒頭は、仙台市の郡和子市長が「仙台市のX-TECH事業で掲げるパーパス”LIFE IS YOUR TIME.(人生はあなたの時間)”に込められた、自分自身の時間を心地よく過ごせる街、自分でライフスタイルを選択できる街の実現に向けて、本日のイベントが未来への新たな一歩になることを祈念したいと思っています」とメッセージを寄せた。
それを受けて、仙台市経済局イノベーション推進部部長・白岩靖史氏が、「4年間で延べ人数3,000人を超える方々に、このプログラムに参加していただいている。仙台東北で新しいさまざまなチャレンジに積極的に取り組んでいただける企業が多いことを本当に嬉しく思っています」と挨拶した。
 仙台市 市長 郡和子氏
仙台市 市長 郡和子氏

仙台市経済局イノベーション推進部部長 白岩靖史氏
2018年に始まったプロジェクトは、ミッションとして①AI人材人数地方都市No.1②X-TECH活用事例30件③X-TECH仙台モデルの実現を掲げた。
プロジェクト全体のコーデイネートを務める株式会社zero to oneの竹川隆司氏によれば、AI・データ利活用人材の育成については、2022~2024年の実績だけでも、G検定・E検定の合計で100名が誕生しているという。
宮城県における両検定・資格の累計合格数は、全国都道府県の中でもトップ10をうかがうところまで上がってきており、AI人材は確実にそのすそ野を広げている。また、この間プロジェクトを通して生まれたAI活用アイデアも39件と、当初のKPIを超えた。
 株式会社zero to one 竹川隆司氏
株式会社zero to one 竹川隆司氏
2024年度もデジタル庁の樫田光氏を招いて「データインフォームド」について学び、2024年7月のキックオフを皮切りに、人材育成とビジネス創出支援の2つの柱で各種イベントやワークショップなどを開催。新たに100社以上、延べ500人を超える人々がこのプロジェクトに参加したという報告があったという。

PBL——企業課題解決に学生・社会人チームが取り組む
イベントではまずPBLチームによる取り組み紹介と成果発表が行われた。PBLは2024年度から新たに取り組まれた「Project Based Learning(プロジェクトベースドラーニング)」のこと。地域の企業の課題に対して、これまでX-TECH事業に参画してきた地域の社会人や学生がチームを組み、企業と協力しながら解決に取り組んで、ビジネスの創出を行う。
業務改革や新ビジネス創出という成果も大事だが、その創出プロセスを通じてAI・データを用いた課題解決のための実践的なスキルを取得することも重視されている。
今回は株式会社ホテル佐勘、お茶の井ケ田株式会社、株式会社舞台ファームの3社がPBLに参画。2024年11月のキックオフイベントで三者三様の課題が提示されたのち、地域コーディネーターの伴走を受けながら、3ヵ月にわたって課題の洗い出しや、ビジネスモデルの構築、AI・データ活用によるソリューション実装に取り組んだ。
「データ活用で実現する新しい秋保ヴィレッジ」をテーマにしたお茶の井ケ田チームは、同社が仙台市郊外の秋保(あきう)温泉で運営する物産館と周辺店舗を含めた地域の活性化に取り組んだ。
そのためには秋保地区への来訪者数データなどを活用したいところだが、必要なデータがなかったり、使いにくかったりするという課題に直面する。
だが、そこで諦めるのではなく、今あるデータでできること・データを集めたらできることに課題を分解。前者では需要予測と実績を組み合わせることで、需要予測の精緻化が図れることを実証。さらに、今後データを集めることで実現可能な、デジタルツインを活用した新しい秋保ヴィレッジのビジョンを示すことができた。
 プレゼンするお茶の井ケ田チーム
プレゼンするお茶の井ケ田チーム
舞台ファームは、1日最大5万株を収穫できるレタスの植物工場を運営している。植物工場では光や温度など環境変数を調整することで栽培のコントロールが可能で、これまで環境変数のデータや栽培データを蓄積してきた。
ただ生育環境に必要な環境変数は一部、人の感覚に依存しているところもある。今回のPBLチームは、生育状況を環境変数から事前に予測し、数値で示すという理想の状況に近づけるために、画像情報からレタスの重量を予測し、環境センサデータからレタスの生育予測をするAIを開発した。
実際の工場の出荷レーンへの実装には課題が残るものの、新しい管理システム実現に向けて、すでにPoC実証が始まっている。

プレゼンする舞台ファームチーム

プレゼンするホテル佐勘チーム
3番目のホテル佐勘チームのプレゼンは、「ハーフビュッフェ形式を最適化する、デジタルオーダー&調理最適化システム」だ。
ホテル佐勘は寛永2年(1625年)創業の長い歴史を持つ温泉旅館。ビュッフェの自由度とオーダー制の料理のクオリティを両立した食事提供スタイル「ハーフビュッフェ」への取り組みも早い。ただ、この形式では厨房からお客様のテーブルへ料理を提供するタイミングがわかりづらい、お客様もオーダーした料理がいつ届くか分からない、という課題を抱えていた。
そこで、お客様がメイン料理を自身の端末からオーダー。調理・運搬が始まると、提供タイミングが表示され、ベストなタイミングで会席料理を手元に届けることのできるアプリ開発に取り組んだ。従業員を対象にプロトタイプを使った効果実証も進めた。
データ蓄積・AI活用による顧客満足度の更なる向上を目指して実証は継続的に行われているという報告があった。
現場に足を運び、課題をリアルに実感すること
プレゼンテーションに次いで行われたPBL総括トークセッションでは、後半のビジネスコンテストの審査員も務める、東京大学未来ビジョン研究センター客員教授・株式会社IGPIグループ シニア・エグゼクティブ・フェローである西山圭太氏、デジタル庁 Head of Unit, Fact & Data の樫田光氏、東北大学理事・副学長・プロボスト・CDOの青木孝文氏、石巻専修大学経営学部教授(観光学)の庄子真岐氏を交え、議論が行われた。
 PBL総括トークセッションでの審査員たち
PBL総括トークセッションでの審査員たち

PBL総括トークセッションでの企業3社
樫田氏は「現場に足を運ぶとか、実際にサービスとかプロダクトを使ってみることが大事。今回のPBLでは、実際に自分でレタスを作ったりとか、ホテルで食事されたりと、現場に身を投じる中で見つけた、リアルにありそうな課題を解いていらっしゃるんだなと思ってすごく迫る感じがした」と、述べた。
庄子氏は「地域で課題解決するのは積み重ねだが、それだけだとその延長線上にしか地域の未来がない。もっと目指す目標を高く、食料自給率50%ではなく100%を目指していただきたい」と、エールを送った。
青木氏は、デジタルで価値を生み出していくことの重要性をあらためて指摘。「温泉旅館のような日本独特のサービスは、実際裏ではかなり複雑なことをやっているが、そのシステム化がデジタルで可能になるということをホテル佐勘の例は示している。ホスピタリティの高いレベルをデジタル技術がイネーブラーにして、さらに高度なものに生まれ変わらせる。これはおそらく日本にしかできないものだ」と語った。
コーディネーターの竹川氏からは、ビジネスの手法で地域課題の解決に取り組み、社会的インパクトを生み出しながら収益を確保する「ローカル・ゼブラ企業」の重要性や、同氏が代表を務めるzero to oneが今年度中小企業庁から選定された「ローカル・ゼブラ事業」にて仙台X-TECHの社会的価値計測に取り組んだ事例が紹介された。
「人材育成と産業活用支援で地域を元気にする仙台X-TECHプロジェクトもその一つだが、それを確かなものにするには、事業の成果を定量的・定性的に実証する必要がある。私たちは地域のGDPや税収データ、各種検定やITパスポート取得者数の推移など60以上のデータを20年分蓄え、その因果関係を調べているところだ。
すでに、E資格の人を20人増やしたら税収が20年で2,000万円向上する、というような試算結果も出ている。IT人材を増やすことが企業にとって本当に役に立ったのか、より具体的には利益率の向上に繋がったのかを実証していくことがこれからの課題だ」と、述べた。
なお、PBLの成果発表については、審査の結果、舞台ファームに最優秀賞、お茶の井ケ田とホテル佐勘にそれぞれ優秀賞が授与された。
AI・データ活用の新規ビジネスプランを競う
イベントの第2部では、AIを利活用した新たなビジネスプランや既存事業の高度化に関するアイデアに取り組む、7社のプレゼンテーションが行われた。以下、発表順に概略を紹介する。審査の結果、最優秀賞(☆)にCiel、優秀賞(★)には坂部印刷とLaboRoboが選ばれた。
●男性客がもっと洋食屋さんに行きたくなるインタラクティブサイネージ
提案者:アルプス システム インテグレーション株式会社 羽田健一氏

羽田氏の趣味の一つに食べ歩きがあるという。この趣味をベースに膨らませたのが「男性客がもっと洋食屋さんに行きたくなるインタラクティブサイネージ」のアイデアだ。
羽田氏が食べ歩きのフィールドとする仙台市、大崎市の洋食店では、なぜか男性の一人客は珍しい。しかし、男性がグルメ・洋食に興味がないわけはない。
そこで、着想したのが、漫画的手法で洋食をアピールしたら、もっと男性も洋食に興味を持ってくれるのではないかというものだ。
漫画的手法とは例えば、季節・天候・時間情報からAIがおすすめ料理を「料理バトル」という形式で提案することだ。サイネージに能動的に触れてもらうことで、洋食に対する欲求を高めることが狙いだ。
おすすめ料理については、各店舗の季節ごとの売れ筋情報などを学習データとして用い、店舗とメニューについてはRAGを用いる。サイネージと実店舗を、クーポン券やポイント付加のサービスでつなぎ、人手不足の店舗や接客が苦手な店主向けにサイネージを利用した接客AIを導入する構想も語られた。
仙台の目抜き通りで自社製のサイネージを用いて実証実験も行った。今後は、サイネージのUIを改善しながら、洋食店に特化したサイネージシステムの構築や、将来的には他のグルメコンテンツも充実させ、グルメシティ仙台を実現したいと提案した。
☆新卒高校生向け就職サービス「Ciel」
提案者:株式会社Ciel 代表取締役 村上和隆氏
高校生の就活の仕組みは大学生などと異なり、企業が学校に求人票を送付。学校の進路担当教諭が生徒に求人を紹介。生徒はあくまでも学校を通じて応募するという流れになっている。
しかも学校推薦が基本で、推薦は一人一社という暗黙のルールがある。職業選択の自由が保証されていないともいえる。デジタル処理も遅れており、県外からの採用ができない、生徒たちとのコミュニケーション以前に進路担当者への根回しに腐心するのは筋が違うという、企業からの声もあるという。
そこで、山形大の院生が24年に起業したCielが提案するのが、同社が提供するプラットフォームが進路指導室の替わりになって、高校生と企業を直接つなぐマッチングアプリだ。生徒はそのアプリを使って企業を発見するだけでなく、企業研究を深めることができ、また最新のAIのサポートを得ながら企業担当者と直接チャットすることもできる。
高卒採用市場は4.7兆円もあり、採用領域において唯一のブルーオーシャンで、ダイレクトリクルーティングの事業チャンスがあるという。求人事業に関しては厚労省の協定ルールがあるが、同社は事前にそれに抵触しないと厚労省に確認を取り付けている。
その上で、すでに東北4県にサービスで実証中だ。中小企業にとっても、自社の強みの言語化や人材の明確化が図れ、学校にとっても進路指導業務のムダを省くことができる。的確な高校生人材と企業のマッチングを促すことで、地域産業をより活性化することにもつながる。こうしたビジネスモデルの確かさが、最優秀賞につながった。
●為替予測AIで実現する観光資源の最適活用戦略
提案者:株式会社FleGrowth 上野俊訓氏

これは金融に関するシステムの開発・販売・運用保守などの業務を行う企業からの提案である。東北のインバウンド需要は活発だが、円安という状況も影響要因で、これがいつまで続くのかは不透明だ。
提案者は国・地域別の訪日外国人旅行者数に対する為替の影響度を調べ、為替レートとインバウンド消費には明確な相関関係があることを確認。今後の為替レート次第では、消費金額が減ったり、訪日外国人自体が減ったりする可能性があると指摘する。
為替を予測できれば需要の変動に備えることができるのではないかというのが提案の問題意識だ。同社は「為替予測AI」のアルゴリズムを開発し、予測結果をユーザーに提供するビジネスを発案した。このシステムを活用することで、観光業ではターゲット市場への戦略的シフト、通貨変動に応じたプロモーション、ダイナミックプライシングの最適化、為替リスクヘッジにつながると言う。
その活用イメージは、観光事業者だけでなく、地域イベント主催者や行政にまで広がる。現在は為替予測モデルのUI/UXの改善や予測精度の検証などに取り組んでいるが、いずれはAPIを開放し、クライアントアプリケーションも開発、最終的には広告による収益化を目指している。
高等学校の為替トレードの授業で使ってもらったところ、デモアプリを使ったチームはそうでないチームに比べ大きな模擬的収益を得られたという。
●「過去の資産を未来の力へ」老舗建設機械レンタル業のデジタル変革
蔵王リース株式会社 取締役営業本部長 平間慎一郎氏

蔵王リースは東日本に多数の拠点をもつ建機レンタルの会社。建設現場の状況は天候、トラブルなどで日々刻々と変わるため、リース会社も機械の在庫管理や需要予測が困難だ。現在は社内業務システムのデータを見ながら試行錯誤で対応している。
しかし、これが帳票形式のため、情報を動的につかむのが難しく、出力にも時間がかかっている。結局は「経験と勘」に頼りがちだ。
同社ではBIツールのTableauを用いて誰でもどこでも使える分析環境を構築。直感的な操作が可能なダッシュボードを使うことで、数字を図やグラフに落とし込みやすくなった。
導入効果はすぐに現れ、営業利益率のデータ確認だけでも1日3時間かかっていたところが、15分に短縮。ダッシュボードでマーケット情報と社内データを比較することで、どの分野の顧客にアプローチすべきかも可視化されるようになった。
今後は工事進捗状況と機材利用状況を掛けあわせたデータ分析を進め、社内では新規顧客の開拓、社外向けには建機レンタル費用の削減につながるようなサービスに育てたいとしている。
さらに将来の展望として、工事現場向けのサブスク型レンタルプランを整備し、最適な機材×タイミング×コストをデータとして把握することで、人手不足など建設業界の課題を解決したいとしている。
★生成AIを活用したお客様課題を解決へと導く自社業務の高度化
坂部印刷株式会社 代表取締役社長 坂部経洋氏

坂部印刷は山形市の本社の他に、仙台にもオフィスを持つ創業144年の老舗印刷会社である。近年は、Webサイト構築、SNSマーケティングなどのブランディング、伝票や資料作成支援などの業務DX支援サービス、そして販促・広報ツール・カタログ・マニュアル制作などものづくりの3つの事業でソリューションを提供し、顧客課題を解決している。
近年はこれらを統合したワンストップサービスを標榜しているが、そこでの目玉になるのが「AIとの協働」によるDXだ。具体的には、生成AIを用いた画像・動画生成でクリエイティブ力を強化。また、文章生成AIを活用した提案書作成や市場調査なども業務として提案している。
これらのAI活用の前提としては、社内データベースの整備・効率化など、社内業務DXによる属人化からの脱却が重要だという認識だ。これまでは毎年約6000件の案件に関する情報は、複数の場所で管理され、かつ属人化していた。
顧客企業とデザイナーとの原稿授受や指示出しも、口頭またはメールなのが現状だ。そこで、社内各所に散らばっている情報資産を複合データベースに集約し、有効活用できる仕組みを構築しつつある。今後は社内業務改善の成果を外販化し、業務プロセスDXサービスの提供を顧客向けに展開していきたいとしている。
顧客の悩みや課題に寄り添い、課題に対する解決策の一環としてAIソリューションを強化した例は、必ずしも派手ではないものの、等身大の地道な努力の成果として高く評価され、優秀賞を授与された。
★LabNeeds-研究自動化プラットフォーム-
LaboRobo 代表 奥山彪太郎氏

高コスト・低柔軟性が、研究機関の実験系研究者が抱える実験の効率化と自動化の課題であるとして捉え、課題を克服した自動化技術を提案するのが、LaboRoboだ。
研究室向けの自動化装置はすでに存在するが、通常そのコストは数百万円から数億円に及ぶ。汎用的すぎる、または専門的すぎるため、既存の装置では個々の実験のニーズに対応できないことが多い。システム導入には専門知識が必要であり、故障した装置のメンテナンスは困難。自動化装置の営業も、現在は学会や研究論文に頼っており、より効率的な顧客開拓が望まれている。
同社は、低コストかつ柔軟にカスタマイズ可能で、オーダーメイドされた自動化装置「ARALA」を開発。既存のロボットアームの先端部品を組み替えて、薬品移動の作業を自動化した。
さらに研究者の課題を集め、それをエンジニアとつなぎ、実験の自動化を加速するオンラインプラットフォーム「LabNeeds」を構想する。研究者が「実験を自動化したい」という課題を投稿するだけで、開発メーカーのエンジニアが低コストでカスタマイズ可能な自動化装置を研究室に提供。研究者は本来の「考える仕事」に専念できるようになる。
研究者の課題をヒアリングして、企業のリソースと橋渡しする役目を研究室の大学生に担わせるというアイデアもユニークだ。ヒアリングの補助として、AIエージェントの活用も提案している。すでに東北大学で成功事例を作りつつあり、これを全国の大学に横展開するのが目標だ。
同社が描くビジネスモデルでは、研究室の自動化市場は18兆円を超え、同社の事業が実際にアプローチできる顧客の市場規模(SOM)は364億円規模と見積もられている。
まず低コストでカスタマイズ可能な自動化装置を作れるエンジニアを増やし、その力を「LabNeeds」上でネットワーク化したいという。研究機関の実験自動化というニッチながらも広大な市場に着目し、ビジネスプランを緻密に練り上げている点が、優秀賞の理由だ。
●ノーコード革命!建設業の現場を変えるAppSheet DX戦略
成和建設株式会社 取締役常務 小田島裕樹氏

岩手県花巻市で建設、産廃、農業土木の各事業に取り組む成和建設。自社のDX化を目指すきっかけになったのが2020年問題だ。建設業界にも時間外労働上限規制が適用され、今までのような働き方ができなくなった。
むしろこれを、社内DX化するための好機と捉えシステム開発に取り組んだ。そこでわかったのは、建設業特有の勤務形態では既存のアプリで対応できないこと。自分たちが使いやすい勤怠管理システムを可能な限り短期間に開発するために、あえてノーコード開発にチャレンジした。
Googleのノーコードツール AppSheet とデータウェアハウス BigQuery、ビジネス情報可視化ツール Looker Studio などを連携させたシステムだ。現在、社員手帳、タイムカード、除雪支援、案件管理の4つのアプリが稼動している。
開発・導入プロセスでは、そのメリットを理解できない社員もおり、退職者も生んだという。しかし、アプリ導入前は事務員が6日間1270時間かけて行っていた勤怠管理情報の集計業務が、アプリ導入後は大幅に削減。圧縮時間は790時間となり、特に事務員の負担を軽減することができた。今ではそのメリットを感じる社員がほとんどだという。
より安価により簡単に自分の会社に合うアプリを作ることができれば、どの会社も労働時間の圧縮に加え、情報の一元化・共有化を容易に行うことができる。自社での運用を目的として作ったアプリだが、今後は建設業だけでなく業界を超えて幅広く運用していけるものではないかと、提案者は語っている。
地域課題に敏感な「変人たち」が仙台の街を変えていく
イベントでは、この後に昨年度受賞企業・団体プレゼンテーションとして、匠ソリューションズ株式会社の佐藤大知氏が「エッジ×LLMの対話接客AIの進展に関して」、MARUMORI-SAUNA株式会社の本多智訓氏が「Public Sauna_DAOのその後とこれから」、MUSASI D&T株式会社の佐藤里麻氏が「地域をつなぐ、半径500メートルの情報発信・私のまちの情報局」と題して、それぞれ簡単な報告を行った。
イベントの最後に、審査員から今年度アワードの総評と仙台X-TECHプロジェクトの今後に関して展望が述べられた。
「東北の人というと、真面目な感じで大人しい、話にオチもないという先入観があったが、これが覆った。東北にもこんなに変わった面白い人たちが大勢いる。
一般的に日本のイノベーションは西高東低の傾向があるが、東日本ではあるが仙台だけは異常なぐらい盛り上がっている。今後も突出した異常値を示しつづけるようにチャレンジを続けていただきたい」(西山圭太氏)
 東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授 西山圭太氏
東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授 西山圭太氏
「AIやデータは手段に過ぎないんじゃないかなと、この場に来るまでは思っていた。しかし、製造業からサービス業まで、あるいは接客シーンなどあらゆるところに使える万能な手段なのだと、あらためて認識できた。
しかも、自社の課題解決目的で作ったシステムを同じ課題を抱える他企業にも使ってほしいとか、それが地域課題につながるとか、WhatからWhyを広げていく視点も得られて、仙台ひいては宮城県のX-TECHイノベーションに大きな可能性を感じた」(庄子真岐氏)

石巻専修大学経営学部教授(観光学) 庄子真岐氏
「課題があるところに人は集まってくる。課題を解くためのツールや技術レベルも上がっている。これからの時代に一番重要なのは、難しいけれど面白くて、人のためになる課題を見つけることのできる人たちだ。
かつ、課題をみんなで解こうよとリーダーシップを発揮し、その課題がなぜ解くべき価値があるかを人に伝えることができる人間だ。AI・データの時代だからこそ、あらためて人間こそが最も貴重なリソースになりうるのだと思う」(樫田光氏)

デジタル庁 Head of Unit, Fact & Data 樫田光氏
「かつては大企業や大学という組織が、世の中を変えていく原動力だったが、今は個人が変えていく時代だと思う。個人が社会を変える原動力になる。例えばスタートアップもそうだし、ソーシャルイノベーターもそうだ。
それから企業の中でDXを推進するときも、それを担う担当者の熱い思いが組織を変えるということがありうる。人からは変人と言われるかもしれないけれど、そういう変人こそが社会を変えると、今回のイベントに参加してあらためて実感した」(青木孝文氏)

東北大学 理事・副学長(企画戦略総括)・プロボスト・CDO 青木孝文氏
会場にはリアル・オンライン合わせて約150名が参加。リアル会場は立ち見もでるほどの盛況で、終日熱気に包まれた。チャレンジャーたちこそが仙台をもっと面白い街にしていく——。参加者全員がその思いに共感しながら、仙台X-TECHイノベーションアワード2025は終了した。

おすすめイベント
関連するイベント