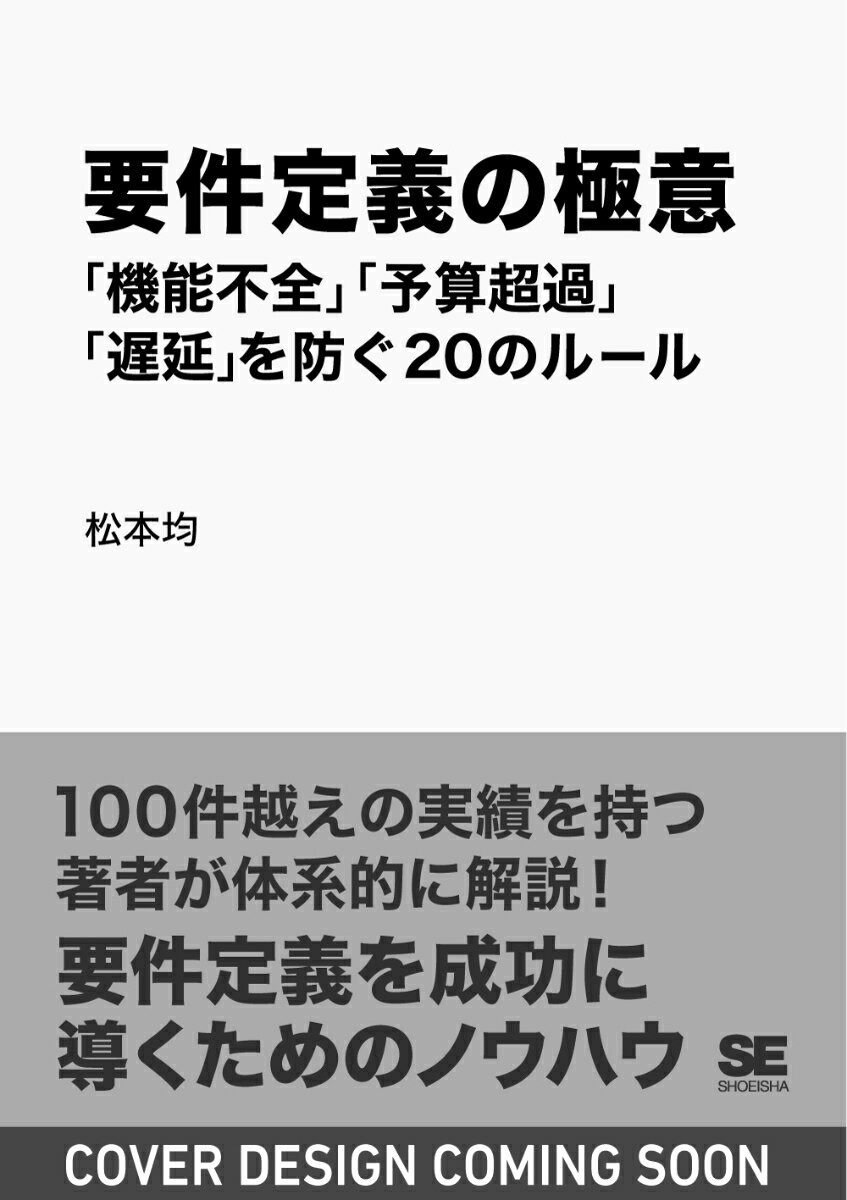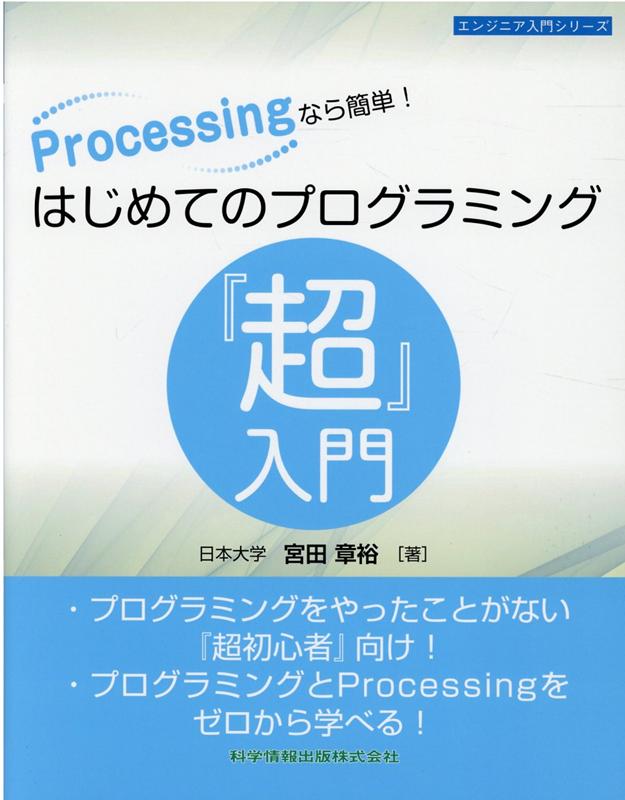
2,970円 (税込)
楽天Processingなら簡単! はじめてのプログラミング『超』入門
書籍情報
発売日:
著者/編集:宮田 章裕
出版社:科学情報出版
発行形態:単行本
書籍説明
内容紹介
プログラミングをやったことがない『超初心者』向け!プログラミングとProcessingをゼロから学べる!
目次
第1部:プログラミングの基礎
1 プログラミング入門
1.1 本章の概要
1.2 はじめてのプログラミング
1.3 バグ
1.4 コメント
1.5 本章のまとめ
1.6 演習問題
2 計算
2.1 本章の概要
2.2 基本的な計算
2.3 演算子の優先順位
2.4 高度な計算
2.5 本章のまとめ
2.6 演習問題
3 変数
3.1 本章の概要
3.2 変数の必要性
3.3 変数とは
3.4 型変換
3.5 本章のまとめ
3.6 演習問題
4 描画
4.1 本章の概要
4.2 Window
4.3 単純な図形の描画
4.4 変数を用いた描画
4.5 本章のまとめ
4.6 演習問題
5 条件分岐
5.1 本章の概要
5.2 真偽値と比較演算子
5.3 if文
5.4 else文
5.5 else if文
5.6 論理演算子
5.7 入れ子構造のif文
5.8 本章のまとめ
5.9 演習問題
6 繰り返し
6.1 本章の概要
6.2 高度な代入演算子
6.3 インクリメント/デクリメント演算子
6.4 while文
6.5 for文
6.6 while文とfor文の比較
6.7 本章のまとめ
6.8 演習問題
7 配列
7.1 本章の概要
7.2 配列変数の宣言・代入・参照
7.3 配列の走査
7.4 配列の基本的な利用例
7.5 配列の応用的な利用例
7.6 本章のまとめ
7.7 演習問題
8 アニメーション
8.1 本章の概要
8.2 アニメーションの原理
8.3 単純なアニメーション
8.4 インタラクティブアニメーション
8.5 本章のまとめ
8.6 演習問題
第2部:関数を用いるプログラミング
9 関数入門
9.1 本章の概要
9.2 関数の基礎知識
9.3 引数・返り値がない関数
9.4 引数があり、返り値がない関数
9.5 返り値がある関数
9.6 変数のスコープ
9.7 複数の関数の利用
9.8 関数設計のガイドライン
9.9 本章のまとめ
9.10 演習問題
10 関数による処理の再利用
10.1 本章の概要
10.2 重複処理の関数化
10.3 汎用処理の関数化
10.4 本章のまとめ
10.5 演習問題
11 関数による処理の抽象化
11.1 本章の概要
11.2 複雑な処理の関数化
11.3 本質的でない処理の関数化
11.4 本章のまとめ
11.5 演習問題
12 再帰関数
12.1 本章の概要
12.2 再帰関数の概念
12.3 返り値がない再帰関数
12.4 返り値がある再帰関数
12.5 本章のまとめ
12.6 演習問題
著者情報
宮田 章裕
宮田章裕(みやた あきひろ)
2008年慶應義塾大学大学院後期博士課程修了。
日本電信電話株式会社(NTT研究所)などを経て、2016年より日本大学文理学部情報科学科准教授。
ヒューマンコンピュータインタラクションの研究に従事し、IoT、ニューラルネットワークなどを駆使して「人にやさしいコンピュータ」の実現を目指して情熱的に研究に取り組んでいる。
ACM会員、情報処理学会シニア会員。
博士(工学)。
宮田, 章裕





![[令和8年度]ITパスポート&基本情報技術者 超効率の教科書+よく出る問題集 2冊セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2326/2100014832326.jpg)