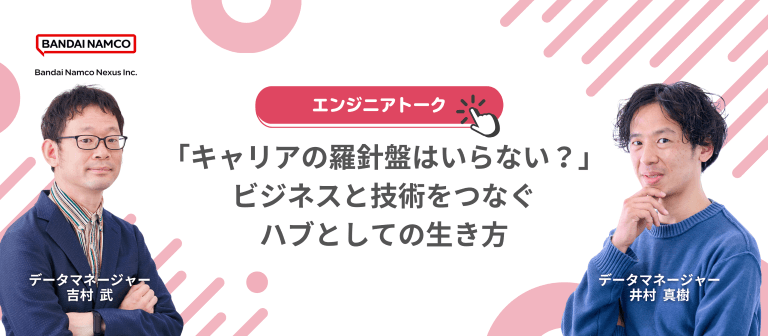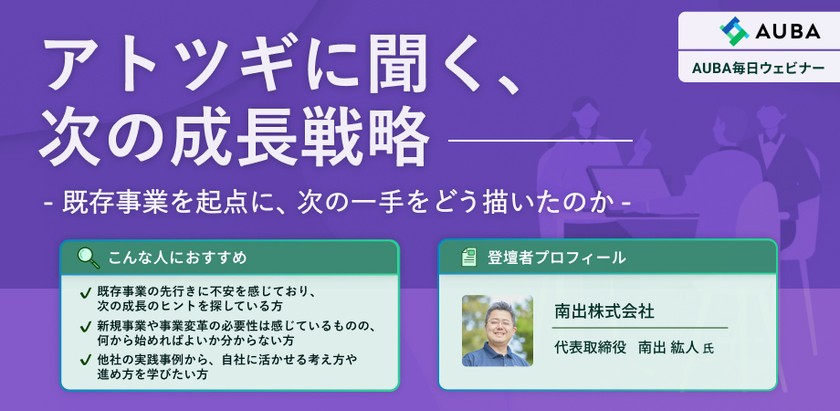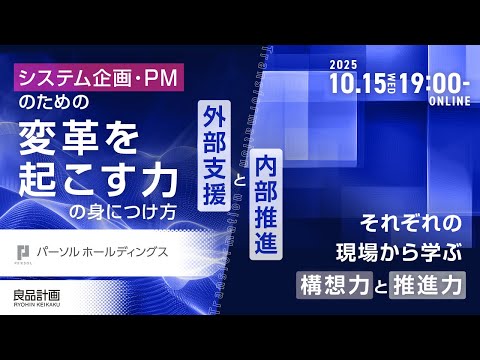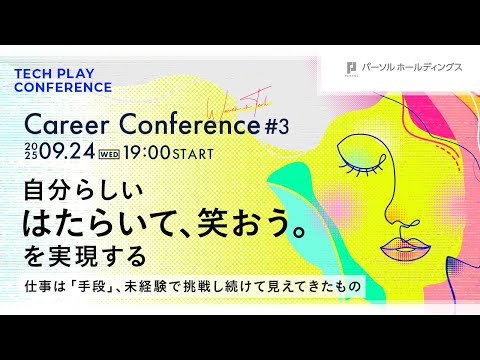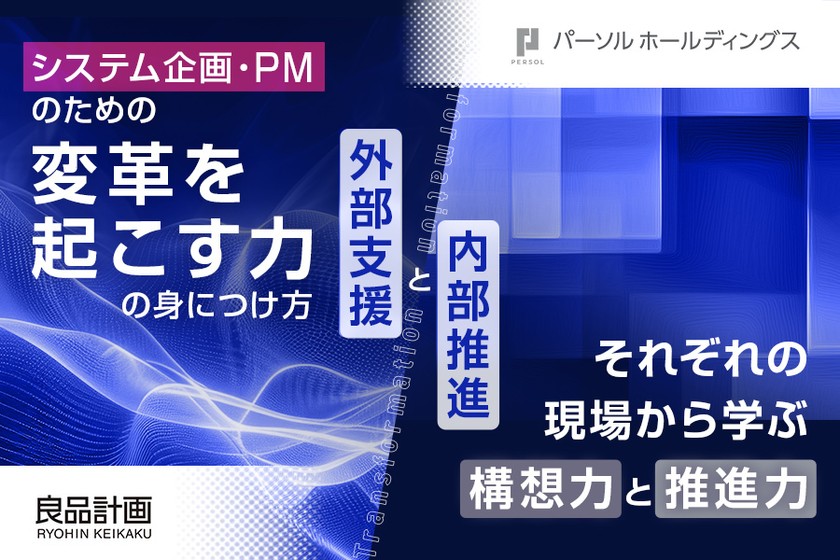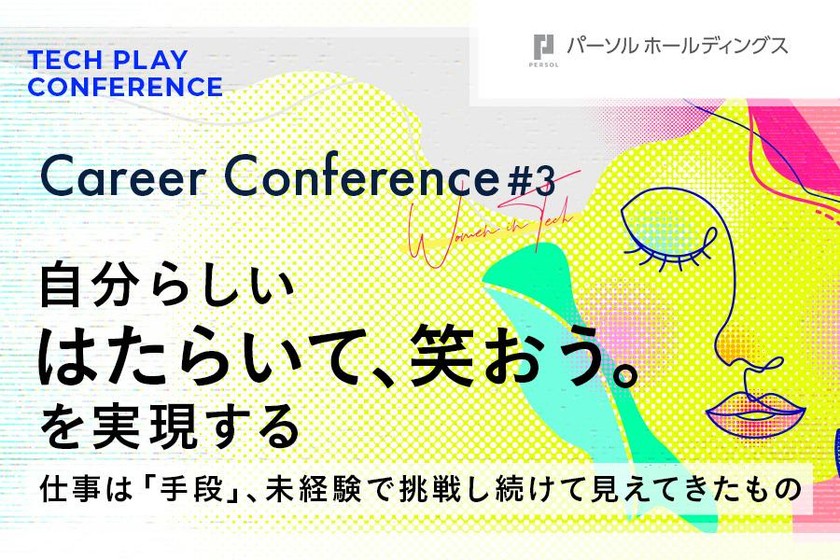ITエンジニアが働きやすく、定着する組織の条件とは? ──パーソル総研調査とレクター広木氏との対談から考える
ITエンジニアにとって働きやすく、定着するのはどのような組織か──。パーソル総合研究所は、ITエンジニアとそれ以外の職種、計2500名を対象に「ITエンジニアの人的資源管理に関する定量調査」を実施した。調査結果をもとに、「エンジニアリング組織論への招待」(技術評論社)の著者であり、数多くの企業の技術組織アドバイザリーを務めるレクター広木大地氏と調査を担当した岩本慧悟研究員が、ITエンジニアの仕事観や最適な就業環境について議論を行った。株式会社レクター 取締役 広木 大地氏(写真右)
筑波大学大学院を卒業後、2008年に株式会社ミクシィに入社。同社のアーキテクトとして、技術戦略から組織構築などに携わる。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。株式会社レクターを創業し、技術と経営をつなぐ技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っている。著書『エンジニアリング組織論への招待 不確実性に向き合う思考と組織のリファクタリング』。
パーソル総合研究所 研究員 岩本(大久保)慧悟(写真左)
東京未来大学モチベーション行動科学部を卒業後、東洋大学大学院 社会学研究科社会心理学専攻 博士前期課程 在籍中。2016年、ディップ株式会社に入社。アルバイトや若手社員の就労に関する調査、新規HRテックサービス新規企画・開発、社内外の人事データの利活用などに従事。社会科学的なアプローチから、より良い「はたらく」の実現に貢献したいと思い、2020年3月より現職。専門は、社会心理学・産業組織心理学。
【入社理由】ITエンジニアが会社選びで重視するのは「安定」と「技術成長」
岩本:今回は、ITエンジニアの採用・定着・仕事観・キャリア構築の実態や特徴を、他職種との比較を通じて明らかにすることを目的に、ITエンジニア1600名とそれ以外の職種の900名、合計2500名を対象に調査を実施しました。
まず、ITエンジニアの入社理由を聞いたところ、「安定して働けそうな環境だと感じたから」が53.8%、「成長できる環境と感じたから」が40.4%、「技術を伸ばせる環境だと感じたから」が38.3%、という結果となりました。

【就業意識】ライバル意識ではなく、リスペクトと仲間意識が強い
実際に働いてみた就労意識に関する調査では、他職種との比較も行いました。すると次の3つの項目で、ITエンジニアと他職種のギャップが見えてきました。
・自社の事業・サービス内容に愛着が薄い
・大きな責任を伴う仕事がしたくない
・同じ職種の人に対して、ライバル意識が薄い

広木:まず、ライバル意識についてですが、私は普段から「ソフトウェアを開発する行為自体がコミュニケーション」だと話しています。抽象的で曖昧なビジョン段階から、綿密に動くプログラムを開発するには、全てのITエンジニアが解釈できるコードや工程が重要で、その実現には、コミュニケーションがついてまわるからです。
逆の言い方をすれば、コミュニケーションがうまくいっていない環境では、いくらスーパーエンジニアがいても、開発はスムーズに進みません。
つまり、開発の仕事ではチームプレイならびに人間関係の構築が、重要かつ基本事項であり、そのために多くのITエンジニアはライバル意識を持ちにくいのだと思います。また、自分よりも優れたITエンジニアを尊敬する傾向もあり、ライバル視よりもリスペクトする意識が高いと思います。
岩本:ITエンジニアは勉強会なども他職種と比べると積極的ですし、お互いが助け合ってプロジェクトを成功に導く仲間意識が強いことは、私も以前から感じていました。今回改めて、明らかになったと感じています。
広木:一方で、仕事への「責任」や「愛着」が乏しいとの結果については違和感を覚えました。たとえば「責任」という言葉に関して言えば、エンジニアはやることが変わらないのであれば、「大口の案件だから」「大企業の案件だから」などの理由で仕事へのモチベーションが大きく変わることは少ないです。でも、「責任重大だから」などと言われてプレッシャーを感じることはあるかもしれません。
そういったことから「大きな責任を伴う仕事をしたいですか?」という質問に対して、「責任」という言葉を「絶対にバグを起こしてはいけない」仕事だと捉えるのではないでしょうか。だから、他の職種より「責任ある仕事が重要だ」と答える人が少なかったのかもしれません。もちろん、最先端のテーマや社会的に意義のある仕事をやりたいITエンジニアは多いはずです。

▲株式会社レクター 取締役 広木 大地氏
岩本:そうですね。ITエンジニアは、仕事の性質上、「責任」という言葉と、失敗・損失を回避せねばならないというイメージがより強く結びついていそうです。
広木:「愛着」という表現に関しても、その解釈が難しかったのでは、と感じました。愛情という表現はとてもエモーショナルなワードため、ITエンジニアは愛着が低かったというよりも、イエスと答えづらかったのではないでしょうか。
会社やサービスに対して、帰属意識や思い入れの強い方が開発スピードが早まったり、より質の高いソフトウェアができるとのレポートがあります。そのような意識が獲得できている環境は素晴らしいですよね。
岩本:そうですね。以前、ITエンジニアが多い組織で働いていた際、自社のサービスの魅力を熱く語ったり、自分の手がけたサービスの認知度が上がることにやりがいや満足感を感じている人が多かったですね。
【年収】能力や成果に見合った金額でないと転職意向が高まる
岩本:続いて、年収に関する調査結果です。ITエンジニアは希望年収763.7万円に対し、現状の年収は613.6万円と150.1万円のギャップがあるのに対し、その他職種は希望年収769.4万円、現状は約628.0万円と141.4万円のギャップがありました。

また、ITエンジニアの希望年収と現状年収とのギャップは、他職種よりもやや大きく、下限金額とのギャップが大きいというデータも出ています。このことから、ITエンジニアは年収をより多く得たいというよりも、正しく評価してほしい志向があると考えています。
年収と離職の関係についても調べました。ITエンジニアは希望年収とのギャップが高まると転職意向も同じく高まります。一方、他職種は管理職以降がダウンする。つまり、年収ギャップが大きくなるとITエンジニアは外を見るのに対し、他職種は社内で積極的な行動を取ることをあきらめる傾向にあることが考察できます。

さらに、転職意向と年収の金額の関係も調べると、ITエンジニアは他職種に比べ年収が高いほど、転職意向が低いという結果が出ていました。

広木:興味深い調査結果だと思います。実際、いくら優秀なITエンジニアであっても、年齢が若いというだけで、会社の賃金制度上、高い給料をもらえないケースがあるからです。そのような企業からは転職し、実績に見合った報酬がもらえる成果報酬が整った企業に転職したり、惹かれるのは自然だと思います。
岩本:さらに、ITエンジニアの職種別に希望年収と現在年収のギャップを見てみると、「セキュリティエンジニア」「組み込み・IoTエンジニア」「ネットワークエンジニア」、役職別では「テックリード」「アーキテクト」のギャップが大きいという結果が出ています。
広木:高い技術力を持つITエンジニアの評価体制には、まだまだ改善できる余地がありそうですね。

岩本:市場価値に見合った報酬をきちんと提供できる、報酬体系の整備が重要だと感じました。年齢に応じて給与が上がる旧態制度ではなく、ITエンジニアなどの専門スキルを持つ職種には、別の給与体系を設けるなど、柔軟に対応する必要があるのではないでしょうか。
報酬制度が整備されていない企業からは、優秀なITエンジニアが転職してしまうリスクがあることが今回の調査で見えてきましたね。

▲パーソル総合研究所 研究員 岩本(大久保)慧悟
【転職】「エンジニアが転職しやすい」は誤り!?
岩本:世間一般には「ITエンジニアは転職しやすい」というイメージが多かったのですが、それをくつがえす結果も今回の調査では出ていました。ITエンジニアの転職意向が22.4%なのに対し、その他職種は26.9%だったからです。
何らかのきっかけによって、より良い環境に転職するのがITエンジニアの特徴であり、己の技術力を高めるために転々とする人は少数派でした。

広木:会社を転々としたいと考えるエンジニアは、あまりいないと思います。転職は大きな決断ですし、せっかく入社した会社を特に理由もなく、ましてや環境や条件がいいのに辞めるメリットはないですからね。ビジネスパーソンの志向と変わらないと思います。
岩本:どうすればITエンジニアが定着する組織になるのか。この点についても調査したところ、組織に対する疑念や批判的な考えや感情の「組織シニシズム」がポイントであることが見えてきました。


さらに詳しく調査すると、特に社内外どちらにおいても立場が弱い環境にあると、ITエンジニアの組織シニシズムは高まることがわかりました。「期待が薄い」「無理難題をいきなり押しつけられる」「プロジェクトの歯車としか思われていない」「顧客との対応が不平等」などです。
逆に、ITエンジニアの組織シニシズムを低くするには、教育体制の充実、議論できる風通しの良い環境などが重要であることも見えてきました。具体的には、会社やマネージャーが育成に対して理解があり、社外のセミナーや勉強会に会社の負担で参加できる制度などです。
広木:組織シニシズムも含め、全般的に興味深い結果だと思います。私はこれまで、ITエンジニアが心地よいと感じる環境のポイントは、「透明性の高さ」「開発環境」「キャリア投資」だと言ってきたからです。そしてこのような環境整備は、ITエンジニアの転職意向を抑制するだけでなく、採用ブランディングそのものでもあります。
また、ITエンジニアの比率が高くなるほど組織シニシズムが低くなる傾向については、注意深く見る必要があると思います。そもそもITエンジニアが多い、つまりIT事業がコアコンピタンスの企業だから、そのような環境が生まれているのか。もしくは、それは見せかけの因果関係で、ITエンジニアが多い職場は成長性が高く、環境変化が起きやすいベンチャー企業が多いことがこうした相関関係があるのかといった点ですね。
一方で、ITエンジニアの習慣や価値観を、別の職種の方が理解することは難しい。ITエンジニアが少ない環境では、エンジニア同士であればすぐに通じ合い、組織的に取り入れやすいことであっても、マイノリティになってしまう環境では絶対的にコミュニケーションが成立しにくい傾向があると思います。
そのため、エンジニア同士の価値観や文化が醸成されず、結果としてビジネスサイドと対等な関係が築けず、弱い立場になってしまう。すると次第に居心地が悪くなり、転職してしまう。これからエンジニアを増やしたい企業にとって、ITエンジニア比率を一定確保していこうというのは必要な指標だと思いました。
岩本:選考段階、それも早い時点で、ITエンジニアが多い組織であることをしっかりと求職者に提示する。またITエンジニアが経営に携わることで、ITエンジニア側も「情報の非対称性」を埋める努力をする必要があると感じました。
広木:両サイドのコミュニケーションの問題はあると思います。たとえば技術的負債に関してはITエンジニアしかわかりませんから、コミュニケーションを通じて、会社全体の不確実性要素として経営サイドに話すことは、とても重要です。
【キャリア】キャリア不安を払拭するには「自己学習」できる環境整備がポイント
岩本:続いては、管理職意向についての調査結果です。ITエンジニアは「はい」が25.2%、その他職種は30.7%と、ITエンジニアの方が管理職意向は低いようです。

一方、「いいえ」の比率はITエンジニアが51.3%、その他職種が49.8%と、ギャップ差はそこまで大きくない。つまり、管理職意向に関しては積極的ではないこと、その理由として「手を動かしてコード書くような現場の仕事を続けたい」「プログラミングスキルが落ちるのが不安」が、その他職種と比べると特に高い数字が出ていました。

キャリア不安に対しても、管理職意向と同じく、技術を習得し続ける項目で、その他職種と大きくギャップがあるようです。またキャリア不安を下げる要因を分析したところ、専門職の処遇が良いこと、つまり「環境」が大きな要因だと考えているITエンジニアが多いようです。
広木:エンジニアのキャリア不安は、置かれた環境だけの話ではありません。たとえば、学習意欲が乏しい人は不安ですよね。従って、環境を中心としたパラメータとした今回の調査だけでは、キャリア不安の原因解明は読み取れないと感じました。解消方法についても同じことが言えると思います。
大前提として、多くのエンジニアがキャリアに対して不安を持っています。技術の進化が早く、自分のスキルでやっていけるのか、今のままでいいのかと考えているからです。
私は経産省やIPAのデジタル人材検討会の委員もしていますので、それらの調査内容を見る機会があります。その調査報告によれば、ITエンジニアが働くのは新しい技術に触れている、学習する機会があるなど、自己学習の影響が大きい業界だと定義されています。つまり、自己学習をどう支援できるかがポイントだと思います。
新しいことや技術に挑戦できる機会を定期的に設けたり、新しい情報をインプットできる業務にアサインするだけでも、キャリア不安は減ると思います。

岩本:具体的には、どのような制度や成長環境を整備すればよいと考えますか。
広木:勉強・成長機会の多くは、業務時間外に充てられることが多いですよね。いわゆる研修です。そうではなく思い切って、そのITエンジニアが経験したことのない実際のプロジェクトやシステムにアサインするのです。
世の中には常に情報が無限にあふれ出ています。それらの情報を無作為にキャッチアップしていては疲れるだけですし、不安は増長します。たとえば機械学習のプロジェクトでは、実際にどのようなコードが書かれているのか。実際のプロジェクトに携わることで、かなり不安が解消します。
最近は技術の細分化が進んでいる傾向もあり、特定ジャンルの情報をキャッチアップするだけでも大変ですから、領域を絞った方がより深く勉強できます。こうした学習は、転職時にも自分の強みになります。自分がフロントエンドエンジニアだと思えば、Webフロントの領域に絞って情報をキャッチアップしたり、勉強すればよいからです。
一方で、ITエンジニアがキャリアを高める上で必要となる、新しいことを学ぶ意欲や、疑問を解消するためにコミュニケーションするといった、本質的スキルは変わりません。また、会社は、情報があふれ過ぎていることがITエンジニアを不安にさせている状況を理解し、対策やケアの環境を整えることが必要だと思います。
岩本:他職種と比べてもITエンジニアが不安の多い環境に置かれていると、広木さんのお話を聞いて強く感じました。
広木:ただ、二極化している印象は持っています。たとえば、インプットをしなくても今の仕事がスムーズに進むITエンジニアがいるからです。つまり、新しい情報はキャッチアップしない。それはそれで良い生き方だと思いますし、逆に先に話したように新しい情報をキャッチアップしていくのもありだと考えています。
【総括】エンジニアとの異文化交流が重要な鍵となる
岩本:最後に、ITエンジニアがより働きやすい環境作りのために必要なことは何なのか、総括をいただけますか。
広木:前半で、ITエンジニアとその他職種の文化ギャップが大きいことを認識する必要がある、と説明しました。つまり、ITエンジニアと他職種との異文化交流が重要なのです。そうした環境作りができる会社は文化資本があり、ITエンジニアはその文化資本に惹かれ、入社していくケースが多いですね。
ITエンジニアを受け入れる文化資本があるかどうか。私が理事をしている日本CTO協会が監修・編纂しているガイドライン「DX Criteria」が参考になります。ガイドラインには心理的安全性などの項目が8つあり、全部で320の質問があります。その質問に「はい/いいえ」で答えていくことで、エンジニアを受け入れる土壌があるかの目安になります。
大事なことは、ガイドラインのチェックも含め、まずはトライしてみることです。自分の会社がどのような位置にいるのか、そこからどうアクションをとれば、エンジニアとの文化が溶け合うような組織になるのか。試しながら着地点を見つけていくことが、異文化交流では重要だからです。
異文化交流を始めるときは先に説明したように、一定数のITエンジニアがいること。トップも巻き込み、トップがしっかりと決断する。その次の段階として、ビジネス部門の人たちを巻き込めるかどうかもポイントです。
岩本:ありがとうございます。今後もこのような機会を設け、情報交換させていただきたいと思います。
【調査概要】パーソル総合研究所「ITエンジニアの人的資源管理に関する定量調査」
調査時期:2020年9月
調査方法:調査会社を用いたインターネット調査
調査対象:全国地域、10人以上の企業で正社員として働く20~59歳の男女 2500人
・ITエンジニア職種1600人
・バックオフィス職種300人
・マーケティング・企画職種300人
・フロント職種(営業職)300人
イベントのお知らせ
パーソル総合研究所の本研究結果を基に、日本CTO協会とパーソルホールディングスがエンジニアが活躍できる組織のつくり方について語るオンラインイベントを開催いたします。
是非ご参加ください!
開催日時:3月16日 19:00~
イベントページ:https://techplay.jp/event/808991