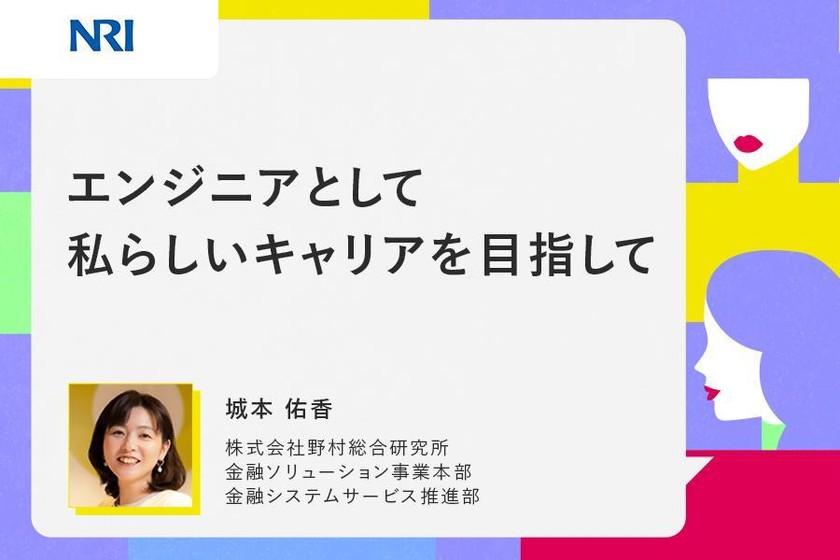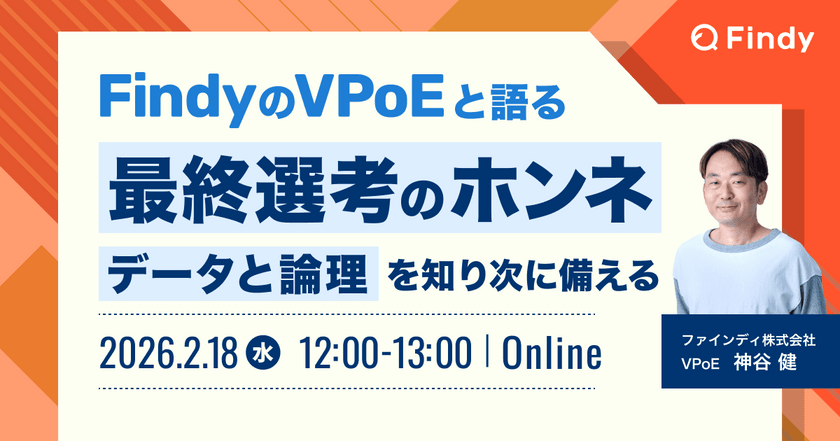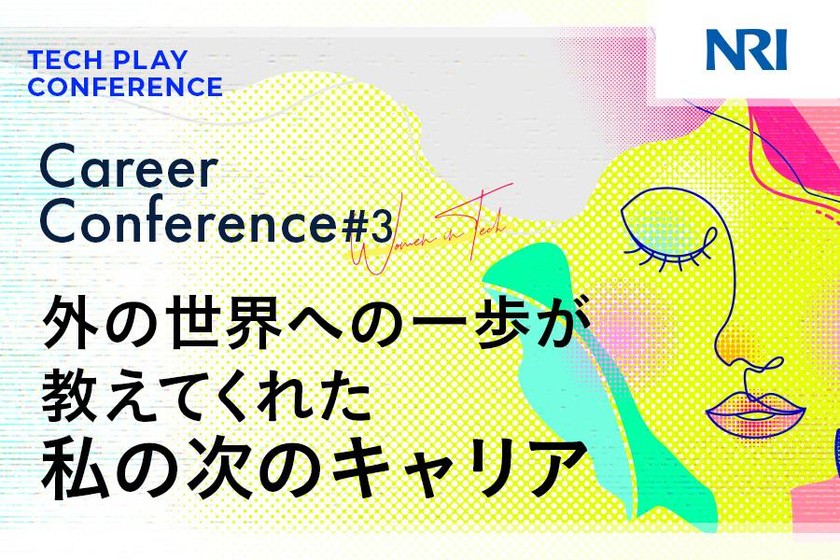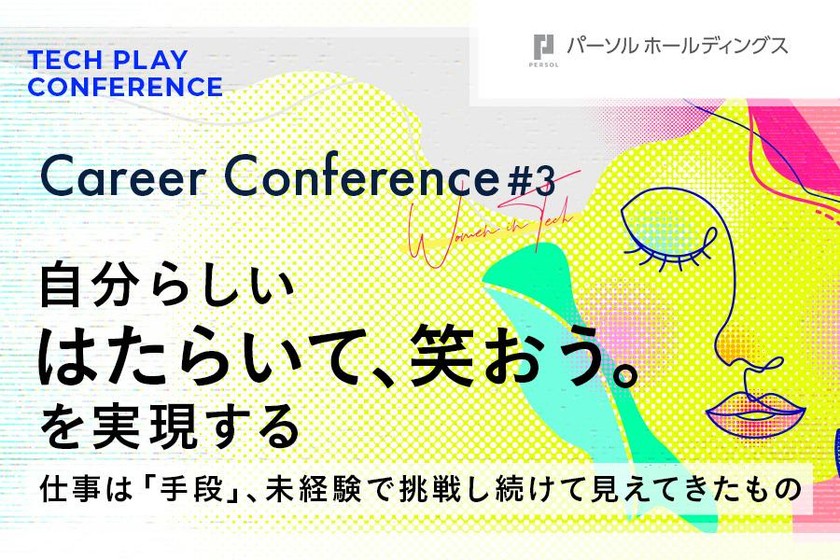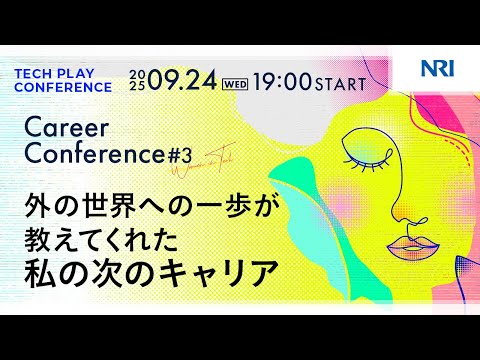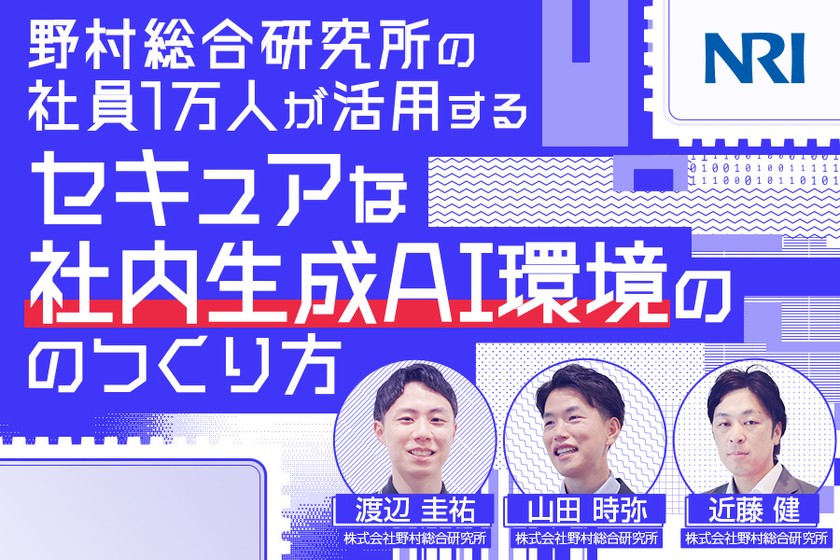エンジニアとして私らしいキャリアを目指して
日本を代表するシンクタンクであり、コンサルティングやシステムインテグレーションサービスなども提供する野村総合研究所。当然、規模の大きなプロジェクトも多い。そのような環境の中、産休・育休制度を使い時短勤務をしながら、大規模プロジェクトのPMとして活躍した経験を持つ城本佑香氏。エンジニアとしてのキャリアとプライベートの両立についての考えや実際の歩みを紹介した。アーカイブ動画

株式会社野村総合研究所
金融ソリューション事業本部
金融システムサービス推進部 城本 佑香氏
子育てのために時短勤務をしながらも、500人月プロジェクトのPMとして活躍
「当時からシステムエンジニアになりたいと思っていました」と、語る城本氏は、高専で電気工学を学んだ後、大学の情報工学科への編入を経て、野村総合研究所に入社する。まさに思い描いたとおりのキャリアを歩んでいく。
入社後は金融領域の担当となり、中でも制度に応じてシステムを変更していく制度対応業務に高い関心を持つようになる。そのためNISAが始まると同時に立ち上がったプロジェクトに自らの意志で参画する。
ところが妊娠と重なったことで、産休・育休制度を取得し10カ月ほど休職することに。必然的にプロジェクトからは離れることとなった。

復職に際し、システムエンジニアとして開発業務を続けていきたいという思いがあった。一方で育児をしながら働くことは、体力が乏しいと考えていた自分には厳しいと考えていた。そこで子どもが小学3年生になるまで使える、1日6時間勤務の時短制度を利用しようと考える。
しかし、当時は今とは異なり女性社員の数がそもそも少なかった。育児中の女性も含め、時短勤務制度を活用しているような、いわゆるロールモデルとなる女性もいなかった。そのため「正直、時短勤務で開発業務を続けることができるのか不安でした」と、城本氏は当時の心境を吐露した。
例えば、子どもは突然体調を崩すことがあるため、周囲に迷惑をかけるのではないか、といった不安だ。城本氏は、そのような思いを上司に打ち明けた。すると上司からは「0.5人月でも工数としてはプラスになる」といった、城本氏曰くポジティブな言葉が返ってきた。
上司の言葉、励ましもあり、見本となるロールモデルがいないなら自分が試してみればいい。本人曰く楽観的な思考で、時短勤務で開発業務に取り組むかたちでの復職となった。
このような背景から、特に子どもの体調など、業務遂行のリスクとなりそうな情報はできるだけメンバーにオープンにするよう心がけた。
また、以前にNISA関連のプロジェクトにアサインされなかった経験から、自分が携わりたい仕事やプロジェクトは言葉にして、周りに伝えることも意識した。するとまさに、2018年から始まるつみたてNISA対応プロジェクトに、PMとしてのアサインを打診される。
ただ、プロジェクトは約500人月という規模であった。時短勤務をやめる意志はなかったため、城本氏は自分には難しいと判断し、一度は断る。すると上司が「長く時短を続けるなら、今こそチャレンジしないと」という言葉をかけてくる。その言葉にハッとした城本氏は、500人月プロジェクトのPMを担うことを決意する。

3つの課題を掲げ、プロジェクトを推進
そして、時短勤務をしながらプロジェクトを推進していくために、城本氏は大きく3つの課題を挙げ、その対策も講じていった。まずは「業務量・業務時間」である。「そもそも足りないのは分かっていました」と城本氏。
そこで、自分以外のメンバーに仕事を任せることができる体制を整えていった。具体的には、有識者や、過去に近しいプロジェクトのPMを経験したメンバーを、PM補佐役としてアサインしていった。
時短勤務制度のため、夜間や休日の作業ならびに宿泊を伴う出張はルール上認められていなかった。つまり、非常時でもPMが参加できない、不在となるケースが生じるということだ。そこで、PMが不在の状況でも他のメンバーがしっかりと判断できるよう、普段からコミュニケーションを密にしていった。
もう一つ、つみたてNISAがどんな制度なのか、実はこの時点では未確定の要素が多く、そのことがリスクとなる可能性を秘めていた。そこで、顧客や業界団体に早い段階からヒアリングをすることで、リスク軽減に努めた。さらに、この制度の場合はなぜこのようなシステムになるのか、というシステム設計上の判断基準となる制度の背景や思想については、必ずプロジェクトのメンバー間で共有することとした。
また、どうしてもPMが必要な日には、子どもを任せられる先を事前にお願いしておくよう、調整した。具体的には、家族である。このような努力や配慮の結果、つみたてNISAに対応したシステムは、無事リリースされた。
「私が取り組んだことは、プロジェクト運営に必要な普遍的なことばかりで、真新しいことは何もしていません。用意していたリスク対策は実施しないケースが大半でした。ただ、このような普遍的な取り組みを行えば、時短勤務でも大規模プロジェクトが推進できると思っています」(城本氏)
城本氏はこのように振り返った。

ソーシャルDX事業の大規模プロジェクトでアプリエンジニアとして活躍
現在はフルタイム勤務に戻り、ソーシャルDX事業の大規模プロジェクトに、アプリケーションエンジニアとして参画。要件定義や顧客対応を担当している。城本氏はこれまでのキャリアを振り返り、「先述した上司からかけられた言葉が今でも指針となっている」と、述べた。
その上で、巡ってきたチャンスは次も巡ってくるとは限らないので、飛び込んでいきたい、とも語った。一方で、時短勤務を続けたように、ライフイベントも諦めたくないとも述べた。そして次のようなメッセージで、セッションを締めた。
「以前の私は、女性エンジニアとして生き残るのはタフなスーパーウーマンだけだと思っていました。しかし、私のように制約があったなりに、推進しているケースもあります。自分のやりたい仕事を続けていれば、道は広がる。このように思ってもらえれば幸いです」(城本氏)
【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答
登壇セッションが終わった後は、イベント参加者からの質問に登壇者が回答する、QAセッションも行われた。抜粋して紹介する。
Q.PMは厳しい思考であれこれ期待されるというイメージがあるが、そのような風当たりはなかったか?
城本:部下からも上司からも、正直ありませんでした。期待というよりは、一緒に取り組んでいこうという風潮でしたから。ただ、私が担当したプロジェクト、システムは制度の変更に伴い毎年変わるので、ちょうど私がPMを担当したあたりから、若手PMの育成の場にもなっていました。このことも、影響しているかもしれません。
Q.PMとして周りのメンバーに期待していることや求めていることは?
城本:若手中心だったこともあり、自分が取り組みたい仕事と異なると思っても、前向きに捉えて頑張ってほしいと思います。またセッションでも紹介したように、自分はこのような考えで設計したという、設計思想が分かる表現を求めました。
株式会社野村総合研究所
https://www.nri.com/jp
株式会社野村総合研究所の採用情報
https://career.nri.co.jp/
おすすめイベント
関連するイベント