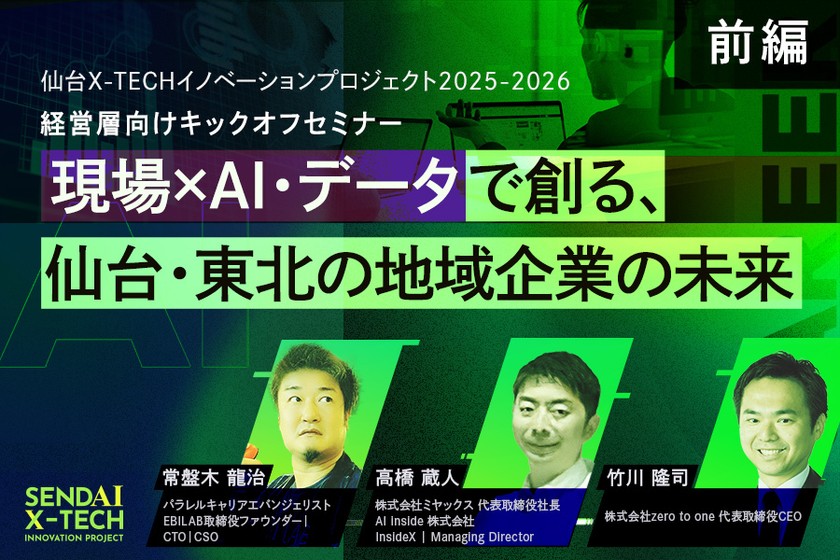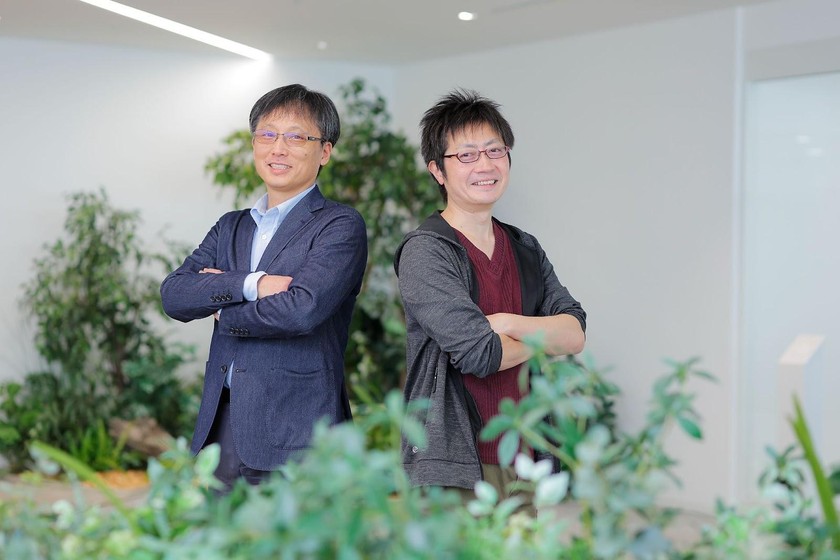【Honda×パナソニック】AIやデジタルツインなど、先端技術を駆使して挑む次世代エネルギーマネジメントシステムの開発~前編~
地球温暖化の要因とされるCO2削減に向け、国の施策はもちろん、企業もさまざまな取り組みを行っている。中でも注目されているのが、エネルギーの使用状況を可視化すると共に、最適化するエネルギーマネジメントシステム(EMS)だ。日本を代表するメーカーのHondaならびにパナソニックグループのエンジニアが、現在の状況や目指すべき未来を語った。アーカイブ動画
こちらの記事は【前編】です。
是非【後編】もご覧ください!
Hondaが目指すエネルギーエコシステムの早期実現とは

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター
エネルギーシステムデザイン開発統括部
エネルギーサービスシステム開発部
部長 水野 隆英氏
最初に登壇したのは、Hondaの水野隆英氏だ。新卒でHondaに入社すると、エンジン制御を担当。F1レースチームへの参画や、Hondaが誇るスーパースポーツカーNSXの開発にも従事。
2018年からBEV(Battery Electric Vehicle)の開発に本格的に携わるようになり、現在はエネルギーサービスシステム開発部の部長として、BEVとバッテリーを活用したエネルギーマネジメントシステムの開発を統括する。

Hondaでは魅力的なBEVの創出や、再生可能エネルギーの活用によるCO2排出ゼロなど3つの活動に取り組むことで、カーボンニュートラルな世界の実現を目指している。

自動車開発においてはHondaが中心となり、材料の調達から開発・生産、さらにはリサイクルといった自動車開発におけるライフサイクル全体において、クリーンエネルギーの利用を始めとする、循環型社会の構築を目指している。そのひとつが、エネルギーサービスである。

化石燃料を原料としていたこれまでの発電システムでは、電力は火力発電所などが生み出したものを、オフィスや自宅はもちろんEVにおいても享受する、上流から下流への一方通行であった。
一方、風力・水力発電などクリーンエネルギーが中心となる社会では、クルマは搭載されたバッテリーにエネルギーを蓄えておくことができる電力貯蔵の役割を担うと共に、自宅やオフィスに電力を供給する。つまり、下流からも電力を生むといった発電の分散が見られる。

このようなクリーンエネルギーならびに、BEVのバッテリーに搭載されたエネルギー価値を最大化するエネルギーエコシステムの実現に向けて、充電器や充電ネットワークサービスの取り組みを行っている。
さらにはV1G/V2G(Vehicle-to-Grid)と呼ばれる、取引価格も含めた電力の需給調整の対策が必要となる。

そこでHondaではそれぞれの領域に強い、国内外のパートナーや他の自動車メーカーと積極的に協力することで、実現を加速させている。
例えば、充電ネットワークサービス領域では、GMやBMWなどとの共同出資により、北米における充電ネットワーク拡大を目指す合弁会社、IONNAを設立。国内の充電ネットワークにおいては、同領域をリードするスタートアップ、PLUGOと協業している。

V1G/V2G領域においては、電力会社と自動車メーカーがエネルギーエコシステムの実現に向け、両者の情報を集約するプラットフォームを構築する「OVGIP(Open Vehicle-Grid Integration Platform)」という取り組みがある。
同取り組みの実現に向け、こちらもBMWやフォード・モーターとの合弁会社、ChargeScapeを設立。「アメリカでは電力会社が3000社以上あるため、個社ごとに契約するのは時間がかかる」と、水野氏は合弁会社設立の理由を述べた。
さらにはV2H(Vehicle to Home)領域、家庭のエネルギーに関してもHEMS(Home Energy Management System)技術に強いスタートアップに出資し、家庭用充電器の共同開発に取り組む。さらには三菱商事ともスマート充電やV2Gに関するサービスに取り組む合弁会社、ALTNAを設立。
「国内外問わずいろいろな企業と組むことで、目指すべき社会の実現を積極的に進めています」(水野氏)
水野氏はこのように述べ、ファーストセッションを締めた。
デジタルツイン環境の概要、エネルギーマネジメントシステムでの実例

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター
エネルギーシステムデザイン開発統括部
エネルギーサービスシステム開発部
エネルギーシステム性能開発課
課長 白澤 富之氏
続いてもHondaから、白澤富之氏が登壇した。白澤氏は入社以降15年近くにわたり、ハイブリッドカーのパワーエレクトロニクスや、パワーユニットの設計や開発に従事。エネルギーサービスシステムにおいては2022年ごろから携わるようになり、充電器やV2G、V2H、BESS(Battery Energy Storage System)といった技術領域における、開発の中心人物でもある。

白澤氏はまず、クルマにおけるデータ活用の取り組みについて紹介した。例えば車両開発について語った。パワートレインの設計においては、顧客アンケートや走行距離といったデータを元に、燃費や最高速度などを設定。シミュレーションを経て、実際のパーツや装置が開発される。

具体的に活用しているデータも紹介された。走行中の車両から取得される速度、加速度、位置情報などのプローブデータだ。具体的には、加速度データを取得し考察することで、高速道路での合流をスムーズにさせる際に役立てるという。
サービスエリアの滞在時間データは充電に要する、ドライバーが許容すると思われる目標時間の設定などに役立つそうだ。その他、天気や温度などの情報も参考にしている、と続けた。

データを元に仮説を検証する際には、デジタルツインを活用したシミュレーションで行っていると述べ、デジタルツイン環境の概要も示した。

気象情報、交通流、道路情報、充電設備など。さまざまな情報をAPI連携し、各種レイヤーを統合することで、リアルな世界の交通流などをデジタルツイン上でも再現する。
「このようなデジタルツイン空間上で、世の中に出ていない技術を検証している最中です」と、白澤氏は述べた。

デジタルツイン環境における苦労についても言及した。まずは、リアルな状況を追求しようと思うと、一般的に取得できるAPI情報では不足している点である。
アスファルトの表面やラジエーター開口部の温度といった具体例を挙げると共に、「論文で調べたり予測モデルを作ったりなどして対応しています」と対応策も併せて紹介した。

人間のペダル操作をドライバーモデルで再現することも、難しいという。こちらにおいては各種数式を用い交通流モデルを作成するなどして、対応している。
設計以外、他の活用事例も紹介された。先ほど水野氏が発表した、エネルギーマネジメントシステムのシミュレーションである。

EVがバッテリーに蓄えている電力を売買するビジネスやマーケットが広まっており、2026年の実現に向け進んでいる、と白澤氏は語る。

実現に向けての技術的なハードルは少ないが、EVの普及や市場のルール、ビジネスとして成立するかどうかが課題だと述べた。
課題のひとつが、EVのバッテリーに搭載された電池の移動である。「移動するために、信頼のおけるリソースであるかどうか、議論になることが多い」と語ると共に、同課題解決に向けた取り組みも紹介した。
ドライバーの行動や、売電を行う前日までにどの程度バッテリーに電力が残っているのかを示すSOC (State Of Charge)。さらにはバッテリーの劣化度を示すSOH(State of Health)といった各種指標の予測であり、リソースアグリゲーションシステムを構築し対応するという。

具体的には前日の14時までに予測を出さないと罰金対象となるため、予測精度を上げる技術が必要だと白澤氏は強調する。
1000台の車両ならびにドライバー個人から得た情報を元に、統計学の中心極限定理を使い計算し、予測しているという。以下のスライドが結果であり、青線が実測値、赤線が予測値である。

現状、平均して150kWほどズレがあること、季節変化や大雪時などにはさらに誤差が生じるが、この程度の誤差であれば使えると判断。実際、同アルゴリズムを使いSOCなどの予測を推進しているという。白澤氏は次のように述べ、セッションを締めた。
「電気自動車を単に売るだけではなく、止まっているときのエネルギーを活用することで、皆さんの生活を豊かにしたい。日本全体の再エネ最大活用のシステムとして、広げていきたいと考えています」(白澤氏)
【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答
セッション終了後は、イベント参加者からの質問に登壇者が回答した。抜粋して紹介する。
<パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 登壇者プロフィール>

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
ソリューション開発本部
システムソリューション開発センター
データ分析活用部
部長 岡市 敦雄氏
Q.海外での充電エネルギーサービスの取り組みについて
水野:日本と比べると欧州の方が進んでいます。一方で、我々はクルマをグローバルに提供していますから、まずはその欧州のサービスをアメリカに展開していく。続いて日本に、そしてアジア各国へ広げていきたいと考えていて、その際にもパートナーとの協業も考慮しながら、進めていきます。
Q.発表したEV充電制御サービスと既存のタイマー充電との違い
岡市:タイマー充電は太陽光発電設備がある場合などのケースでは、天気予報を見ながらお得になる時間帯に充電するように手動で設定する手間がかかります。特に法人の建物の場合には、需要を見ながらコントロールすることは難しいでしょう。我々が開発するエネルギーマネジメントシステムに置き換えることで、そのような手間をなくすことができます。
Q.PHEVモデルの航続可能距離は紹介したデジタルツインを活用して決定しているのか?
白澤:走行距離が少なくデータが少ないため、現在はガソリン車のデータを変換して活用、計算しています。当然、現実とのギャップが出ないようにも考慮しています。
Q.先端技術の活用も含めた開発に対する想いは?
岡市:当社の製品やサービスによりお客様の生活や暮らし、社会をいかに快適で心地よいものにしていくか。そのような想いで開発に臨んでいます。技術は手段だと捉えていますので、先端技術はもちろん積極的に活用していきますが、古い技術でも必要な場合は組み合わせも含め、適切に採用しています。
水野:Hondaが創業期から掲げていることでもありますが、環境をよくすることで人の役に立ちたい。これが、開発の根底です。EVの展開については、クルマや自宅のデータを活用することで、パーソナライズされたサービスをお客様が意識することなく提供したいと考えており、その結果、暮らしや移動の概念が変わるだろうと思っています。
Q.夜中に急遽外出することになったがBEVの電力が販売されていて移動できない。このようなケースは生じるのか?
白澤:EVであっても移動が一番であり、その次として止まっているときのエネルギーを販売するという考えが前提です。そのため移動に必要な電力の絶対量は確保した上での電力販売といった制御をしていますので、走りで困るようなケースは生じないと考えています。
Q.EV普及先進国である欧米での課題とは?
岡市:EVの普及に伴い充電設備も増加する必要がありますが、送配電インフラに流せる電力上限の制約で、新たな設備を設けるまでに順番待ちの地域があるなど、時間が生じているといった課題があります。
白澤:紹介したようなV2Gサービスをグローバルに展開していこうと考えていますが、電圧が対応していないのが現状です。またルールや法律、アセスメントなどが各国により異なるので事業としての成立も含め、どのように対応していくか。このような課題があると考えています。
Q.パートナーシップとの連携における工夫や配慮は?
水野:これまでの経験から、利益という観点で進めていくとうまくいかないと考えています。実現したいビジョンがあり、一緒に組むことでスピーディーに実現できる。そのような考えが一致すると、話がスムーズに進むと捉えています。また現状のパイを分け合うのではなく、新しいパイを広げるといった議論で進めることも、同じく大事だと考えています。
Q.リアルタイムプライシングなどの最適制御によるCO2削減への貢献について
岡市:最適制御を行うことは、クリーンエネルギーの活用につながり、主に火力発電によって電力を供給している時間帯の電力使用を下げることにもつながるため、CO2削減に間接的につながるものだと考えています。
※【後編】の記事もぜひご覧ください ※
本田技研工業株式会社
https://www.honda.co.jp/
本田技研工業のキャリア採用情報
https://www.honda-jobs.com/
本田技研工業の採用情報
https://global.honda/jp/jobs/?from=navi_footer_www
本田技研工業の電池・パワーエレクトロニクス領域について
https://www.honda-jobs.com/about/esd/
おすすめイベント
関連するイベント