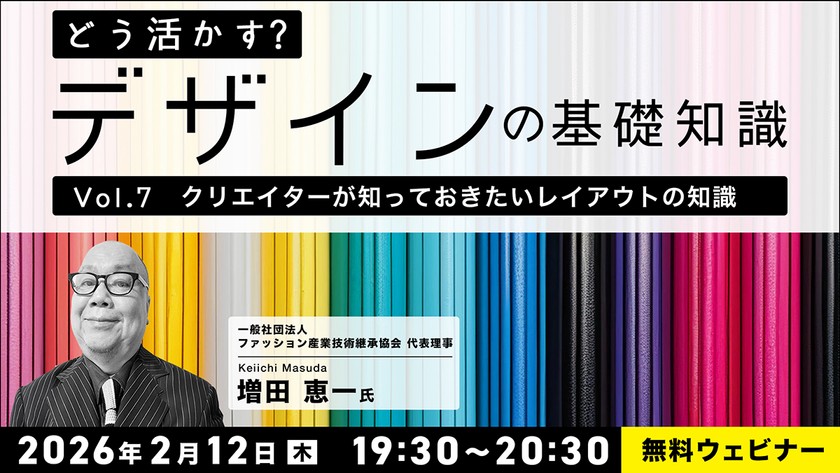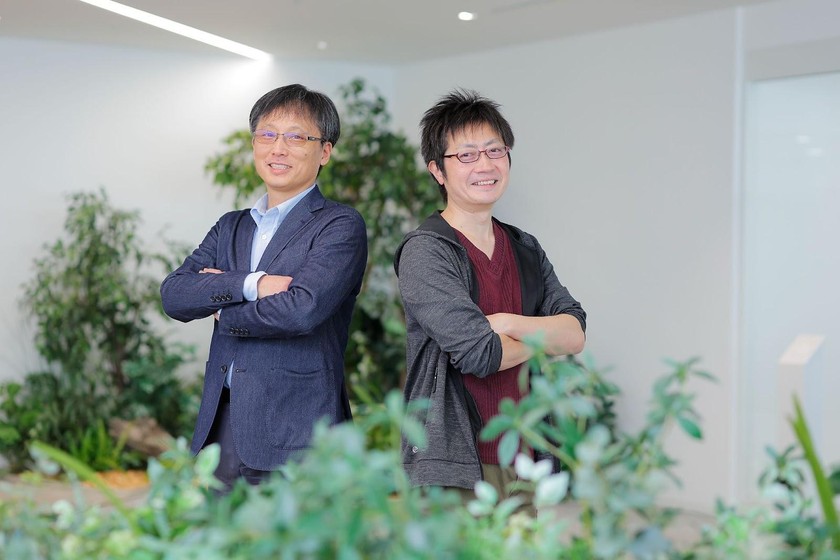世界有数の自動車拠点、愛知(名古屋)。地の利を活かして全国拠点と連携しながら、SDVの最先端を走る
100年に一度の変革期を迎えている自動車業界。Hondaは特にソフトウェアの役割を重視し、ソフトウェアを定義した上でハードウェアを決めていくクルマづくり「ソフトウェアデファインドビークル(SDV)」を推進している。これを主導するのがSDV事業開発統括部だ。 全国拠点のひとつとして、2024年に新設されたのが名古屋拠点。次世代パワートレイン制御システム・ユニット開発に従事し、拠点を統括する西面 房俊チーフエンジニアに、名古屋拠点が目指すSDV戦略とこれからともに仕事をしたいエンジニア像について聞いた。この記事に登場する人

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 SDV事業開発統括部
電子プラットフォーム開発部
電子プラットフォーム開発課
チーフエンジニア 兼 名古屋拠点長
西面 房俊 氏
大学院卒業後、大手コンピュータメーカーに就職。2000年、本田技術研究所に転職。パワートレインのエンジン制御ソフトウェア開発に従事。2017年、京都の電子部品メーカーに再転職。Honda時代の元上司との対話をきっかけに、2024年 Hondaに復帰。大阪拠点を経て、2024年10月から名古屋拠点長を務める。
自動車産業の集積地である愛知の特性を活かして
——まず、名古屋拠点設置の狙いからお話しください。
西面:名古屋拠点はオフィスを設置して間もない新設拠点です。私が大阪拠点から異動してきたのが2024年10月。名古屋拠点はほぼ全員が転職者なので、デスクの上に名札を置いて、全員が全員の名前を覚えることからスタートしています。
Hondaが栃木、東京、大阪、名古屋、福岡と全国各地にSDV事業開発統括部の拠点を置いたのは、それぞれの拠点の近隣から優れたエンジニアを採用したいという目的があります。
今は、場所にとらわれずに開発が進められる。それぞれの人がそれぞれ好きな地域で仕事をしながら、相互に連携してチームとしてまとまり、これまで以上の成果を出す、そういう組織形態にしていきたいと考えています。
名古屋拠点だけが単独で担う開発分野があるわけではありません。ただ、地域の特性があるので、いずれは名古屋拠点の開発の特性が発揮されると思っています。

——次世代EV開発の上で有利に働く、名古屋や愛知県のメリットはどこにあるとお考えですか。
西面:例えば、愛知県はOEM(完成車メーカー)や自動車部品サプライヤーが集結する、世界有数の自動車開発の拠点です。自動車産業における競争関係を保ちながらも、お互いが持続的な成長ができるように、切磋琢磨してきました。会社の枠を超えて、地域の中でエンジニア同士がつながることもできます。
これからは、EVがリードする世界の新しい自動車産業マップの中で、日本として電動車産業をどうやって盛り上げていくかが重要です。そのためにメーカー間で協力できるところもあるはずなので、Hondaの名古屋進出がそのきっかけになればいいと考えています。
さらに、部品サプライヤー層の厚さも愛知の特色です。これまでOEMは、ソフトウェア開発における企画から要求仕様の検討までを担い、ソフトウェアの実装はサプライヤーへ依頼していました。
しかし、今後はOEM自体がこれまで以上にソフトウェア開発力を強化しなくてはなりません。「ソフト開発を手の内に」というのが、いまSDV事業開発統括部のスローガンの一つになっています。
ソフトウェアの開発力を向上させるには、やはりサプライヤーの持つ技術を取り入れたり、お互いに連携していったりなどの協力体制が必要になります。これまでサプライヤーでソフトウェア開発を担当していたエンジニアが私たちのチームの一員として、戦力になってくれれば、とても心強いと思っています。

Hondaのソフトウェア開発マインドとは
——サプライヤーで開発に従事してきたエンジニアがOEMに転職する場合、どんな心構えでいてほしいですか。
西面:もちろんサプライヤーとOEMでは同じ車載ソフトウェアでも、開発にあたってのマインドは異なります。サプライヤーではソフトウェアを一つの部品として、OEMが示した仕様通りに納品することを事業としています。
ただクルマは複合体なので、自社の部品だけではなく、他の部品と連携しながらクルマとして成立させなくてはなりません。
自社部品の目線も大事ですが、OEMでの開発では、その目線を変えて全体を見渡した時に、その部品がどういう部品であれば良くなるのかというところを考え抜かなければなりません。部品単体というよりは車両全体のシステムアーキテクト的な立ち位置で関わる必要があると共に、その醍醐味も味わえると思います。
——Hondaのソフトウェア開発のスタイルにも最近、変化が見られます。例えば「ソフトウェア自社開発」に力を入れるようになりました。これはどういう背景があるのでしょうか。
西面:名古屋拠点の開発現場は、20代の若手が多いですね。中には量産開発は初めて経験するというメンバーもいます。だから、いきなり成果を出すことは難しい。けれど、Hondaのソフトウェア開発自体も最初から完璧を求めないという考え方を持っています。

西面:私が栃木の研究所で、パワートレインの制御ソフトをプログラムしていた頃は、Hondaが詳細設計まで担い、最後のコーディングだけをサプライヤーに依頼し、それをビルドしていました。
ところが、時代の流れとともに、Hondaは要求仕様までを担当し、だんだんコードから離れるような開発体制となり、ソフトウェア領域はサプライヤーにお任せするようになっていきました。自社でソフトウェアを内製する比重が徐々に減ってしまったんですね。
それをもう一度、原点回帰し「ソフトウェアを自社で開発する体制」を取り戻すというのがSDV事業開発統括部の考えなのです。新しい開発スタイルを再構築していくので、転職者も遠慮することなく、一緒にHondaのSDVらしいソフトウェア開発手法の創造に関わっていってほしいと思います。
とはいえ、ソフトウェア開発を内製化しただけでは、私はいずれ行き詰まると思います。内製化で、かつスピードアップということになると、当然、仕事量が膨大になります。
人を増やすにしても限界はあります。そこで必須になるのが、デジタル・トランスフォーメーション(DX)です。AIなどを活用したコーディングの自動化などを、今後進めていきたいと思っています。

行動せずに後悔するよりは──私が久しぶりにHondaへ復帰した理由
——西面さんご自身のキャリアも波瀾万丈ですね。Hondaに再び戻られたのはどういう思いからですか。
西面:私自身はHondaの中でも少し異色のキャリアを歩んできました。大学院でニューロコンピューティングを専攻し、卒業して最初に就職したのが大手コンピュータベンダーでした。そこで液晶プロジェクターのRGBデータの組合せをコンピュータで自動化する仕事に従事していました。
新卒ではコンピュータ会社に行く選択をしましたが、実は高校生の頃から本当に行きたかった会社はHondaでした。F1やワールドソーラーカーラリーを見て、かっこいいなあと(笑)。コンピュータ会社の仕事が一段落した折に機会があって、Hondaに転職しました。ちょうど環境問題が叫ばれていた時期、今度はクルマのメーカーに行って排出ガスクリーンなクルマを作りたいなと思いました。
Hondaでは、主にエンジン制御のソフトウェア開発に携わり、そこで長らくキャリアを積んでいました。そして、2017年に、京都に本社を置く電子部品メーカーに再転職しました。個人的な事情ですけれども、私は神戸出身のため、いずれは故郷に近いところで仕事をしたいと思い、関西へと拠点を移しました。
その会社では、品質管理システムの開発に従事していました。管理職として20人以上の部下がいて、マネジメントも若手育成も楽しく、このまま定年退職するのもいいなと思っていました。そんな折に、Honda時代の元上司がクルマの専門技術展「オートモーティブ ワールド」で講演するという話を聞きつけたのです。懐かしさもあって、私も講演に参加し、講演の後に一緒に食事をしました。
その際に、元上司から「Hondaが大阪に開発拠点を作った」ということを聞き、「西面が関西に戻ったのは実家に近いという理由があったからだろう。大阪でもHondaの仕事ができるから、戻って来ないか?」と誘ってもらったのです。

西面:ずいぶん悩みましたが、行動しないで後悔するよりは、行動してから後悔したほうがいい。どちらにしても後悔するなら、自ら動いて後悔したほうが価値がある——そんなふうに思い、五十路を目の前にして、人生再チャレンジをしたというわけです(笑)。
そして、2024年にHonda 大阪拠点に転職したところ「次は名古屋拠点を作るから、そこで拠点長としてマネジメントをしてほしい」と言われたんですね。名古屋といっても、駅前のビルで自宅から通うことができたため転勤を承諾し、今は名古屋まで新幹線で通勤しています。
誰よりも早く行動し、早く失敗してこそ、人は育つ
西面:私が名古屋へ転勤になったのは、名古屋はキャリア入社の社員ばかりでHonda経験者が少なかったこともありました。拠点長任用の要件として「Honda経験者にマネジメントしてほしい」ということがあったようです。そして、私の場合は、Hondaだけでなく他の会社も数社経験しているため、客観的な面からもHondaの良さを伝えられるんじゃないか、ということも期待されたのかなと思います。
——他のメーカーもご経験されて、逆にHondaの良さ、Hondaらしさを感じることもあったかと思います。それはどんなところでしょうか。
西面:Hondaはどちらかというとトップダウンよりも、現場が頑張って商品を作り上げていくという会社です。若手も含めて一人ひとりが、担当した仕事を自分で考えて自分のものにしていく。若手が自立するスピードが速く、それが強みになって、底力にもなっている。若手の優秀なメンバーが頑張ってやっていけば、いいクルマができていきます。
また、Hondaでは、みんなで話し合う「ワイガヤ」※の文化があり、何かあったらすぐ相談したり議論したりする組織風土です。私自身も、率先して行動で指し示すことが大切だと思っています。
※ワイガヤとは?
「夢」や「仕事のあるべき姿」などについて、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論するHonda独自の文化。合意形成を図るための妥協・調整の場ではなく、新しい価値やコンセプトを創りだす場として、本気で本音で徹底的に意見をぶつけ合うもの。
今後は、私も人材採用の面接に参加します。面接を通して何を知りたいかというと、その人の失敗体験ですね。私自身もたくさん失敗しています。ただ、私の場合は敢えて「失敗を早くする」ようにしています。まずは自分でやってみる。たとえ失敗しても、周りの人より早く失敗して、早く修復していれば、影響をなるべく最小限に抑えられます。早く失敗することによってこうやったらダメなのかと気づけるだけでも大切なことだと言えるでしょう。

西面:創業者 本田宗一郎の語録にも「失敗もせず問題を解決した人と、十回失敗した人の時間が同じなら、十回失敗した人をとる。同じ時間なら、失敗した方が苦しんでいる。それが知らずして根性になり、人生の飛躍の土台になる」という言葉があって、あれ、好きなんですよね。私も「何でもトライする」「早く失敗する」といった、意気込みのある人がいいなと思っています。
車載ソフトウェアは、組込みソフトウェアなどの経験がない人は尻込みする人もいるかもしれませんが、そんな心配はいりません。車載はクルマという商品性質上、要件が厳しいだけで、基本的なソフトウェアの開発というところは変わりません。
ソフトウェアをしっかり開発できる人であれば、あとは車載ソフトウェアとはこういうものだと理解していけば、活躍してもらえるかなと期待しています。
Honda 名古屋拠点の採用情報
名古屋拠点|募集要項・エントリーはこちらから
名古屋拠点|ソフトウェアエンジニア採用の詳細情報はこちらから
Honda SDV事業開発統括部に関する情報はこちらから
※記載内容は2025年2月時点のものです