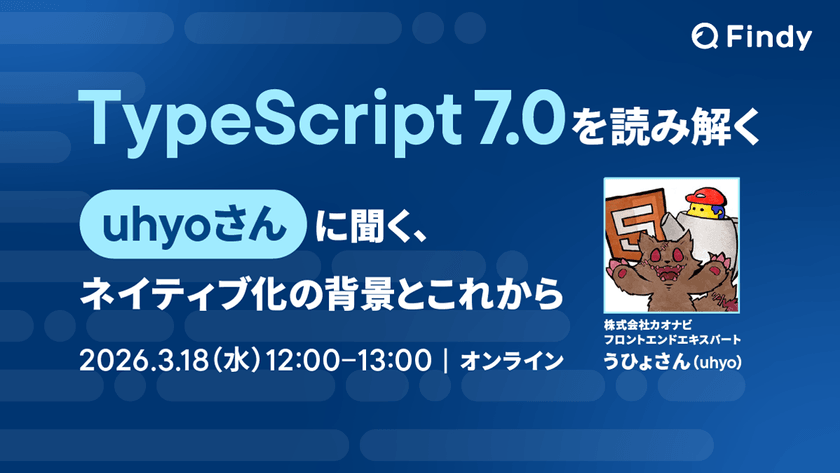ヤマハ発動機、2030年までに全製品をコネクトするデジタル戦略を語る ~海外DX事例、コネクテッド基盤、デジタルマーケティングetc.~
2030年までに全ての製品をコネクトする「コネクテッドビジョン2030」を掲げるヤマハ発動機。二輪車、マリン、特機、産業用機械、ロボットなど、世界中に製品を展開する同社が、デジタルトランスフォーメーション(DX)やデジタルマーケティングを新製品開発に活かし、新たな顧客獲得やサービスを醸成。そして既存顧客に対しても、より精緻でパーソナルなサービスを提供している。今回はコネクテッド推進の海外事例や分析基盤アーキテクチャなど、ヤマハ発動機のデジタル戦略を紹介する。アーカイブ動画
■登壇者プロフィール

ヤマハ発動機株式会社
IT本部デジタル戦略部 部長 新庄 正己氏
1995年ヤマハ発動機入社。モーターサイクル車体設計部門にて多くの大型モデル車体開発に従事。Drag Star、 VMax、 MT09などを担当。調達部門に異動しモーターサイクルのコストダウンやインド工場立ち上げに従事したのち、再び開発に戻りクルーザーカテゴリーのプロジェクトリーダーを数年担当。2017年からMC事業本部に異動し技術戦略、EV戦略などを担当。2020年からヤマハ発動機のDXを推進するデジタル戦略部の部長に就任。大阪出身、名古屋工業大学卒。

ヤマハ発動機株式会社
IT本部デジタル戦略部 グループリーダー 大西 圭一氏
2008年ヤマハ発動機入社後、二輪車事業において東南アジアを中心として海外工場の生産企画と製造技術業務に従事。海外留学を経て、コーポレートVC業務およびIoT関連の新事業開発を担当。現在は全社のDX推進を担うデジタル戦略部にて、デジタルマーケティングの戦略立案と実行、およびデータを活用した事業課題解決とデータ分析活動の民主化推進に従事。名古屋大学工学修士 マサチューセッツ工科大学経営学修士。

ヤマハ発動機株式会社
IT本部デジタル戦略部 齊藤 浩太氏
ソフトウェアベンダーでETL製品の開発、Web系ベンチャー企業で求人情報の検索サービスのバックエンド開発、Webサービスの立上げなどを経て、2020年にヤマハ発動機入社。入社後はユーザー認証基盤の運用やコネクテッド基盤の運用に従事。現在は主にコネクテッド基盤の運用、構成の検討、社内への普及に力を入れて活動している。

ヤマハ発動機株式会社
LM事業本部GB統括部 山田 宗幸氏
2005年ヤマハ発動機入社。東南アジアで主力の小型スクーターの車体設計業務を経験。2012年から4年間、主要市場であるインドネシアのR&D拠点立上げメンバーとして駐在し、現地スタッフの教育含めた開発基盤の構築と現地開発モデルの設計業務を推進。帰国後、LM事業本部に異動、技術戦略関連業務を経て、2019年よりLM事業におけるコネクティビティ関連の業務プロセス構築及びモバイルApp開発PJ推進に従事中。

ヤマハ発動機株式会社
IT本部デジタル戦略部 藤井 北斗氏
2009年ヤマハ発動機入社後、R&D部門で自動運転システムなどの開発を担当。具体的には、自動運転システムのAI開発、AWSを使った配車システム開発、サービス設計のためのGPSログ分析などを担当した。2019年、AI開発、コネクテッド、データ分析の経験をよりビジネスに近い領域で活かしたく、デジタル戦略部データ分析グループに異動。現在、製造系データ分析やマーケティング系データ分析を担当している。また、データ分析民主化のための社内講座講師も担当している。
DXはあくまで手段──世界の人々に感動を与えることが目的
ヤマハ発動機は売上高1兆4713億円(2020年12月期)のうち、およそ9割を海外市場が占める。まさしくグローバル企業だ。
「IT企業の業績が右肩上がりで伸びている一方、製造業の業績は横ばいです。しかし、私たちにはこれまで培ってきた技術力と、180を超える地域や国で事業を展開してきた、販売代理店などの豊富なネットワークを持っています。このネットワークにデジタルをかけ合わせることで、ヤマハならではのDXを実現することを目指しました」(新庄氏)
最初に登壇した新庄正己氏は、このように力強く述べた。

「DXと聞くと、どうしてもテクノロジーや新しいデジタルツールに注目しがちです。しかし私たちがDXを行う理由は、『世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する』という企業目的を達成することです。だからこそDXは手段であり、ゴールではないことを取り組む前に明確にしました」(新庄氏)
意図が明確になり、経営陣が集まって議論を進めていく中で、ヤマハ発動機のDXはIT部門だけで進めるのではなく、全社一丸となって進めていくことを決定した。その結果、ヤマハ発動機におけるDXの定義や意図はより明確になっていった。具体的には次の3つだ。
- 競争力のある経営システムを構築する
- 既存事業をデジタルで強化する
- 新たなビジネスの創造
ヤマハはグローバル企業のため、関連企業が約200社あり、各社がそれぞれ経営基盤を構築している。そこで、1つ目の経営システム構築においては、この経営基盤を全社統一のERPとして構築することで、DXを加速していく。2つ目の既存事業のデジタル強化では、以下の4つを重点領域として取り組んでいる。
- デジタルマーケティング
- コネクテッド
- データ分析
- スマートオペレーション
「デジタルデータ基盤を整えながら、これらの領域においてデータ活用することで業務・製品・お客様をつなぎ、お客様にさらなる価値を提供することを目指しています」(新庄氏)
「現在約5000万人いる世界中の顧客に対して、DXを進めることで新たなサービスを提供したり、デジタルを活用することで新たなお客様とつながる。あるいは、異業種とのコラボレーションにより、さらなる価値を提供する。このような未来を描いています」(新庄氏)

3つ目の新たなビジネス創造のテーマについてこのように説明し、セッションを締めた。
Webサイトの閲覧ログを精緻に解析し、デジタルマーケティングに活かす
続いては、大西圭一氏が登壇。DXを進める上で活用するデータとデジタルマーケティングについて紹介した。
まずは、ヤマハにおけるデータの捉え方について、「データはあくまでツールであり、ヤマハの強みをさらに引き立てるためのものだ」と強調。その強みを次のように紹介した。
ヤマハ発動機には情熱や熱い思いを持ったメンバーが大勢集まってきており、それらは弊社の強みの源泉だと考えています。グローバルなメンバーの顔ぶれも特徴です。私がいま一緒に仕事をしているメンバーも、インド、シンガポール、ベトナム、中国のメンバーが顔を揃えています。
職位を超えて活発に意見を通わせるフラットな環境であるため、多様なメンバーが自由闊達にアイデアを出し合うことができる。その結果、シナジーやケミストリーが発生し、新たなサービスや製品が次々と生まれています」(大西氏)

ヤマハの自由闊達な雰囲気は、大西氏も登場しているコーポレートサイトを見れば、より深く理解できる。
だが、現時点では以下3つの課題がある。これらの課題をオンラインとオフライン横断しながら様々な顧客接点からデータを取得し、分析やマーケティングに活かしている。
- お客様一人ひとりの意思決定プロセスの把握
- お客様との直接コミュニケーション
- データドリブンなマーケティング手法の確立
大西氏は、現在進めている顧客データを利活用する基盤アーキテクチャ、システム構築における考えについても紹介した。

「顧客のデータ基盤はTreasure Data CDPをベースに、既存のSaaSツールを目的ごとに組み合わせて構築しています。最初から大きなシステムを構築するのではなく、いわゆるマイクロサービス、プロジェクトニーズドリブンで進め、適宜調整しています」(大西氏)
ヤマハでは分析やマーケティングを行う上で、PVやUUではなく、1人の顧客がどのページを、どのようなジャーニーで見ているのかに着目しているという。つまり、顧客ごとの行動を閲覧ログから細かく可視化し、マーケティングに活かしているのだ。

たとえば、同じモデルのバイクの紹介ページに何度もアクセスしている顧客がいれば、該当するバイクの試乗キャンペーンの広告を表示する1to1マーケティングだ。
顧客ごとのデータを分析していくと、ハイパフォーマンス製品を購入する属性の顧客は、他のカテゴリー、ロードバイクと水上バイクといった違う製品であっても、同じく上位クラスの製品を閲覧していることがわかり、クロスセルに使えるという収穫があった。
一方で、同社はメーカーであるため、実際の販売や顧客とのタッチポイントは、各地に点在するディーラーが行う。そのために、先の3つの課題が生じていた。そこで同社は、得たデータやマーケティングアイデアをディーラーにも伝えることを決めた。
「イベント時には多くのお客様が来場されます。当然ですが、お客様によって製品に対する興味関心の範囲や強さは異なります。しかし、応対できるキャパシティには限りがあります。興味関心が高い購入見込み客のお客様の情報を優先的に販売店様にお伝えして接客に活かしていただくことで、お客様にとっても販売店様にとっても良いフローができるように活動を進めています」(大西氏)
このような接客も含め、購入後のアフターケアにおいても、同じくWebから得られる閲覧データをより分析し、最適な情報やサービスをディーラーに提供することで、顧客にとってフリクションのない体験を提供していく。

お客様が多くの時間を過ごされるオンライン上で個別化された最適な体験を提供しつつ、販売店様でもより良いおもてなしの体験をしていただく。そのような販売体験の提供が可能なレベルまで達することが目標だと語り、セッションを終えた。
全製品のデータを利活用できるコネクテッド基盤を構築する
ヤマハでは2030年をめどに、すべての製品に通信機能を搭載してデータを収集・活用する 「コネクテッドビジョン2030」を掲げている。顧客データから得た情報を分析し、新たな製品開発や、より価値の高いサービスを提供することを目指す。もちろん、その実現には乗り越えるべき壁がある。3人目の登壇者、齊藤浩太氏は次のように語る。
「バイクはエンジンから、電動自転車はバッテリーからデータを得ます。データの取得先は製品ごとに異なり、通信手段もSIMカードやBluetoothなど様々です。そのため製品ごとに専用のデータ基盤を用意したいところですが、構築・運用どちらにおいてもコストが大きくなることは明白です。そこで汎用性の高い基盤を作り、製品ごとの専用基盤と連携することとしました」(齊藤氏)

同社が1年間で販売するバイクは約500万台、マリン製品は約30万台。コネクトテッド2030が稼働した際には、大量のデータアクセスが生じることは明白であり、それに耐えうるシステムが求められた。
そこで選択したのは、AWSのサーバーレス アーキテクチャだ。クラウドでスケールしやすいのはもちろん、従量課金のためコストが抑えられる。すでに多くのシステムで採用されているため、情報を持つベンダーや技術者が多い点もポイントだった。

アーキテクチャおよびデータの流れも紹介された。それぞれの製品基盤から上がってきたデータはAPI連携で入り、Kinesisがキャプチャする。Lambdaで振り分け、製品ごとに分類されたストレージ、S3に保存される。さらに、S3に溜められたデータを分析やサービスに活かす、という流れだ。
技術的な説明を補足すれば、S3のデータをGlueやAthenaを使い、抽出、分類、格納といった処理を実行する。処理を行う際は事業部とやり取りすることで、現場で価値あるデータとして使えるように確認し合いながら進めることが重要だ、と齊藤氏は強調。セッションを終えた。
インドネシアで展開しているモバイルアプリのコネクテッド事例紹介
「コネクテッドビジョン2030」が実現すると、どのような体験やサービスが生まれるのか。続いて登壇した山田宗幸氏は、すでにインドネシアで提供しているモバイルアプリの事例を紹介した。

山田氏は、まずシステムアーキテクチャ、データやサービスの流れを上記図のように示し、バイクからはオイルの残量、アクセルやブレーキを操作するタイミングなどのデータが基盤に上がっていく流れを説明した。
そのデータをもとに、いつオイル交換するのがベストか。燃費が向上するにはどのような運転を行えばいいのか。利用者が喜ぶ情報やリコメンデーションを、フィードバックしていく。バイクのモニターに表示できないような情報も、同じくスマホに伝える。逆に、スマホへの着信情報などは、バイクのモニターに表示するような仕組みも備える。
「お客様一人ひとりに最適なレコメンドすることが、コネクテッドサービス最大の特徴。パーソナライズ化されたサービスです。ヤマハ製品はバイクを筆頭に、購入サイクルが長い。資産のひとつとも言えるでしょう。お客様の大切な資産を、いかに最適な状態で楽しんでいただけるかを意識しています」(山田氏)
具体的なサービスとしては、購入後の定期的なメンテナンスのアナウンス、トラブル時に近隣のサービスセンターに速やかにアクセスできることなど。日々の“Experience”を最適化し、冒頭の企業目的、感動を与えることでユーザー満足度をさらに高める。これが、ヤマハ発動機が実現しようとするDXなのである。
「これまでお客様とのコミュニケーションを担っていたのはディーラーだけでした。しかしデジタル、DXを利活用すれば、我々メーカー自身もお客様にもっと寄り添えるようになる。大きなビジネスチャンスだと捉えています」(山田氏)
データ分析の事例、データの民主化に向けた社内教育について
最後に登壇したのは、データサイエンティストの藤井北斗氏。まずは、先ほど大西氏が紹介したデータ分析ならびにデータマーケティングの内容を補足した。
システムアーキテクチャは、Google Cloudをメインで活用。Web行動履歴の解析、顧客の購買確率算出は、機械学習自動化プラットフォーム、DataRobotによるAIでスコアリングする。エンドユーザー向けのサービスだけでなく、ディーラーに対しても信頼性の高い営業ツールの開発を行っている。
BtoB、BtoCどちらのサービス開発も担っていると説明し、スマートオペレーションにおけるデータ活用についても言及した。

また、紙のドキュメントで保存していた情報をデジタル化し、Google Cloud Platform(GCP)のBigQueryに入れることで、リアルタイムでデータ監視ならびに解析が行えるようになった。
「その結果、これまで熟練者の経験や勘に頼っていた不良品検知を、より効率よく行うことができます。同じく、熟練者に頼っていた製造設備の異常検知においても、モータの電力波形をデータ化し、リアルタイムに解析することで、事前予知できるようになりました」(藤井氏)
藤井氏はデータサイエンス業務に携わって2年目となる。今後はより多くのデータサイエンティストを増やしたいという想いから、「データ分析の民主化」活動を行っている。その活動内容についても紹介した。
具体的には2つある。1つ目は、いわゆるブートキャンプ型の研修だ。実務から3週間離れ、毎日8時間、データ分析に関するスキルを学んでいく。毎日Pythonでコードを書くなど、ブートキャンプの名に相応しいハードな内容だ。だが、受講者は着実にデータサイエンティストとしてのスキルが身につく手応えもあるという。

しかし現在は、新型コロナウイルスの影響でオフラインでの実施が難しくなった。そこで、2020年8月からは、新たな研修をオンラインでスタートさせた。
新しく始まった研修は「座学+ウェビナー」という構成で、研修期間は5週間。データを活用した分析プロジェクト計画書の作成から、実際のデータ分析、レビュー、フィードバックと、実際のデータ分析プロジェクトと同じようにPDCAで進めていく。さらに、演習だけでなく宿題も用意した。
「座学では社内の実例を紹介し、ワークショップでもそれぞれのメンバーの実務課題に重ねるなど工夫を施しました。このような努力もあり、定員150名に対しこれまで403名が受講するほどの反響でした。しかもITや研究開発部門だけでなく、ビジネスサイドのメンバーも多く受講しました」(藤井氏)
まさに、ヤマハが全社をあげてDXを推進していく雰囲気が醸成された、と藤井氏は感慨深く話し、講演セッションの幕を閉じた。

【Q&A】参加者から寄せられた質問に回答
各セッションの終了後には、参加者から寄せられた質問に答えるQ&Aタイムが設けられた。分野別にまとめて紹介する。
【デジタルマーケティング】
Q:技術的スキル以外にDXで重要視する点はどこか
新庄:部署や職種によっても異なりますが、ビジネスを伸ばすためであれば、ビジネスを理解することだと思います。
Q:各国でのデジタルマーケティングは、どのようなグローバル体制で行われているのか。現地特有のドメイン知識が必要なのではないか
大西:おっしゃる通り、現地特有のドメイン知識が必要です。一方で、各国にデータサイエンティストを配置するのは難しい現状があります。そこで日本本社の役割としては、地元のお客様のことをよく知る現地のメンバーが動きやすいような基盤を整備します。
Q:要素技術開発は行っているか
大西:システムのアーキテクチャ、ソフトウェアの開発においてですが、先に紹介したように既存ツールを利用するのが基本です。もちろんPythonでゴリゴリコードを書くようなケースもありますが、そこは是々非々で行っています。ただし、機械学習のライブラリをゼロから作るようなことはありません。
Q:事業部とデジタル戦略部との連携について聞きたい
大西:デジタル戦略部という部署ではありますが、各部署で働く人の気持ちを理解したり、ドメイン知識を学ぶなどして、信頼関係やコミュニケーションの構築に努めています。テクニカルな知識よりも総合力、全員が同じ舞台に立っている気持ちが重要だと思います。
たとえば私は以前、製造技術部門にいたので、そのときに構築した信頼関係やネットワークを活用したりもしました。あるいは、すべてのデータを見せるのではなく、少しずつ、取り掛かりやすいデータや効果を見せることで信頼関係を構築し、部門間の壁を超えて連携を強められると考えています。
【コネクテッド】
Q:コネクテッドで得られるデータは、ユーザーよりも受け取る事業者のほうが大きいように思う。ユーザー側のメリットを知りたい
山田:先のインドネシアの例で説明すれば、不慮の故障に遭う確率が下がると考えています。もうひとつは、毎日使う楽しみさがある、いわゆる趣味的な要素もあるだろうと。正直、まだ手探り状態ですので、一緒に考えてくれるメンバーを求めています。
Q:本社で基盤を構築してグローバルで使うのは理想的だが、大変だったのでは?
齊藤:できるだけシンプルに設計しています。汎用基盤はあくまでデータを受け取り、商材ごとに振り分けて溜める。これだけの役割だからです。
Q:ASEAN各国のデバイスからのデータは、ローカル国内に保存するなど要件やレスポンスの課題はなかったのか
齊藤:ASEANは特に問題ありませんが、EUなどはローカライゼーションの規制が厳しい、AWSをどのリージョンで分けるか、といった課題があります。
Q:DXを進める上で、同部門はどこまでの権限を持っているのか
新庄:ヤマハはボトムアップで挑戦する風土があります。そのため権限がないメンバーや部署であっても言い続けていると、次第に実現することが多いですね。コネクテッド担当の山田は、同プロジェクトをどうしても担当したいと宣言して、今のポジションに就きました。
【データ分析】
Q:説明したテーマに藤井さんはすべて関わっているのか
藤井:短いテーマであれば1週間、長くても3カ月。かなり重いテーマの場合は研究開発部門に協力をお願いすることで、私は全プロジェクトに関わるようにしています。また効率的に進めるためにAutoMLなどを導入し、プログラムに要する時間を削減しています。
Q:幅広い部門で課題のデータ分析をしているが、各課題はどのように吸い上げているのか。現場やデータ分析チームからのヒアリングなのか
藤井:課題分析テーマシートを現場からもらってから業務に着手するケース、私たちがヒアリングするケース、どちらもあります。
Q:データ分析から性能やデザインへFBする取り組みは行っていないのか
藤井:設計や3次元形状などでAIを活用し改善したいとのニーズは確かに上がってきています。ただ現状としては改善効果が見えやすい、製造現場のコスト削減などを最優先しています。すべてのテーマを網羅できていないのが現状で、人手が欲しいのが正直なところです。
Q: PythonとData Robotのようなツールの使い分けについて。また経営層に対するツール導入の決済はどうされているのか
藤井:PythonとDataRobotの使い分けについては、DataRobotを使った方が効率的な場合はDataRobotを使っています。データのプレパレーションツールのAlteryxもよく使います。決裁については、経営層も含め全社的にDXの理解が進んでいることもあり、すべてというわけではありませんが、きちんと説明すれば決裁が通りやすい状況です。
Q:ITツールの運用やサポートはすべて自社で行っているのか
藤井:データサイエンティスト、データエンジニア、そのほか社内システムの開発に携わっている協力会社のエンジニアそれぞれが得意分野を担当することで、基本的にはチーム内ですべて行っています。
Q: プロジェクトのその後のモニタリングについて
藤井:人数より、どれだけスキルを身につけたかだと思っています。その上で、現場に戻ったときにコスト削減や費用対効果など、業務課題の貢献まで達成できることが、重要だと捉えているからです。
ただ昨年から取り組んでいるプロジェクトのため、あまりモニタリングはできていません。一方で、受講者の約半分、200名以上に受講証を発行できたので、手応えを感じています。今年中には可視化を行い、次回のイベントで成果を報告したいと思います。
Q:データ分析の解析プログラムの開発もすべて自社内で行っているのか
藤井:新しい技術については協力会社にお願いしたり、私たちが学んだりしていますが、基本的な姿勢としては、すべて内製化するという想いで臨んでいます。
ヤマハ発動機株式会社
https://global.yamaha-motor.com/jp/
採用情報
https://global.yamaha-motor.com/jp/recruit/
中途採用情報メールマガジン
https://survey.digital.yamaha-motor.co.jp/CareerRecruiting.html
おすすめイベント
関連するイベント