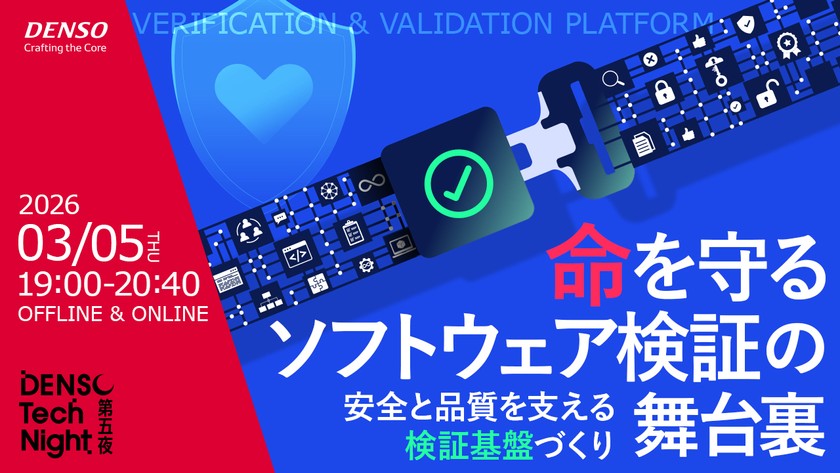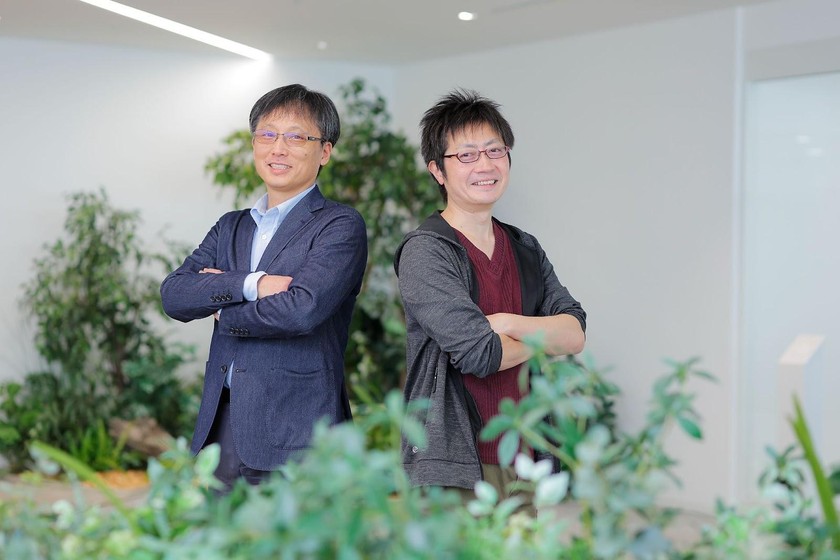Honda×AWSが仮想空間でクルマをつくる──車載ソフトウェア開発体制"Digital Proving Ground"爆速開発がスタート!~前編~
本田技研工業(以下、Honda)では、ECUと自動車関連ビジネス全般のソフトウェア開発を1つの組織体とし、開発環境をアマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWS)のクラウド基盤上で、データサイエンティストやサードパーティ、CCoEも含めた関係者がアジャイルに協調開発できる爆速開発を実現しようとしている。今回はそのソフトウェア開発体制の軌跡と展望を紹介する。アーカイブ動画
こちらの記事は【前編】です。
是非【後編】もご覧ください!
AWSとHondaがタッグを組んだ理由とは?

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
グローバルオートモーティブ事業本部 本部長 池本 明央氏
「ソフトウェア爆速開発!? クルマは仮想空間で磨き上げろ」というタイトルで開催されたHondaとAWSによるセミナー。そのトップバッターとして登壇したのは、アマゾン ウェブ サービス ジャパン グローバルオートモーティブ事業本部 本部長の池本明央氏だ。
AWSはHondaと10年以上に渡り、コネクテッドカー(インターネットへの常時接続機能を具備した自動車)の領域で、共同作業を行ってきた。2022年の中頃より、新たに取り組んだのが、組織横断(クロスドメイン)による開発ができるフレームワークの構築である。
その取り組みについて、昨年12月に米ラスベガスで開催されたAWSのグローバルイベント「re:Invent」で発表。「Hondaのチャレンジは世界の中でも高い評価を得ました」と池本氏は言い切る。

AWSはなぜ、Hondaを選んだのか。AmazonおよびAWSはフライホイールと呼ぶビジネスモデルを採用している。フライホイールとは、顧客に対して様々な価値を提供して満足度を高めることで、さらに顧客や売手を増やして売り上げを伸ばす。ビジネスのサイクルが持続可能な成長を遂げられるというビジネスモデルである。

池本氏は「このビジネスモデルで一番、大切になるのがパートナー」だと強調する。AWSはこのホイールを一緒に実現していけるパートナーを常に探していたところ、Hondaが最も「本気でイノベーションを起こしたい」という熱い思いを持っていたという。「AWSとしても、手を組まないわけにはいかないと感じました」と、池本氏は力強く語った。
Hondaが爆速開発のパートナーにAWSを選んだ理由

本田技研工業株式会社
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
コネクテッドソリューション開発部 部長 野川 忠文氏
続いては、Hondaのソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 コネクテッドソリューション開発部 部長の野川氏が登壇し、HondaがAWSを選んだ理由について紹介した。Hondaでは、開発プロセスにおいて、まずソフトウェアを定義した上でハードウェアを決めていく。
現在は、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)という考え方を推進しているという。SDVをプラットフォームとして、どのように活用するのか。
「AWSは元々、Amazon(インターネット通販)を支えるインフラとして生まれ、外向けにサービスとして提供したもので、今やAmazonの事業を支えています。これは我々が今つくろうとしているSDVプラットフォームと同じ。SDVをそのような存在に育てていくには、技術はもちろんですが、経験やカルチャーが重要になる。だからそれを学べるAWSを選んだのです」(野川氏)

Hondaは4輪のクルマだけの会社ではない。二輪、汎用機、ジェット機もつくっている。今では宇宙での乗り物という話も出てきているという。
「最終的にはSDM(ソフトウェアデファインドモビリティ)まで広げていきたいという想いで開発を行っています」(野川氏)
これまではクルマはハードをつくり、車内システムをつなげてから、車外とつながるシステム(コネクテッドサービス)の検証などを行ってきた。だが、それではIn-Car/Out-Carのソフトウェア開発のスケジュール感が合わない。
それらを解決するためにHondaが考えたのが、「デジタルプルービンググラウンド(DPG)」である。プルービンググラウンドとは、クルマのテストコースのことだ。SDV開発者はそれぞれ時間や場所、スキル、担当する車両などが異なる。
そのさまざまなSDV開発者が、いつでもどこでも簡単に開発できるバーチャルな環境がDPGである。
「まずは車載ソフトウェアの仮想開発環境からつくります。最終的には一般ユーザーからのデータをもとにニーズを取り込み、そのデータを利活用しながら価値を継続的に生み出していけるようにする。それがDPGの目指す姿です」(野川氏)

AWSに突撃し、自由自在に爆速アジャイル開発!
続いては、Honda×AWSの爆速開発において、ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部で活躍している4人のエンジニアによる具体的な開発内容に関する発表が行われた。

本田技研工業株式会社
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
コネクテッドソリューション開発部コネクテッドソリューション課 水原 涼太氏
まず登壇したのは、2020年にHondaに新卒で入社して以来、コネクテッドプラットフォームの開発周りに携わり続けている水原涼太氏だ。Honda×AWSの爆速開発の仕組みづくり、DPGが生まれた背景について語った。
Hondaが目指すDPGとは顧客のニーズを取り込み、それを満たすための製品をSDV開発者がセルフサービスで、爆速開発して提供することができる開発環境だ。この構想に至った背景には、「やりたい開発がなかなか進まないことがよくあり、もどかしさを感じていた」と水原氏は言う。
例えば、水原氏が欧州向けのエネルギーサービスを開発していた時に、自社の車であるにも関わらず、電力会社のエンジニアの方が詳しいことがあったり、コネクテッドプラットフォームが使いにくかったりするなどの困りごとがあったという。
そんな時に、次世代車両とクラウド間の通信方式について、研究開発を推進していた先輩の野上大樹氏から「AWSの開発手法を一緒に見に行かないか」と、誘いを受けた。そこで水原氏たちは突撃隊を結成し、米・サンノゼのAWSのラボを訪れた。

水原氏たちは、自分たちがどんなことに困っているのか、事前にメンバー4人でワイガヤ(話し合い)を行い、困りごとを言語化した。すると、「なかなか車両側のスペックが公開されない」「実際にテストをしたいが、テストに使える車両がない」など、さまざまな困りごとが出てきた。
事前準備をしていったこともあり、現地では20人以上のエンジニアから話を聞けたという。
「一番、驚いたことは、AWSのエンジニア全員が自社での開発者体験、開発環境に不満がなかったことです」(水原氏)

AWSでは、あるべきことにフォーカスできる組織や仕組みがあり、独自のサービスづくりの考え方が明確にされている。その中でも最も水原氏が驚いたのは、つくったものをユーザーにシームレスに届けられる基盤は、約10年前から存在していたことだ。
「開発者がインフラやデプロイ方法を気にすることなく、自分のつくったソフトウェアの価値をユーザーに爆速で提供できる仕組みが、もう既にできていたんです。そこに感銘を受けました」(水原氏)
水原氏は、日本に帰るとすぐにマネージャー層を呼び集め、報告を行った。そして、その場でDPGをつくっていく話を進め、予算も確保したという。日本に戻ってからは、すぐDPGの開発が始まった。アジャイルで取り組んでおり、画面や一部機能は稼働し始めている。

仮想化による実車レス開発への挑戦

本田技研工業株式会社
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
モビリティシステムソリューション開発部ソフトウェアエンジニアリング課 東 敦斗氏
続いて登壇したのは、クロスドメインのSDM開発環境(DPG)でサブリーダーを務める東敦斗氏だ。
東氏は「なぜ、実車レスを目指すのか」について、第一に「SDV化によって、ソフトウェアの検証量が増加していること」を挙げた。ソフトウェアで制御される機能が増えることで、ソフトウェアの規模が増大していること、そしてOTA(無線通信による車両とのデータ送受信)によるアップデートで、ソフトウェア更新頻度も上がってきているからだ。一方で、バーチャルな環境でテストできる割合も増えてきていることから、「仮想化への期待が高まっている」と、東氏は語る。

第二に挙げられたのは、検証用の実車、ECUというハードウェアが不足していることだ。ハードウェアの空き待ちが発生したり、セットアップに時間がかかったりするだけではなく、開発初期はそもそもハードウェアがないという課題がある。
これらを解消するために、「各開発者がそれぞれ自分の仮想車両を持って、いつでもどこでも開発できることを目指しています」と東氏は語る。
仮想化のメリットは「早い(Early)検証」と「速い(Fast)検証」の2つが実現することだ。前者はECUサンプルが上がってくる前にソフト開発・検証を開始できたり、クロスドメインで仮想モデルを共有したりすることで早い段階で幅広い検証ができるようになる。
後者はライセンスさえあれば、並列化を増やしてスケーラブルな数を検証することができ、適切な仮想環境を使い分けていくことで、故障原因の切り分けが可能になる。
「この2つの『早い・速い』検証で爆速開発を実現していきたいと考えています」(東氏)

ではどのように実現していくのか。まず、Core ECUというソフトウェアを集約化するコンピュータの仮想化を実現する。
次にArea ECUやデバイスを仮想化し、それらを時間同期で接続してシミュレーションする。このようなステップで仮想車両をつくっていく。
この仮想車両つくりに活用するのがAWSである。AWSは仮想ECUを提供する仕組みづくりとの親和性が高いからだ。

例えば、「EC2 Graviton」はAWSが提供するArmアーキテクチャのプロセッサである。ECUで使用しているのはArmプロセッサであるため、クラウドで開発したソフトをシームレスにECUの上で動作させることができる。
また、マーケットプレイスを利用すれば、ECUに乗せるOSやミドルウェア、テスティングツールなど、容易に実行環境や検証ツールの導入が可能になる。しかも仮想開発に欠かせないスケーラビリティも担保できる。

だが東氏は、「仮想化できれば終わりではない」と語る。以前、仮想ECUを用意したところ、開発者から「用意されても、何の検証が可能なのか、使い方がわからない」などの声が上がり、実機で進めることになったことがあったという。
このことから東氏は「仮想化の段階によって何ができるのか、その価値をユーザーに提示することの大事さを学びました」と話す。
東氏は、この教訓とAWSから吸収したプラットフォームエンジニアリングの考え方から、仮想車両を活用したソフトウェア開発のゴールデンパスをつくっていこうと、現在AWSと共に挑戦している。

今回の活動を振り返り、東氏は以下のように語り、セッションを締めた。
「モビリティのプラットフォームを築き上げていくモチベーション、AWSさんとともに成長していく喜びを得ることができました」(東氏)
クライアントファーストで構築するデータ利活用基盤

本田技研工業株式会社
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
コネクテッドソリューション開発部コネクテッドソリューション課 チーフ 中野 眞希氏
続いて登壇したのは、2021年に中途入社し、データ利活用基盤の開発・運用を担当している中野眞希氏だ。中野氏は主に、DPGのデータ利活用領域について解説を行った。
現在のHondaコネクテッドデータ利活用基盤は、以下のスライドのような構成となっている。その中で中野氏が担当しているのが四輪車両走行データの社内および社外活用のための仕組みだ。
「この部分におけるユーザーからの課題や問題の解決を、AWSと共に図っています」(中野氏)

さらに、「理想的なデータ利活用基盤とはどのようなものか」について、中野氏はこう語っている。
「一般的にレスポンスが早い、マルチクラウド、最新のテクノロジーが使われているなどが挙がると思いますが、そうではありません。スーパーアプリではなく、ユースケースごとに必要なソリューションを考えることが重要です」(中野氏)
データ利活用にはニーズだけではなく、ユーザーペインもある。例えばコネクテッドのデータを収集してAmazon Redshiftにロードしようとしても、うまくいかないことがある。
Amazon Redshiftの問題だけではなく、その上流のシステムの処理に問題があったり、欠損異常値があったりするからだ。それに加え、データ収集してもデータをどのように活用できるかわからない人も多いだろう。
「どんなデータが必要か、データサイエンティストとデータエンジニアとの調整が必要なため、データ利用までにリードタイムが発生してしまうという問題点もありました」(中野氏)

これらのユーザーペインを解決するため、約2カ月という爆速で、データ取得のオンボーディング時間を改善するパイロットシステムをAWSとともに構築した。
その際に重視したのが、データディスカバリ機能の強化、データロードのセルフサービス化、他システムと結合しやすい仕組みをつくれるよう拡張性向上の3点である。
「これらの技術要素は、現行の利活用基盤はもちろん、DPGにも必要になる要素なので、今後も適用していきます」(中野氏)

AWSとは、「パイロットシステムをつくって終わりではなく、事業性の試算まで実施しました」と、中野氏は語る。
まず社内向けのデータ配信サービスや、社外向けのデータ配信サービスというビジネスを開始した場合の収益を計算。ROIがプラスになるように、AWSのメンバーとHondaのステークホルダーが集まり、「山籠もり(会議)」を2日間実施した。
ROIをビジネス観点から検証し、さらに攻めのデータ外販ビジネスが展開できるような仕組みを検討したという。
「パイロットシステムの構築により、次期プラットフォームの礎ができました」(中野氏)

今回の活動を通して、中野氏はHondaおよびAWSのすごさを実感したと語る。Hondaのすごさの第一は、年齢問わず、意思のある人に対してはやりたいことにチャレンジさせてくれるボトムアップのカルチャーがあること。
第二はHondaに貢献できる取り組みであれば、会社として支援、評価してくれること。第三に事業会社ではあるが、最新のテクノロジーに触れることができること。さらに最新のテクノロジーを取り込もうとするカルチャーがあることだという。
「Hondaで何か取り組みたい意思のある人は、ぜひ、Hondaにジョインしてください」と中野氏は呼びかける。

次にAWSのすごさについて語った。第一にHondaに対してリスペクトがあり、Hondaの三現主義の基、共にユーザーの声を拾い上げてくれること。第二にAWSは常にユーザーにとって最適解を一緒に考えてくれることだと言う。
「他社製品とのインテグレーションを考えてくれますし、自社のサービスを使ってくださいという提案もしてくることもありません」(中野氏)
さらにAWSサービスの仕様を、Hondaにとって使いやすいように変えようと爆速で動いてくれる。「AWSの本当に素晴らしいところ」と中野氏は強調し、次の登壇者にバトンタッチした。
AD/ADAS開発を進めるデータ開発基盤の構築

本田技研工業株式会社
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部
先進安全・知能化ソリューション開発部先進安全プラットフォーム開発課
アシスタントチーフエンジニア 畑 圭輔氏
続いて登壇したのは、2017年にHondaに転職し、次世代シミュレーション環境開発プロジェクトなどに携わった後、2023年からは自動運転システム開発におけるデータ基盤構築プロジェクトのリーダーを務める畑圭輔氏だ。
畑氏はAD/ADASにおけるデータマネジメントシステムの開発プロジェクトを立ち上げ、現在は同プロジェクトのリーダーとして推進している。
ADはシステムが主体となって車両を運転する機能だ。一方、ADASは安全運転支援システムなので運転の主体は人。その運転をサポートするシステムである。
AD/ADAS開発では、データ活用が必須となる。テスト車両運行データ、カメラのビデオデータ、レファレンスデータ(テスト車両が正しく振る舞えているのかを確認するための正解データ)、メタデータ(テスト車両の走行の軌跡、ドライバーのコメントなど)という多種多様な大量のデータを、開発や検証のチームに届けなければならない。
だがデータの流れが滞ってしまうと、「開発が遅れてしまうだけではなく、AD/ADASの性能にも直結してしまうのです」と、畑氏は指摘する。

このようなデータ基盤はこれまで、なかったわけではない。これまで走行テストは地域が日本限定だったので、国内の拠点にオンプレミスのサーバを立て、データを管理していたのだ。
だが、走行テストは海外でも行われるようになった。またセンサーの性能も向上により、データ量も増加してきた。
「今までのオンプレミスの環境では多拠点での開発の変化にも耐えられなくなると考え、AWSで新しいデータ基盤を構築することになりました」(畑氏)

以前のAD開発では延べ130万kmの走行テストを実施し、精度を高めてきた。今後はこのような走行テストが、世界中で始まる。しかも高機能センサーの搭載により、テスト車1台から1日10数テラバイトのデータが生成される。
この膨大なデータをAWSにアップロードする手段として、当初はインターネット回線の利用を考えて試算したところ、1日1台分のデータをアップロードするのに1カ月以上かかる計算になったという。
そこでAWS Direct Connectという専用線のサービスを使い、AWSにデータを集約することとした。国内はHondaの拠点をメインに、海外に関してはAWSパートナーデータセンターを活用している。

こうしてデータは溜まり始めているが、「保管にも工夫がいる」と畑氏は言う。
一つはデータ保管のライフサイクルをきちんと整備すること。「ホットデータ、コールドデータ、廃棄というフローはS3のマネージドサービスを組み合わせることで省力化しています」(畑氏)
次に、保管のルールを守ることだ。例えば米国では、e-Discoveryという電子証拠開示制度がある。民事訴訟で情報開示が求められた場合、正しくデータを開示する必要があるのだ。このようなルールに対応する機能も、AWSのマネージドサービスには備わっている。

データの保管はできても、そのまま利活用できるわけではない。そこで利活用するための前処理が必要になる。
「それもAWSの中で行っています。例えば顔やライセンスプレート(ナンバープレート)の匿名化。そういう処理もAWSでやっています」(畑氏)
それらの利活用をより推進するため、ダッシュボードも構築し、取得データの可視化も実現している。

まだプロジェクトは途中とはいえ、「AWSのマネージドサービスや仕組みにより、リソースの集約がかなりできた」と、畑氏は評価する。
リアルな車を扱っているので、クラウドとの接点はかなり苦労したが、インターフェースに関するサービスも充実していたので、自分たちで設計・構築できたという。
「3~4人という少人数で構想から約1年である程度形にできたのは、マネージドサービスが充実していたからです。とても助けられました」(畑氏)
【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答
セッション後は、参加者からの質問に登壇者が回答した。抜粋して紹介する。
Q.ArmコアはAWS Gravitonを活用して仮想化実現とのことだが、周辺IPなどの仮想化はどのように対応するのか?
東:SoCベンダーと提携しながらやっていくことを想定しています。HondaとしてのカスタムSoCをつくっていくことを実現していきたいですね。
Q.ハイブリッド人材育成には、どのくらいの期間を要するものなのか?
(教育が終わる期間ではなく、個人で理解し、開発を進められるレベルになる期間)
野川:ハイブリッド人材が必要だと理解することが大きなハードルだと思います。例えば、IVIシステムはOut-carとIn-carが一緒になることでシナジーを生むので、それぞれを個別に分担するのは無理があります。
だからこそ、それぞれの強みを生かしながら両方を分かる人材が必要なのです。これからの課題はどうやってハイブリッド人材を育てていくか。今、いろいろ施策を打ちながら進めています。
Q.仮想環境は車両ドメインによって難易度が違うが、どこからターゲットにしているのか?
東:ECU単体から始め、デバイスモデルをつくっていくことになると思います。モデルを用意するようになるには、実際に提供しているベンダーと協力してつくっていくことがカギになります。
Hondaではモデルをつくる方法については、各部署に対してトップダウンで、「こういったモデルを用意してほしい」というものを用意し、それを仮想環境で実現できることを全体的に広める方法を採りました。難易度の高いところに対しては、私たちが手を入れていくようになるかもしれません。そういう状況です。
※【後編】の記事もぜひご覧ください ※
本田技研工業株式会社
本田技研工業
本田技研工業のキャリア採用情報
Hondaグループキャリア採用サイト
本田技研工業の採用情報
採用情報 | Honda公式サイト
本田技研工業のSDV事業開発統括部 ブランドサイト
https://software.honda-jobs.com/
おすすめイベント
関連するイベント