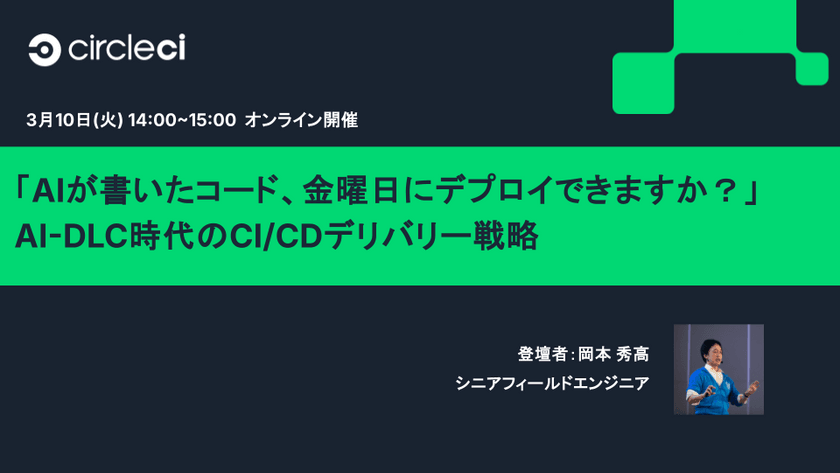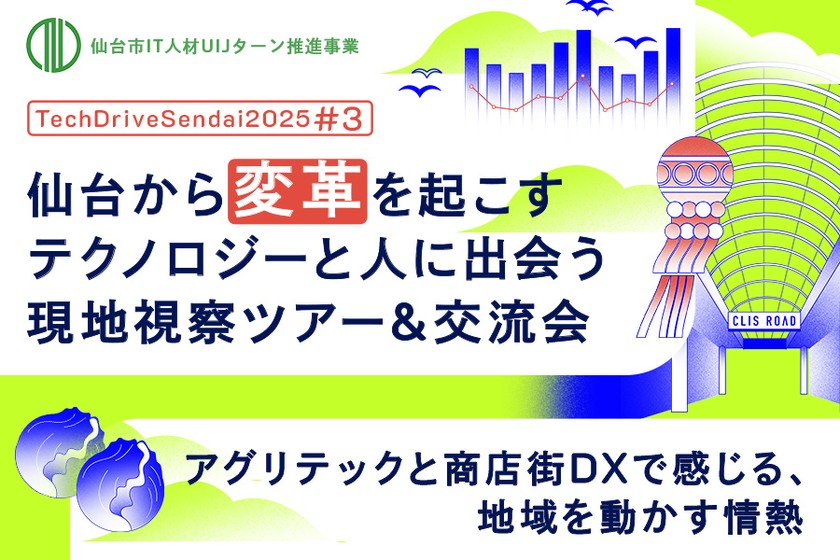【コード・フォー・ジャパン×IBM×ウイングアーク1st】北九州の地域課題に挑むリーダーと考える「地域社会×デジタル活用」 #KITAKYUSHU Tech Day2
地域社会が抱える課題が複雑化していく中で、デジタル活用の注目度が高まっている。地方自治体や企業だけでなく、市民らがテクノロジー(Tech)を活用し、ソリューションを開発・提供するシビックテックの取り組みも増えてきた。そこで今回は、日本におけるシビックテックの第一人者である関治之氏、日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスとウイングアーク1stが、基調講演やモデレーターの糸川郁己氏を交えたパネルトークを通じ、「地域社会✕デジタル活用」について語り合った。アーカイブ動画
基調講演:デジタル人材×地域市民の協業で地域課題を解決【コード・フォー・ジャパン】

一般社団法人コード・フォー・ジャパン
関 治之氏
最初に登壇したのは、一般社団法人コード・フォー・ジャパンの代表理事でもある関治之氏だ。もともとオープンソース好きのソフトウェアエンジニアであり、地域の物理的な課題解決にテクノロジーが貢献できると感じ、同団体を設立。シビックテック活動を推進しており「シビックハッカーと名乗っています」と、自己紹介を行った。
シビックテックとは、「Civic(市民)」と「Tech(テクノロジー)」をかけ合わせた言葉である。市民が主体となってテクノロジーを通じ、政府と市民の関係を改革すると共に、地域の課題を解決していくという、世界中で行われている活動である。

市民、行政向けそれぞれで活動をしており、市民であればリビングラボやハッカソン、行政であればアプリ開発やオープンデータの整備や提供などで、両者の協業によるオープンソースなデータインフラの構築などがある。
後述もするが、テックと名はついているが「エンジニア以外でも参加できる」と、関氏は語る。また、各地域がゼロベースからインフラなどを構築するのは負担が大きいため、他の自治体で構築したものを共有する。そのような環境の推進も行っている。
日本における活動も紹介した。地域住民が主体となりながらも、それだけではボランティア活動になりがちなため、中央省庁やアカデミア、IT企業や非営利団体など、さまざまなステークホルダーと協業することで、継続的なサービスを生み出していく。

その中においてCode for Japanはまさに下記画像の領域に重なる、大きく3つの柱で事業を進めている。例えばデジタル民主主義の「Decidim」とは、2016年にスペインで生まれた、市民が参加し意見交換できるオープンソースのデジタルプラットフォームであり、いまでは日本を含む、世界各地の自治体で活用されている。

地域をつなげるハブのような存在も目指しており、各地にコード・フォー・〇〇と名の付く団体ならびにコミュニティが90以上広がる。北九州市もまさにそのような地域の一つで、Code for Kitakyushuがある。

特に力を入れているのが月例で行われるハッカソン、ソーシャルハックデイであり、65以上の地域で行われている。 特にテーマは決まっていないそうだが、地域の課題や悩みなどを参加者が持ち込み、皆で話し合い、まさにハッカソンのようにテクノロジーの力で解決していくことを目指す。

先述したDecidimの他にも、地域の天候や河川の水位情報に関するデータ連携を行える基盤がある。カーボンフットプリントの量を知ることや、地域市民自身が街の状況を提供することができる。

また、おすすめのスポットや安全な公園などを提供するアプリの開発支援なども手がけている。

アプリを開発する以外の活動も行っている。例えば、ウィキペディアに地域の文化財などの情報をアップするための、ワークショップの開催である。
実際、同取り組みをウィキペディアで調べると、まさに全国各地で広がっているムーブメントであることがわかる。このようなシビックテックの事例を複数紹介した後、関氏は取り組みにおいて意識していることを、次のように話した。
「理論で関係者を説得するのは、いくら正論であっても難しいこともあります。そこで、まずはプロトタイピングでいいので実際のものを作り、見てもらうようにしています」(関氏)

関氏は具体例も示した。地域の保育園情報をよりわかりやすく提供するアプリだ。自治体のWebサイトによる情報はテキストのみではわかりづらいことから、マップにすることでわかりやすくした。
実際、このプロトタイプを持って自治体の関係者に話を持っていったところ、データの提供が承認されたという。また、本ケースのように「サービス関係者をどんどん巻き込んでいくと、シビックテックの力が発揮されます」と、関氏は述べた。

プロトタイプの作成も含め、関氏はシビックテックを進める上で気をつけている4つの「P」を頭文字とした、フレームワークを紹介した。
まずは「People」、人だ。さまざまな人たちと協業することが望ましく、そのような多様な人たちでプロトタイプを作成することで、学びや新たな課題が明らかになってくるという。

その中から良いアイデアはプロジェクトとして企業などに参画してもらい、予算をつけるなどして具体的な事業フェーズに進んでいく。
一方で、仮にプロジェクトまで進まなかったとしても、他の自治体などから声がかかることもあるので、取り組み内容はnoteなどに記載してオープン化することも心がけている、と語った。関氏は最後に親友だというオードリー・タン氏の言葉を参加者に投げかけ、セッションをまとめた。
「衝突から生まれる熱量は、新たな価値を生むエネルギーになります」(関氏)
事業会社とテクノロジー企業での経験を活かし、地域課題解決を目指す【日本アイ・ビー・エム デジタル・サービス】
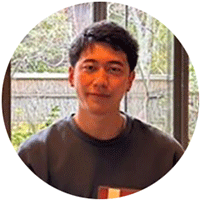
日本アイ・ビー・エム デジタル・サービス株式会社
地域DXセンター事業部 九州DXセンター
主任ITスペシャリスト 辻 聖人氏
続いて登壇したのは、日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスの辻聖人氏だ。北九州市で生まれ育ち、福岡県の大学で学んだ後、事業会社に就職。エンジニアとしてさまざまな業務や職種を経験した後、2023年に日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスに入社した。
現在は地域DXセンター事業部に所属し、自身も再び北九州市で暮らしながら、地域住民とのさまざまな共創活動にも取り組む。辻氏は自身の歩みや当時の思いを振り返りながら、エンジニアのキャリアならびに、これから求められるエンジニア像について紹介した。

まずは最初のキャリア、新卒で入社した事業会社でのシステムエンジニア時代である。カード会社のシステム開発部に所属していた辻氏は、既存システムのクラウド移行や社内ツールの開発から運用保守など、さまざまな業務に従事する。
多くのプロジェクトでリーダーを務めていたことから、当時必要であったスキルを次のように話した。
「リーダー層とのやり取りが多かったため、業務知識や課題解決力、コミュニケーション能力などのヒューマンスキルが求められていました」(辻氏)

一方で、いわゆる現場の開発エンジニアとしての技術力が不足しており、適切なレビューができないなど、不安を抱えていたという。
そこで、社内の研修を受けたり、独学で学んだりもしたが、仕事と並行して開発エンジニアのスキルを伸ばすのは難しいと判断。テクノロジー企業への転職を決意する。
それが現在の会社、日本IBMグループのITプロフェッショナル集団、日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスであり、開発部門に配属された。そして望んでいたとおり、技術力や開発経験が求められる環境でエンジニアとしての研鑽を積むことになる。

一方で、以前と同じくリーダーポジションも任されたため、コミュニケーション能力などのヒューマンスキルは変わらず必要であった。 ただ、協力会社のエンジニアに限定されること、さらには成果物の質や期日の厳守といった、さらなるスキルも求められるようになった。

辻氏は両社での経験を改めて振り返り、自身の成長や得たスキルも含め、事業会社とテクノロジー企業で求められるエンジニアの違いや課題などについて、比較したスライドを紹介した。

その上で、自身が目指すエンジニア像を、MustとWantに分けて紹介した。例えばMustでは、ビジネスとシステム両方に精通していることである。
「そのようなエンジニアは需要が高いこと。プロジェクトでの成功率も向上していくと思うからです」という理由も合わせて紹介した。
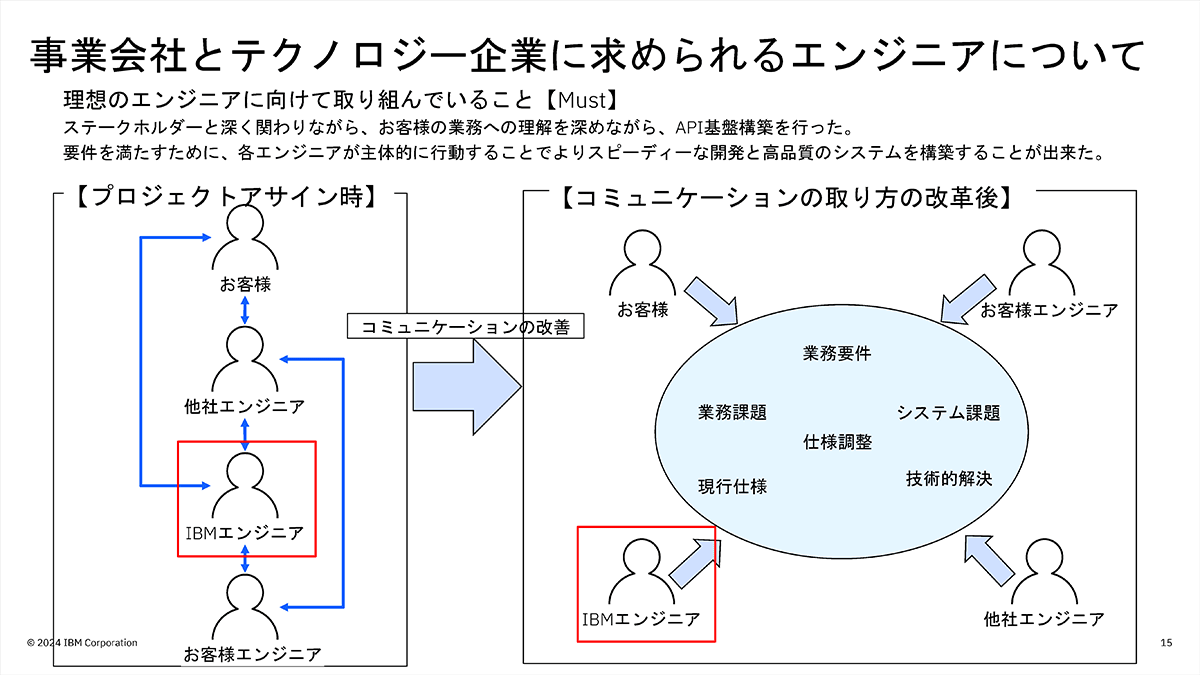
Mustの実現に向けて自身が取り組んでいることも、実際のプロジェクトの事例を元に紹介した。
あるAPI基盤構築のプロジェクトであったが、辻氏らは最初からではなく、設計段階からの参画であったため、より上流の業務要件などの各種機能などがわからず、当初は提供されたAPIを設計していくのみの業務だったという。
しかし、それでは最適解にならないと判断。それまで個別に取っていたコミュニケーションから、他のステークホルダーとも密な関係性を構築すると共に、認識をすり合わせながら開発を進めることのできる体制に変えた。
その結果、それぞれのステークホルダーが自分たちの業務に集中できるようになり、辻氏たちは機能開発のみに注力し、最適なソリューションをスピーディーに構築することができた。
Wantについては、さまざまな領域の技術や知識を増やすべく、それぞれ学べるコンテンツを使用する他に、外部の研修を受けたり、社内のエンジニアなどとも交流したりして、ノウハウなどの共有にも努めている。

現在所属する部門の具体的な取り組みも紹介された。地域の課題解決に向けて、北九州市の高校や自治体と、生成AIの活用などを議論するテクノロジーセッションなども開催している。
その他、車いすやベビーカーの利用者が、安全に通れるルートを探索するまち歩きイベントなどを開催しているという。
辻氏は最後に改めて、北九州市に拠点を持つ日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスにジョインした理由を、理想のエンジニアとなるため、かつ、地域活動にも積極的に携わることのできる環境を望んだためである、と述べ、セッションを締めた。
産官学の共創で構築した地域創生モデルを北九州市から全国、そして世界へ【ウイングアーク1st】

ウイングアーク1st株式会社
社長室 室長 兼 地域創生ラボ ラボ長 阿多 真之介氏
続いて登壇したのは、ウイングアーク1stの阿多真之介氏だ。営業職としてウイングアーク1stに入社した後、伊藤忠商事への出向などを経て、現在は社長室室長を務める。また、2024年8月に北九州市に開設した地域創生ラボのラボ長として北九州市に移住し、業務に取り組んでいる。
「情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」というビジョンを掲げるウイングアーク1stは、2004年の設立以降、データ活用に関するサービスを提供しており、2つのメイン事業を展開する。

1つ目は、請求書や納品書といった各種帳票の作成や管理を行うソリューションであり、市場シェアは69%と、国内トップを誇る。

もう一つは企業内外のデータを可視化する各種ソフトウェアサービスであり、こちらも市場シェア24%と、高い数字を誇ると共に、着実に販売数も伸びている。
ウイングアーク1stは2021年に、J3で活躍する北九州市のプロサッカーチーム、ギラヴァンツ北九州と北九州市との3者で、連携協定を締結したのを契機に、北九州市に進出していく。
エンジニア採用を考えた際、年間約3000名という理工系人材を輩出していること、北九州市が積極的にデジタル化を推進していることなどが背景にあったと、阿多氏は語る。
2023年7月には、北九州市と包括連携の協定を締結。阿多氏がラボ長を務める地域創生ラボの開設へと続く。「2030年までに累計100名のエンジニア採用をしたいと考えています」との展望を述べた。
そして、新たに採用した人材も活用することで、北九州市発で構築した地域課題解決モデルを産官学で共創しながら全国、そして世界へ展開することをビジョンに掲げている。

ウイングアーク1st、北九州市、それぞれが具体的に掲げている、2030年までに実現したいテーマの詳細を記したスライドも示すと共に、4つの取り組みについて詳しく紹介した。
1つ目は「DX・GX推進」だ。北九州市のGX推進コンソーシアムに賛同すると共に、まずはCO2の排出量を可視化する「EcoNiPass」というツールを無償で提供している。

2つ目は「雇用創出・人財育成」についてだ。ウイングアーク1stが北九州市に進出した背景には、先ほど述べた理工系人財の雇用がある。実はこの背景は視点を変えると、北九州市側にとってもありがたいものであった。
現在も着実に増えてきてはいるが、それでも北九州市の大学などを卒業した優秀な理工系人材の市内での受け入れ先となるIT企業は、未だに乏しいからだ。そこで進出しただけでなく、各大学に出向き、出張授業のようなイベントを開催しているという。
さらには、自社のオフィスに学生を招き、ハッカソンはもちろん長期的にプロジェクトに携わることのできる、インターンシップなども提供している。「中にはプロダクトの実機能の実装に携わる優秀な学生もいます」と、阿多氏は成果を述べた。
3つ目と4つ目は「地域活性化」に関する内容だ。ギラヴァンツ北九州のチーム強化に向け、心拍数や走行距離などを測定するセンサー機器やカメラを含めたスポーツテックを提供することで、選手のパフォーマンスアップを目指す支援も行う。

もう一つはサッカーの試合を観に来た人たちに、帰りに小倉の街を回遊してもらい、地域を活性化する取り組みであり、同プロジェクトはまさに進行中だという。最後に阿多氏はUIターン、非エンジニアという属性も踏まえた上で次のような見解を述べ、セッションをまとめた。
「北九州市にはプロボノ的に活動される方が多く、産官学のステークホルダー全員が、より良い取り組みを前向きに行っている街だと思います」(阿多氏)
産官学が連携し、シビックテックも含めたIT・デジタル化などDX推進を継続
講演セッションが終わった後は、北九州市のシビックテックやデジタル推進と関わりの深い、糸川郁己氏も参加し、パネルトークセッションが行われた。

I.I. 代表
Code for Kitakyushu 顧問
(公財)北九州産業学術推進機構 ロボット・DX推進センター マネージャー
NPO法人Startup Weekend 認定ファシリテーター 糸川 郁己氏
まずは、北九州市におけるシビックテックも含めたIT・デジタル推進の現状などについて、自身の取り組みも含めて紹介した。

糸川氏は2014年にコード・フォー・ジャパンと連携する北九州地域におけるITコミュニティ「Code for Kitakyushu」を有志と共に立ち上げた。
そして、コロナ禍中の2020年には他地域で活動するITコミュニティが開発したツールを北九州市用にカスタマイズし、テイクアウト可能な飲食店の検索アプリ「北九州テイクアウトマップ」を提供。同アプリは、多くの市民に利用されるなど、多くの市民の生活に貢献した。

現在は、北九州市の外郭団体である、北九州産業学術推進機構(FAIS)のロボット・DX推進センターでの活動がメインであり、北九州市に拠点を構える企業のDXを推進するための相談や、専門家の派遣業務などに携わっている。
実際、このような取り組みの結果、市内の企業の多くがDXに取り組んでいる。かつ、経済産業省が開催するDX関連のアワードを受賞するなど、確実に成果も出ているという。

また、北九州市はIT企業の誘致にも積極的で、ここ10年でIT企業188社が進出。4600人もの新規雇用が生まれている。さらにはこのような機運や流れをより醸成するべく、産官学によるさまざまなDX支援に取り組んでいることが紹介された。
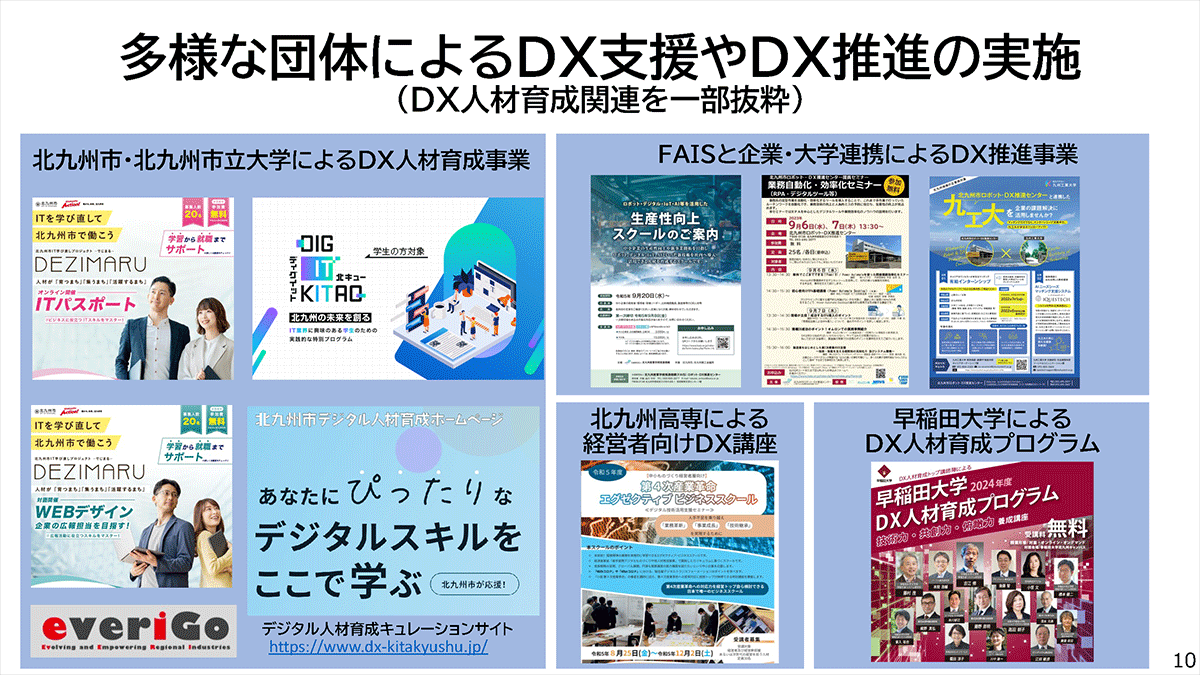
【パネルトーク】地域社会のデジタル活用やシビックテックについて考える
ここからは糸川氏がモデレーターとなり、登壇者も加え改めてシビックテックの推進について、語り合った。
糸川:ウイングアーク1stさんが手がけている、Z世代向けの企画が気になりました。
阿多:講演で紹介した、ギラヴァンツ北九州のプロジェクトになります。ホームゲームの集客から街への回遊などを、まさしくZ世代のメンバーをアサインして行っています。
糸川:Z世代の採用はどのように行っているのでしょうか?
阿多:各大学への出張授業やオフィス見学会など、まずは当社を知ってもらう活動から始めています。またこのラボで務めるZ世代にはIターン人材もおりまして、東京からに限らず、長野からなど他の地域からの移住者もいます。
糸川:実際に北九州市に移住されてどうですか?
阿多:移住支援制度を会社独自で整備しているおかげで、移住ハードルは低いと思います。移住支援に関しては北九州市でも同じく支援制度がありますので、そちらも参考にしてもらえればと思います。
私が働いているラボが入居しているビル(BIZIA KOKURA)には、コワーキングスペースが設けられております。本日登壇された日本アイ・ビー・エム デジタル・サービスさんも入居されており、その場を活用し入居企業同士や地場企業の方々とも交流の機会を持つことができありがたいです。北九州の方々は、地元の企業、市役所の方々、大学生まで、みなさん温かいと感じています。
※参考サイト:北九州ライフ
糸川:私も北九州市生まれではありませんが、移住してきて、人の温かさを感じています。以前、街でお店までの道を訪ねたら、わざわざ店まで案内してくれました。
阿多:地域の方たちと一緒になって、北九州市を共に盛り上げることができたらと思います。
糸川:一方でUターンされた辻さん、コミュニケーション改革ではITツールなどは活用したのでしょうか?
辻:当初はドキュメントだけのコミュニケーションになっていたため、みんなで1つの輪になって話すような機会がなく、認識齟齬などを感じていました。そこでコミュニケーションツールを使い、オンラインでもいいからみんなを巻き込んだコミュニケーションを意識しました。
糸川:私も「北九州テイクアウトマップ」の開発の際には、要件をシンプルに伝えるだけでコミュニケーションが少ない、とメンバーから指摘されたことがありました。まさに辻さんも、事業会社にいたからこその気づきだと感じました。
最後に話された地域との関わりについて、エンジニアがどのように関わっていくべきか、お考えを聞かせてもらえますか。
辻:こちらでもまずは、地元の方とコミュニケーションを取ることが大事だと考えています。その上でエンジニアとしてどのような技術を使えばよいのかなど、進めていきたいと思います。
糸川:関さんは北九州市の現状を聞いてみて、いかがでしたか?
関:IT企業がこんなにも数多く進出しているとは驚きでした。一方で、市民・行政・企業が連携して作ったツールなどは、先の豊岡市のように使われやすいのが特徴です。
ボランティアだけでは限界がありますし、企業と一緒に活動することでプロトタイプから実際のサービスレベルへの接続がうまくいくと考えているからです。
実際、シビックテックがうまく進まない要因にもなりますが、いくらハッカソンで優れた技術ができたとしても、ニーズにフィットしていなかったり、データの共有が得られなかったり、人と人が共に考えつながっていかないと、うまくいかないと思うからです。
そういった観点からも北九州市は市民自らが参加している座組が素敵であると共に、シビックテックのポテンシャルが高い地域であるとも感じました。
糸川:今後さらに地場企業なども含めて地域内で盛り上げていく方法をお聞きしたいです。何か、うまくいく工夫などあれば教えていただけますか。
関:自治体でも多様な部門がありますし、市民もさまざまな人たちがいます。その中で活躍しているキーマンがいるので、そのような方たちと熱量を持って未来について話し合う場を設けることが重要だと考えています。
そして、そのような場はオープンにし、できるだけ皆が参加すること。かつ、オフラインで一緒にお酒を飲むような場であることも重要だと思います。飲みニケーションは、全国共通ですから(笑)。
阿多:まさに私と糸川さんの出会いも、飲み会の席でお隣だったことでした(笑)。北九州市はこのような進出企業と地元の企業が、IT企業や事業会社との垣根を超えて、出会える場を設けてくれているのでありがたいと思っています。
辻:お話を聞いていて、コミュニケーションは何かを始める大きな一歩だと考えていました。実は私もCode for Kitakyushuのイベントに参加したことがあります。エンジニアであるかは関係なく、コミュニケーションを広げていくことで、10年後理想の街になっていればいいと思います。
糸川:改めて、地域をテクノロジーで変えていきたいと考えている方にメッセージをお願いします。
関:シビックテックの活動はエンジニアだけのものではありませんし、エンジニアだけの活動ではうまくいきません。多様な人が参加する必要があります。
コーディングができなくても手伝えることはいろいろあるので、まずはCode for Kitakyushuのようなコミュニティに参加し、メンバーと語ることが大事だと思います。
阿多:先に話題に挙げたように、北九州市にはIT企業が多く進出しています。そのため北九州市で働くという選択肢が増えてきています。もう一つ、私は東京から北九州市に移り住んだことで、QOLがとても上がりました。働く場所もあり住みやすい。おすすめの場所だと思います。
辻:エンジニア目線でのメッセージになりますが、北九州市で働くエンジニアのスキルが低い、ということはありません。現に、私が働く会社でもみな成長意欲が高く、実際にスキルも向上しています。北九州市で活躍したいと考えているエンジニアがいましたら、ぜひいらしてください。
KITAKYUSHU Tech Day
https://impact-kitakyushu.jp/
おすすめイベント
関連するイベント