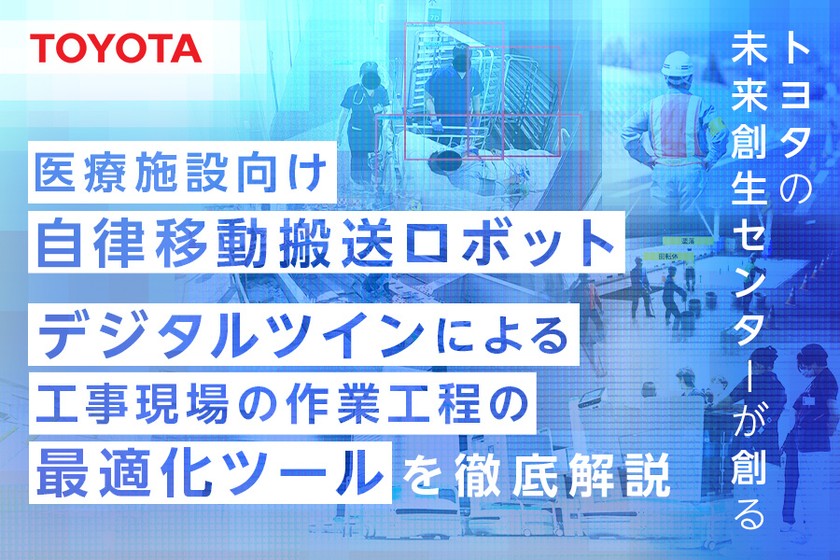トヨタの未来創生センターが創る「ヒューマノイドロボット」 ──アーキテクチャ・運動制御理論・要素技術・実装事例を徹底解説
トヨタの未来につながる研究をミッションとする組織「未来創生センター」。今回は、ヒューマノイドロボットの開発について、ハードウェア・ソフトウェアの両面から、その特長や技術、研究課程について紹介する。アーカイブ動画
「運動性能」+「遠隔技術」でWOW(感動)を創造する

未来創生センター 主査 野見 知弘氏
最初に登壇した野見氏は、まずトヨタの未来創生センターについて説明した。野見氏いわく、未来創成センターとは「事業計画にはない」研究開発を自由に行う集団。具体的には、ロボティクス、革新インフラ技術、バイオヒューマン、数理データサイエンスなど取り組んでおり、今回登壇したメンバーは、ヒューマノイドロボットの研究開発を推進している。
ヒューマノイドロボットの実用化に向けては、ロボットに詳しい人ほど「難しい」と考える人が多い。一方で、未来創生センターのメンバーに「100年後のロボットと共存する社会」をテーマにAIアートを描いてもらったところ、以下のような絵が得られた。
「ロボットと人が結婚したり、ロボットが人を介護したりなど、ロボットと人が共存する未来の社会に見えます。いずれこのような未来が実現するのであれば、自分たちの手で創造したい。人類の歩みを加速させたいと考えました」(野見氏)

未来を創造する一方で、今の瞬間も大切にしていると野見氏は続ける。例えば、衣食住以外、旅行やスポーツの中にこそ、人生を彩る大切なものがある。それらに対し、自分たちの技術で人々の暮らしを便利に快適にできるものを創りたいのだという。
コロナ禍でその想いは強くなり、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、TOKYO 2020)のマスコットキャラクターのロボット化、フリースローを行うAIバスケットボールロボット「CUE(キュー)」のさらなる開発につながっていく。
CUEは、B.LEAGUE(以下、Bリーグ)のオールスター戦に出場したり、TOKYO 2020開催中には、大会の初日から最終日まで、期間中の全日程で毎日パフォーマンスを披露。いくつもの賞も獲得している。

トヨタ自動車は「幸せの量産」をミッション、「可動性を社会の可能性に変える」をビジョンに、すべての人に移動の自由を提供するモビリティカンパニーを目指している。
可動性には心の移動、感動といった意味も含まれていることから、ヒューマノイドロボットの開発においては、「運動性能の向上」と「遠隔技術」を軸に、心の移動であるWOW(感動)生み出していきたいと、野見氏は語る。
ヒューマノイドロボットの開発は、さまざま技術領域の専門家が業界の垣根を超えたオールジャパン体制で取り組んでいる。各領域の専門家が、チームを組んで取り組んでいることも特徴だ。

ハードウェアの要素開発、ロボット全体の設計をスピーディに

未来創生センター 主幹 原田 哲志氏
続いて、登壇したのは、ハードウェアの機械設計を担当する原田氏である。
ハード面においては可動性を高めるために、「パワー」「スピード」「精密性」「柔軟性」という4点に注力して開発を進めていると、原田氏は語る。
開発はアクチュエーター、アンプ、バッテリーといった要素領域から全体の設計までと幅広いのも特徴だ。CAEを駆使しながら、自ら開発した要素や機構のアイデアを実現していく。原田氏はやりがいを次のように話した。
「要素開発から行うため、実際にどのようなシーンで使うのか、どのような設計にすればよいのか、自分の思いや裁量を反映することができます」(原田氏)

自動車開発で培ってきた技術も活かされている。例えば、鉄、アルミニウム、ジュラルミンなど、さまざまな素材の金属を複雑な形状に加工する技術だ。加工の依頼や部品調達を依頼できる環境も整っている。
また、バスケットコート1面ほどの広さを誇る実験場に評価施設が整備されており、余裕を持った状態で確実に評価を行うことができる。評価から設計へのフィードバックサイクルも速く、「そこにやりがいを感じている」と、原田氏は語った。
開発しているヒューマノイドロボットは、先の「パワー」「スピード」「精密性」「柔軟性」に主眼を置いて開発を進めており、ロボットにより注力領域が異なる。

パワー、スピード、精密性の特徴を持つ「CUE」
シュートやドリブルを行うAIバスケットロボット「CUE」は、最大20mのロングシュートを正確に放つことができるなど、パワー、スピード、精密性が備わる。特に「高出力アクチュエータ」「高出力バッテリー」「ダイナミックな動作の機構解析と実機計測」の特徴を有する。
●高出力アクチュエータ
高出力アクチュエータは各関節に備わる。ロングシュート時には0.3秒の間に約70Aもの大電流が流れるため市販の製品では対応できず、自分たちで開発している。用途や目的により使用するアクチュエータは異なるが、主にインナーロータモータと波動減速機、アウターロータモータと遊星減速機のセットで使い分ける。
モーターは自動車用の超ネオジム磁石を使用し、90度ごとに磁石の向きを変える「ハルバッハ配列」という方法で磁力を強めている。また、極数やスロット数など数千パターンで最適化解析も実施しながら、スピーディーに開発を進める。
減速機に関しても自動車で培った技術、自動車のトランスミッションで使う高強度な開発鋼を使うことで、高出力化や軽量化が行えている。

●高出力バッテリー
シュート時にはロボット全体で数百Aの電流が必要となるため、自動車用の高出力バッテリーを小型化することで実現している。

●ダイナミックな動作の機構解析と実機計測
計測や解析では、ロボットの腕の振りによる慣性力やドルブル時、ボールとハンドの接触による撃力などにより、構成要素単品や静的な解析では乖離が大きくなる。
そこで、機構解析、動的なCAEと実機のモーションキャプチャーによる継続的な組み合わせを行いながら、振動低減の対策を行う。
「足が地面に固定されていないため、振動が誘発されることもヒューマノイドロボット開発の難しさの1つ。今後は足裏と地面の接触も考慮した解析を検討しています」(原田氏)

「トルクサーボモジュール」でしなやかさに動く「T-HR3」

未来創生センター 主任 近藤 寛之氏
続いては近藤氏が登壇。遠隔操縦とインタラクションに主眼を置いて開発された「T-HR3」における技術について説明した。

人とロボットが共存する社会では、ロボットが人のようにしなやかに動くことが求められる。例えば握手をした際、強く握り過ぎてはならないし、逆に、力が弱すぎても不自然だ。そのため、どのくらいの力がロボットにかかっているかを把握し、かかっている力に対し、ロボットをコントロールする技術が求められる。
T-HR3には、関節に働くトルクを正確に把握するために、トルクセンサーモーター、減速機などのアクチュエーターをパッケージングした「トルクサーボモジュール」が搭載されており、この要素がしなやかさを生み出す。
トルクセンサーは起歪体(外力により歪みを発生させる部品)に、非常に小さな歪みセンサーをスパッタリング(薄膜形成の手法の1つ)して整形され、感度も精度も非常に高い。
さらにトルク以外、並進力やモーメント(物体を回転させる力の大きさを表す量)といった力を最小限に抑えるのにも適している。遠隔操作では、ロボットが把握した力を遠隔地の操縦者に直感的に把握する役割も担う。

手の部分は人と同じように5本指構成とすることで、複雑なタスクを行うことを目指した。実現には「劣駆動メカニズム」を選択した。
劣駆動メカニズムとは、実際に動作する関節数に対して駆動する関節数が少ない、受動的な要素を持つ構造のこと。つまりアクチュエーターの数は少なく構成しながらも、把持などの操作を可能にする。
遠隔操作では、ロボットが触れた反力を操縦者にフィードバックできる仕組みを、リンク機構で実現している。近藤氏は開発の苦労と成果を次のように話した。
「親指の動きは複雑なため、自由に動かせるリンク機構の設計で苦労しました。しかし今では自分の手のように遠方のロボットハンドを操作し、コインをつかむ動作も可能になりました」(近藤氏)
軽量化は、設計・シミュレーション技術のひとつである「トポロジー最適化」という手法を採用した。指定条件と範囲内で最も軽量な構造に収束していくことで、最終的に同等の強度を持ちながら30%以上の軽量化に成功した。

小型マスコットロボットだからこその工夫が多数搭載
マスコットロボットの特徴も紹介された。幅広い層とのコミュニケーションを実現するために、かわいらしい容姿をしているが、中身は本格的なヒューマノイドロボットだ。近藤氏は小型化の実現など、その工夫について説明した。
スライド左側の脚部では、関節トルクを補助するスプリングにより自重指示をアシストしたり、リンク機構を使うなどして、足先の計量化を実現している。
マスコットはバランス的に頭が大きいため、首関節の強度が求められる。そこで小さなモーターでも大きな出力を発揮できる「球面パラレルメカニズム」を採用した。口まわりの動きも配慮している。

また、操縦者の目線を追うようなアイトラッキングだけでなく、ハートマークで喜怒哀楽を表現するような仕組みがアイディスプレイに施されている。ただ、当初は苦労もあった。
「初期の試作段階では、ファイバーオプティカルプレートという、レンズの奥にある画像を表面に伝達する特殊な素材に 反射防止コーティングを施していました。しかし、天井の強い照明などが写り込んでしまい、美しく表現できませんでした」(近藤氏)
そこで、コーティングの種類や素材の見直しなどの試行格錯誤を重ね、通常のガラスの約10分の1の超低反射の特殊ガラスを採用。反射を抑えながらも、ディスプレーの色味も損なうことなく表現できるよう改良された。

着ぐるみを着ているような状態でもあるため、熱がこもりやすいとの課題もあった。かつ、小型でもある。そこで小型な体内でも納められるアクチュエータを、3軸まとめて駆動できるアンプパッケージとした。
加えて、従来のシリコンからガリウムナイトライドで開発したことで、発熱がかなり抑えられた。現在はさらなる可動性の向上を実現すべく、ロボットのさらなる運動性性能の獲得、飛躍に向けた研究開発を進めている。

ソフトウェア開発の特徴とソフトウェアアーキテクチャ

未来創生センター グループ長 森平 智久氏
ソフトウェアの全体概要や特徴などについては、森平氏が説明した。小型・大型に限らずヒューマノイドロボットの構成は共通化されており、CPUで動作する各種ソフトウェアを組み合わせたソフトウェアプラットフォームとなっている。

高性能なアクチュエータやセンサー類の性能を最大限発揮させ、制御性を高めるためにはできるだけ早い時間でプログラムの変更や制御を行う必要がある。現状ではLinux上でリアルタイムパッチを行うことで実現している。通信・フィールドバスにおいては、EtherCATを採用。1ミリ秒との早い周期で体内通信を行う。
連続的で実行可能な指令値でない場合、ロボットに過負荷を与えたり、機体同士がぶつかったり、転倒するといったトラブルが発生しかねない。そこでロボットモデル、キネマティクス、ダイナミクスといったロボットの運動プロパティを配慮した上で、司令を出している。
「ここまでが制御の土台。この上に各ロボットの基本動作を実装します。このフローこそがヒューマノイドロボットならではの滑らかで情動的な動きを実現します」(森平氏)
このような基本動作の司令を担うのが、スライドの赤枠で囲われた領域だ。基本動作の呼び出し、切り替え、組み合わせを行うと同時に、周囲の環境や対象物の認識も行うことで、リアクティブ性も実現する。

ヒューマノイドロボットはシビアなリアルタイム制御が求められるため、ソフトウェアプラットフォームは独自で開発している。一方で、汎用的なロボット用のソフトウェアプラットフォーム「ROS」との連携も意識した構成でもある。
外部ツールとの連携も意識しており、プラグインの追加でさまざまなOSSの物理シミュレーターへの対応が可能となっている。
「特にまだ実在していない機体や、転倒の可能性が高い場合などは、物理シミュレータを用いた開発プロセスが必須となります」(森平氏)

「モデル予測制御」など、運動制御におけるフレームワーク

未来創生センター 主幹 土井 将弘氏
続いては、制御ソフトの開発リーダーを務める土井将弘氏が登壇し、運動制御について解説を行った。運動制御は「オンライン軌道生成」「接触制御」「全身協調制御」という3つの要素から成り立っている。
「オンライン軌道生成」では、モデルを用いて安定に動作を実現できる運動軌道を逐次生成。「接触制御」では、力センサーやIMU(Inertial Measurement Unit/慣性計測装置)などのセンサー情報を用いて、モデルと実機の誤差を吸収するように動作を修正する。
そして「全身協調制御」で、重心や足先などさまざまな運動軌道に基づいて、全身の姿勢を決定する。この一連のプロセスを周期的に繰り返すことにより、 さまざまな運動を安定的に実現している。

土井氏はさらに、それぞれのプロセスをより詳しく紹介した。
「オンライン軌道生成」プロセスは、「重心モデル」「モデル予測制御」に細分化される。 重心モデルとは重心と接触力の物理的な関係性、運動方程式そのものであり、このモデルを使うことで、入力値による重心の動き、挙動が予測できる。
モデル予測制御では、現在から一定時間先の未来までの入力を最適化することで、現在の入力値を決定する。 そしてこの予測ホライズンを後退させながら、毎時刻の入力を決定していくことで軌道が作られていくという仕組みだ。

「接触制御/動作修正」においては、前プロセスで作った軌道は着地はもちろん、足を地面につけている状態でも軌道からズレるため、常に動作を修正する必要がある。この修正を行うためのプロセスである。
この2つのプロセスを経て生成・軌道された重心や足先などの拘束条件に優先度をつけるかたちで、全身の姿勢を制御していく。その結果、スライドのような自由度の高いポーズが実現する。

それだけではない。3つのプロセスを組み合わせた運動制御のフレームワークを用いることで、さまざまな運動や動きを安定して行うことができる。
「ロボット自体が環境認識を行っているわけではありません。言ってみれば、ロボットが目をつぶって歩いているのと同じような状況です。しかしフレームワークが機能することで、常に安定した走行や運動を実現していきます」(土井氏)
強化学習を行うことで、ロボット自らが運動を制御していく
一方で重心モデルでは、関節可動域や速度・トルクの制限を、軌道生成に反映させることができないという課題があった。そこで現在では全身の運動方程式を用いた全身のモデル予測制御に取り組んでいる。セッションではトイ・プロブレムによるデモ動画も紹介された。

さらには人が制御システムを実装するのではなく、ロボット自体が深層強化学習を行うことで、自身でコントローラーを獲得できる取り組みも行っている。具体的には、人の運動軌道に近い動作を達成すると、報酬を与えるように設定。シミュレーションを繰り返すことでコントローラーの精度を高めていく。
土井氏は今後も『強化学習×運動制御』領域を探求していきたいと決意を語り、セッションをまとめた。
CUEのアプリケーション実装と機械学習の実機適応事例

未来創生センター 主幹 滝沢 良氏
続いては、CUEのソフトウェアを担当している滝沢氏が登壇。まずアプリケーションの実装事例として、シュート・自律移動・ドリブル・スラロームドリブルの特徴的な動きについて紹介した。

●シュート
手先からのボールのリリースは、幾何的に計算式で表すことができる。その後のボールの軌跡についても計算できると考えがちだが、「実際にはボールがでこぼこしているため、計算どおりにはいかない」と、滝沢氏は説明する。
実際に採用している計算手法は、ゴールまでの距離や向きを入力値、シュートの強さや角度を出力値とし、ガウス過程回帰モデルで扱う。
最初はシュートを外すこともあるが、外したデータでモデルを更新することで、次第にシュートの確率が高まっていく。なお実機では、ゴールの位置やシュートの軌道をセンサーなどで観測することで、シミュレーションと同じような調整(効果)が得られるという。

滝沢氏は、最適なシュート動作を獲得する問題解決手法の紹介も行った。ブラックボックス最適化のアルゴリズム、ベイズ最適化の活用だ。
調整するパラメータは、回転角度、動作タイミング・速度、動作開始角度といった、ロボットの司令、関節軸の動作とし、目的関数はシュートの最大距離。加えて、最大トルクや消費電力といった制約条件も設け、最適なパラメータを探す。
結果として、約20mものシュートを打てるフォームを得る。セッションでは実際にCUEがロングシュートを放つ動画も紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

しなやかで継続するドリブル、自律移動を可能にする取り組み

未来創生センター 安井 雄哉氏
自律移動に関しては、同じく制御ソフトウェアを担当する安井氏が解説を行った。
CUEの両足には、つま先とかかとに1つずつ、両足で合計4つのメカナムホイール(ロボットの移動として用いられることが多い機構)が装着されており、この4つのホイールを制御することで、前後の動き、回転からスラロームまで、しなやかな動きを実現している。
移動制御では、ホイールがついた脚部を台車、それ以外を1つの重心体と見なした「倒立振子モデル」により予測制御を行い、バランスを取りながら高速な移動を実現している。
脚部にはレーザを発射して距離を測定する「LRF(Laser Range Finder)」が搭載されており、自己位置の推定も行う。
「ボールを置いてある位置を予め手動でマッピングし、そのマップとLRFで取得したデータを照合。フィードバックすることで位置を把握し、移動や軌道を修正します」(安井氏)

ただし、4つのホイールに荷重が均等にかかっていないと、先のモデルで作成された制御が反映されない。それどころか、ホイール同士のベクトルの釣り合いが崩れることで、暴走する危険性もある。そこで、脚部に力センサーを搭載しインピーダンス制御をしている。
安井氏は引き続き、ドリブルにおけるポイントも紹介した。ヒューマノイドロボットがドリブルする事例がそもそもなかったこともあり、開発は手探り状態で進んだという。
まずは、手をまっすぐ振り下ろしてドリブルをさせようとしたが、うまくいかなかった。ボールが真上、つまりハンドに返ってこないからだ。ボール位置のフィードバックが必須だと考え、足先に距離を光学的に計測するToFカメラを仕込み、ボールの位置を認識した。ドリブルはできるようになったが、長くは続かなかった。
そこでボールを打ち出す位置や速度も考慮するように、データを収集。回帰モデルを作成して反映した。その結果、安定したドリブルが継続されるようになった。
現在開発している最新の機体、CUE6ではスラロームで移動しながら、安定したドリブルを行えるまでに進化している。

「フィジカルインタラクション」がロボットをより人らしくさせる

未来創生センター 主任 山本 一哉氏
ヒューマノイドロボットのインタラクションについては、山本一哉氏が主にフィジカルインタラクション、人とのコミュニケーションについて解説した。
フィジカルインタラクションとは近藤氏が説明したように、ロボットが人やものに接触した際、その力を正しく察知し、しなやかに受け止めることができる技術である。
セッションではヒューマノイドロボットの腕部分を模したロボットが、外力を与えられてもグラスからワインをこぼさず、人に押されてもしなやかに受け流す様子が紹介された。
「フィジカルインタラクションでは、最低限の出力で自らの姿勢を保持する制御が求められます。その際には、自らの重さも考慮することが重要です」(山本氏)

このフィジカルインタラクションの技術をT-HR3に応用したのが、まさにトヨタのヒューマノイドロボットの特徴の一つである、遠隔操作につながる。山本氏はこれをバイラテラル制御と表現した。
バイラテラル制御とは、2つの装置感での動き、作用・反作用、つまり力の受け流しを相互に制御する技術である。装置を使って遠方の操縦者がT-HR3と共通するやり取りは、まさに代表事例と言えるだろう。
操縦者がロボットをリアルタイムで動かすのはもちろん、操縦によりロボットが受けた力を、操縦者にフィードバックも行う。その結果、これも先の説明に重なるが、繊細なタスクを実行することが可能となる。

例えば、人との握手やボディタッチといった、まさにコミュニケーションである。フィードバック機構を備えているため、人が手を上下に動かした動きも、遠隔で操作している人に伝わり、即座に対応できる。
また、肩を軽く叩くようなコミュニケーションも、反力が伝わってくることで、適切な力で行うことができる。
マスコットロボットを通じてコミュニケーションを醸成する
マスコットロボットを使い、会話ではなくボディランゲージでコミュニケーションを行う取り組みの事例も紹介された。
1つは、Bリーグのマスコットキャラクター「ルークロボ」型のマスコットロボットだ。試合を見にきた観客とのやり取りを通じ、実証実験を行っている。

もう1つの事例は、NHKのEテレで放送中の番組『リフォーマーズの杖』内に登場する MCロボット「ベアツシ」だ。ロンドンブーツ1号2号の田村淳氏がリアルタイムで操縦しながら、ゲストとのコミュニケーションを図っている。
「ベアツシは口や眉毛を動かすことも可能です。田村淳さんの表情をリアルタイムで撮影して認識しながら、感情豊かに自律したMCを務めています」(山本氏)

ルークロボやベアッシのようなマスコット型のロボットは、顔が大きく胴体が太いなどの特徴がある。そのため人と同じような感覚で操縦すると、顔や体に手がぶつかるといった問題が発生してしまう。
このような衝突や干渉を回避するために、接触しそうになると反力を介し、それ以上近づけないような仕組みも備えている。そのため、マスコットロボットの操縦に慣れていない操縦者であっても、トラブルなくロボットを操作することができる。

【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答
セッション後は、イベント聴講者からの質問に登壇者が回答した。その一部を紹介する。
Q.瞬間的な大電流の供給において、キャパシタは検討しなかったのか
原田:検討しましたが、高い運動性能を実現しようとすると重量とトレードオフの関係になってしまうため、現状ではバッテリーを採用しています。
Q.CUEの身長が2m13cmの理由は?
野見:実は『SLAM DUNK』(スラムダンク)に登場する桜木花道のロボットを作りたいと考えていました。そのため当初の身長は188㎝でしたが、アルバルク東京にアレックスカークという素晴らしい選手を知り、彼と肩を並べるために同じ身長にしました。
Q.バックドライブなど、外力に対するハードウェア側の工夫
原田:バックドライブを得る工夫は、主に3つ。1つが慣性を下げる。ロータモータをできるだけ軽くする、2つ目が減速抵抗を下げる、そして3つ目が減速比を下げる。この3つを達成するために、アウターロータモーターと遊星減速機の組み合わせとしています。
Q.CUEに搭載しているセンサーの数は?
原田:くるぶしに6軸センサー、ボール認識のためのToFカメラ、環境認識のためにLRFがあります。そのほか、バランスを認識するためにIMU、ゴールを認識するためのカメラが胸にある構成です。
Q.遠隔操作時の遅延に対する取り組みについて
森平:10km離れた場所での遠隔操作(制御)の実証実験は行っており、10ms以上遅れると伝達の感触が鈍くなるという結果を得ています。
トヨタ自動車株式会社
https://global.toyota/
未来創生センター「未来につながる研究」
https://global.toyota/jp/mobility/frontier-research/
未来創生センターTwitter
https://twitter.com/TOYOTA_FRC
未来創生センターの採用情報
【新卒応募の方はこちらから】
①エントリー画面
https://toyota-saiyo.snar.jp/jobboard/detail.aspx?id=R91kDschOq0
②未来創生センターについて
https://www.toyota-recruit.com/saiyo/project/course/future_creation/
【キャリア応募の方はこちらから】
https://www.toyota-recruit.com/career/project/course/mirai.html
おすすめイベント
関連するイベント