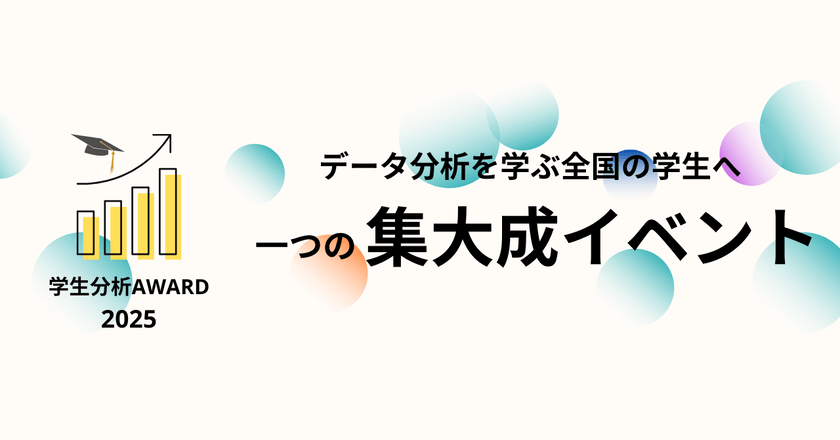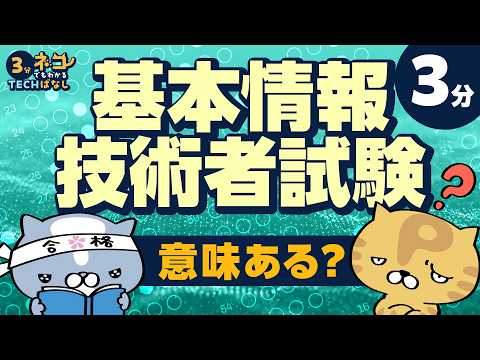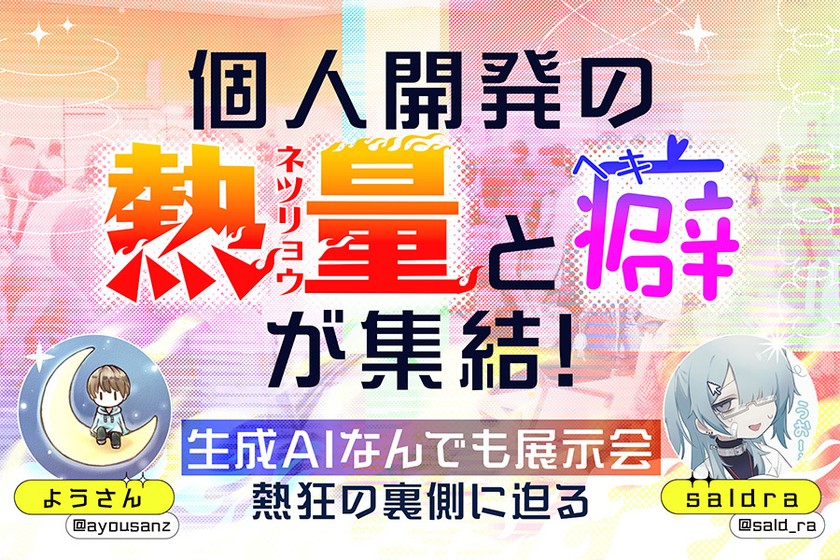TOYOTA×NISSAN×Hondaのソフトウェアエンジニアが語る「これからのモビリティの世界観と実現」に向けたソフトウェア戦略
AI、IoT、クラウド、5Gなどの最先端技術ソフトウェア技術が自動車においても活用されるようになり、モビリティの未来にも変革をもたらそうとしている。今回の「Japan Mobility Tech Day」では、業界を代表するトヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業が各社の描くモビリティの世界観と展望、ソフトウェア技術戦略について語った。アーカイブ動画
Autowareがもたらす「モビリティソフトウェア開発の未来」とは

株式会社ティアフォー 創業者 兼 CEO
The Autoware Foundation代表理事
東京大学大学院情報理工学系研究科 特任准教授 加藤 真平氏
最初に登壇したのは、Autowareの開発者であり、同OSを開発・展開するスタートアップ、ティアフォーのファウンダーでもある加藤真平氏だ。すでにグローバルでの利用が広まっているAutowareだが、国内でも浸透しつつある。
現在は各地の自治体関係者とコミュニケーションを取りながら、タクシーやバスといったさまざまな車両での運用における実証実験を繰り返している段階だという。小型ロボットやレースカーへの実装も視野に入れており、こちらも実証実験や24時間365日稼働する運用が始まっており、Autowareならびにティアフォーの役割や存在意義を次のように語った。
「すべて同じソフトウェア、プラットフォームという観点で利用、実装できるのがポイントです。だからこそOSSとして展開しており、民主化、誰でも使えることに意味があると考えていますし、事業のコアでもあります」(加藤氏)
自動運転やADASなど、各種最新技術やサービスの実装が進んでいる自動車だが、基本的な構成、アーキテクチャは大体同じだと加藤氏は言う。

その上で共通のソフトウェア、OSであるAutowareはどのような役割を担っているのか、次のように述べた。
「ハード・ソフトウェアすべてを自社、1社で開発するのは難しい。そこで途中までの段階の道具を提供するのがAutowareであり、山登りで五合目までを車で連れていくような役割です。そこから先のレイヤーは山登りで言うならば、五合目以降は自分の足、各社それぞれが開発していく流れとなるのです」(加藤氏)
加藤氏はOSSのため正確な利用数は分からないと前置きしながら、も20~30カ国、数千社までに利用は広まっていると、現在の利用状況を話した。

Autowareには物体や位置の検知、路上駐車の回避機能、車両制御といった自動運転に必要な基本性能が揃っているため、スクラッチでソフトウェア開発を行うことは、費用対効果の面から適さない。
だが、Autowareを活用することで、QCDにおけるクオリティやデリバリーに注力することができる、と加藤氏は補足する。また、基本的な機能は共通としながらも、さまざまなソフトウェアモジュールを再利用かつ組み合わせることで、スピーディにそれぞれの車両や利用用途に合った車両を開発できると続けた。

さらにAutowareは、運用におけるプロセスもDevOpsでワンストップで提供する。そのため開発者は、Autowareのソースコードをキャリブレーションすることで、最適なパラメータを見つけることができる。また、運用前のシミュレーションをWeb上で実施、管理することで、OTA(Over The Air)のデプロイや遠隔監視なども行える。

ティアフォーでは、OSやソフトウェアだけでなく、マシンビジョンカメラやミリ波レーダー、LiDARといったハードウェアも開発している。
「自動運転のレベル4に見合ったハードウェアはなかなかないので、こちらも自分たちで開発しています」(加藤氏)
さらには、シミュレーション機能も備える。自動車業界で一般的なHILSではなく、ここでもソフトウェアの技術を活用し、デジタルツインの仮想空間を構築。実際、西新宿のデジタルツイン空間を構築している。
東京にいながら、地方の自動運転車両を監視できる見守りシステムの開発にも着手しているという。
「実際に自動運転のオペレーションが始まると、故障で動かないなどの各種トラブルが想定されるため、必要なシステムだと考えています」(加藤氏)

見通しの悪い交差点に立つ電柱などにセンサーを設置することで、自動運転車がより安全に運行できる「スマートポール」にも着手。こちらもすでに実証実験を行っている。
ティアフォーは2023年の10月にレベル4の自動運転の認可を取得しており、「近いうちに実際にサービスインされる予定です」と、加藤氏は語る。その際にもデジタルツインのシミュレーション技術を活用することで、さまざまなユースケースがシミュレーション上で行えると補足。実際にバスの自動運転をシミュレーションしている様子も紹介した。

人材育成プログラムにも注力しており、レースカーを自動運転させるイベントなどを実施していることを紹介し、次のように述べてセッションを締めた。
「ソフトウェア人材にモビリティを動かす楽しさを知ってもらい、多くの方が自動車業界に興味を持ってもらいたい。現在はゴーカートですが、いずれはF1などでも行い業界を盛り上げていきたいと考えています」(加藤氏)
【TOYOTA】自動車業界におけるソフトウェア開発の魅力

トヨタ自動車株式会社
デジタルソフト開発センター フェロー 村田 賢一氏
続いて、トヨタ自動車の村田賢一氏が登壇した。以前は家電業界で情報家電やゲーム機などのアーキテクチャ開発に従事していたという村田氏、トヨタ自動車に入社してからはコネクティッド戦略策定推進などを経て、現在はデジタルソフト開発センターでフェローを務めている。
社会構造の変化ならびにCASEにより、モビリティ業界は100年に一度の大変革期にあると村田氏は指摘。「トヨタ自動車はビジネス優先ではなく、安全安心なモビリティ社会を実現したい。そのためにソフトウェア開発が必要だ」と、力強く述べる。

自動車業界におけるソフトウェア開発の魅力は、「担う領域がどんどん増えていること」だと村田氏は語る。
実際、さまざまな機能がECUにより電子制御されてきており、制御に必要なソースコード量も右肩上がりで増加。現在は数千万行ほどにも達していて、この先まだまだ伸びるという見解を示した。

自動車で活用されるソフトウェア技術は、車内・車外(In Car、Out Car)の制御・サービスと大別されている。車内では従来からある「動く」「止まる」「曲がる」といった制御系ソフトウェアに加え、現在はHMI(Human Machine Interface)、IVI(In-Vehicle Infotainment)と呼ばれるインフォテイメント系のシステムやサービスの需要が増加しているという。
「1社だけでソフトウェアを開発することはもはや不可能に近い。業界で団体を設立し、Linuxを組み込みとして利用するOSSを活用している状況です」(村田氏)

一方で上記スライド左のOut CarではいわゆるMaaSと呼ばれる、各種モビリティサービスの根幹となるWeb系ソフトウェア開発の技術が活用されている。
データセンターにデータを集めるための通信プロトコルの制御技術や、得たデータをクラウドで制御・管理する技術などが必要で、特にOut Carにおいてはセキュリティを担保する必要もあることから、「Trusted Computing Group(TCG)と呼ばれる業界団体に加盟するなど、技術の研鑽や信頼性向上に努めている」という。
村田氏は、近年の自動車業界におけるキーワードである「ソフトウェアデファインドビークル(SDV)についても「ソフトウェアデファインドビークルはどんなクルマを開発するということではなく、どのようにクルマを作るのかという、“つくり方”を定義したものです」と、説明する。
従来のようにハードウェアを定義してからソフトウェアを開発するような流れではなく、ソフトウェアを定義してからハードウェアを設計することだと続けた。また、実現に向けては以下スライド右側のイラストのように、ソフトウェアとハードウェアをパソコンのように切り分けることが必要だと補足した。

このようなソフトウェアデファインドビークルでのモビリティ開発では、データ分析が重要であり、データをマネジメントし、コーディネートするVehicle OSが必要になってくる。
「走る」「止まる」「曲がる」といった運転に必要な制御から、コックピット、インフォテイメントのような利便機能、さらには交通系、エネルギー系、決済系など、各種社会サービスのプラットフォームと繋がる必要があるからだ。そして次のように話した。
「このようなクルマづくりで重要なのは、個人の要望に応じるなどカスタマイズが必要であり、『クルマの知能化』が重要だと言われています」(村田氏)

村田氏は最後に、In Car、Out Carそれぞれにおけるソフトウェア開発の具体的な事例を示し、これらのプロジェクト開発をまとめるPM人材も活躍していることを紹介。「ソフトウェア開発でクルマの未来を変えていこう!」と熱いメッセージを投げかけ、セッションを締めた。


【日産自動車】モビリティの未来を切り拓くソフトウェアデファインドビークル

日産自動車株式会社
コネクティドカー&サービス技術開発本部
コネクティドカーオフボード開発&オペレーション部 部長 村松 寿郎氏
続いて登壇したのは、日産自動車の村松寿郎氏だ。村松氏が入社直後に携わった業務は、衝突防止レーダーの研究である。2000年の米国赴任をきかっけに、車載コンピュータやオートモーティブ、コネクテッドなど、ソフトウェア領域にも携わる。
現在はコネクテッドカー&サービスのクラウドシステムやモバイルアプリの開発及びオペレーションを手がけている。
創業から90周年を迎える日産自動車では、「人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける」というコーポレートパーパスを掲げている。その実現には技術が重要だと、村松氏は語る。
具体的には「電動化」「自動化」「コネクテッド」と3つの技術を束ねることで、未来のクルマ、インテリジェントモビリティの開発を実現していく。実現に向けて重要となるキーワードが「ソフトウェアデファインドビークル」だ。

昨今の自動車業界のトレンド技術やサービスを表したCASEというワードがある。まさに日産自動車のインテリジェントモビリティとも重なるが、「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動化)」「Shared(シェアリング)「Electric(電動化)」の頭文字を取ったワードである。だが村松氏は、次のような見解を述べた。
「Sに関してはソフトウェアデファインドビークルのSと言ってもいいほど、最近ホットなテーマになっていると感じています」(村松氏)
村松氏は、ソフトウェアデファインドビークルに関してこう解説した。
「ソフトウェアデファインドビークルとは、ソフトウェアが定義する、ソフトウェアで定義された車両と直訳でき、クルマの性能や機能が定義対象となります」(村松氏)

しかし、クルマの機能や性能はすでにソフトウェアで制御している。そのため、OTAによるソフトウェアのアップデートによる機能・性能が再定義でき、再定義しやすいクルマが、ソフトウェアデファインドビークルの本当の意味ではないかと、村松氏は見解を述べる。
村松氏は車載ソフトウェアの規模増大を、トヨタ自動車の村田氏と同じくソースコードの行数で説明。ボーイング787飛行機は650万行、最新鋭の戦闘機でも2500万~3000万行と改めて車載ソフトウェアの規模の多さを強調し、「今後は億行になっていくと思います」との見解を示した。

当然プロセッサーの進化も必要となっており、実際に性能が向上している。村松氏はグラフを示すとともに、処理性能を示す指標OPS(Operations Per Second)の単位が、以前はメガがGiga(ギガ)であったのがTera(テラ)にまでなっていると述べた。

進化した機能の一例も紹介された。コックピットでは、以前はナビゲーションシステムだけであったのが、マルチメディア機能を搭載するようになっている。メーターもアナログであったのが、デジタルディスプレイに変わった。
ナビゲーションシステムにおいては、音声で目的へのルートを示すように、自然言語理解(Natural Language Understanding/NLU)といった技術も搭載されており、EVであれば蓄電・充電情報も加味した情報が提供される。

車載OSの変化も語られた。最近はAndroidとLinuxが半々であり、リアルタイムOSから汎用OSにシフトしつつあるという。

昨今の自動運転は高度化が進んでおり、以下スライドが示すようにクルマに搭載されたカメラやLiDARなどで360度センシングする。さらには前のクルマとの距離を測ることで自動制御したり、レーンチェンジなども自動で行ったりする機能が搭載されるなど、非常に多彩なタスクを実行している。

自動化とはそもそもどういうことなのか、村松氏はこう語る。
「以下スライドの上側は人が運転する流れを示したものであり、下部が自動運転での流れとなります。人が持つ感覚器官は各種センサー類が担いますが、青色で塗られた部分はソフトウェアの技術で行っている領域。そして、自動化の元となるのがデータです」(村松氏)

機能が進化かつ多様化しているため、車載アーキテクチャの数やデータ転送のボリュームも増えていった。実際、2017年と2020年の車両で比べるとECUの数は2倍、CANの信号数は2.5倍に増加している。
ECUにおいては、それぞれのドメインをコントロールするようなアーキテクチャに変化、統合されており、このような流れはこの先も続くだろうと、村松氏は見解を述べた。
OTAについても解説された。パソコンやスマホでは電源オンのときのみアップデートを行えるが、クルマの場合はあくまで新しいバージョンのダウンロードまでを走行中に行う。そして電源がオフになった瞬間に、アップロードを実行するという違いがあるという。
最後に村松氏は、今後のソフトウェアデファインドビークルの世界観を次のように述べ、セッションを締めた。
「従来のように開発者が集めたデータからではなく、実際に走っているクルマから得たデータがクラウドにアップされる。そのデータをもとに、新たなソフトウェアを開発し、再びクルマにダウンロードしてアップデートする。そのような開発が可能になると考えています」(村松氏)

【本田技研工業】Hondaの描くソフトウェアデファインド

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター
ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 統括部長 四竈 真人氏
最後のセッションは、本田技研工業の四竈真人氏が登壇した。四竈氏のキャリアはエンジン開発から始まり、ハイブリッド制御開発などに従事する。2015年に自動運転のプロジェクトリーダーに抜擢され、以降はADASの研究などに従事。現在はソフトウェアに関する全般業務を担う部門の統括部長を務める。
Hondaは四輪自動車、二輪自動車、パワープロダクツ、小型ジェット機など、さまざまなパワーユニット製品を世に送り出しており、その数は年間2800万と世界一を誇る。
四竈氏は、これまでのハードウェアデファインドの世界では難しかったパワーユニット製品が、ソフトウェアデファインドモビリティの世界でつなぐことができるようになってきたと語る。
「本当の意味でそれぞれのパワーユニットをつなぎ、シナジーが出せる大チャンスな時代が到来しています。具体的には、移動効率の最適化や誰一人事故に遭わない世界観を実現しようと考えています」(四竈氏)

Hondaが描くソフトウェアデファインドとは、クルマから得たデータを素早く分析し、新たなソフトウェアや機能を開発し、再びクルマにフィードバックする。そのループ、サイクルを繰り返すことだ。
このループを実現するためのアーキテクチャこそ、ソフトウェアデファインドビークルであり、具体的にはソフトウェアプラットフォームならびに、機能ごとのECUを集約するE&Eアーキテクチャだと、四竈氏は述べた。

ソフトウェアデファインドビークルが実現した未来では、どのようなインパクトがあるのか。まずは人に対して、ソフトウェアはOTAの技術を活用することで、ハードウェアと異なり、変化することが可能になる。
その結果、その時々に楽しみたいことを、各々が体験できるようになる。自動運転が実現すれば、運転に要していた時間から開放されるだけでなく、移動中の社内を誰でも自由に動けるようにもなる。

続いては社会へのインパクトである。カーボンニュートラルへの貢献や交通事故死ゼロなど、これらはHondaが2050年までに実現を掲げている目標でもある。
渋滞軽減、新しいビジネスモデルの創出、さまざまな人の社会参加など、ソフトウェアデファインドビークルの浸透により、「私たちの社会生活そのものが変化し、新たな価値が枚挙にいとまなく生まれていくようになるだろう」と、四竈氏は語る。
四竈氏は自動車業界へのインパクトも示した。まずは業界構造がこれまでの自動車メーカー(OEM)とサプライヤーという関係性から、モビリティサービスプロバイダがさまざまな価値を束ねていくように変わる。
バリューチェーンにおいては、これまでは単に車両を提供するだけだったビジネスモデルから、エンタメ、シェアリング、充電などのさまざまなサービスを、さまざまなプレイヤーが提供するようになる。
品質とスピードのバランスでは、品質とスピードを両立するため、これまでは設計や開発にじっくりと時間をかけて世に送り出していた流れから、プロトタイピングをスピーディに世に送り出し、フィードバックをうけて改善していくような流れになるだろうという見解を述べた。

自動車開発へのインパクトも大きい。四竈氏は大きく4つのインパクトと変化を示した。1つ目は、顧客と企業の関係性だ。ソフトウェアデファインドビークルではOTAによるソフトウェアのアップデートがあるため、販売後も長きにわたり関係性が続くようになる。
2つ目は製品・サービスの変化であり、どちらかというと企業起点でのプロダクトの提供から顧客起点に変わる。
3つ目は開発スコープである。ローンチに向けた「終わりのある開発」からソフトウェアのアップデートにより「終わりのない開発」に変化する。日々、ユーザーが求めるニーズや機能を開発し続ける終わりのない開発に合わせて、開発の仕組みやプロセス、組織などを見直す必要があり、これは大きな変化である。
そして4つ目はハードウェアをソフトウェアに合わせるような開発に変わっていくと、四竈氏は次のように述べた。
「従来であればコストを抑えてハードウェアを開発することが求められており、そこが競争力でもありました。しかし、ソフトウェアデファインドビークルの開発では、発売後のソフトウェアのアップデートを踏まえ、柔軟性を持ってハードウェアを設計しておく必要があります」(四竈氏)

四竈氏は今年のCESで発表されたコンセプトカーと3つのコンセプトを紹介。その1つが「賢い」であり、「まさにソフトウェアの出番であり、ソフトウェアデファインドビークルを開発していくことを宣言しています」と述べた。
ソフトウェアデファインドビークルを開発するには、これまで述べてきたように開発サイクルの高速化、さらなる柔軟性、品質の担保などが求められるため、「ソフトウェア開発やAI、IT技術も手の内化する必要がある」と四竈は語る。
ソフトウェアデファインドビークルは、開発を実行したらそれで終わりではなく、その先にソフトウェアデファインドビークルで何をするかが大事だと四竈氏は強調する。その際にはさまざまな基礎技術や戦術をクロスドメインすること、携わる人のマインドを変化することが重要だと続けた。

そして最後に一枚のスライドを見せ、次のように述べセッションを締めた。
「Hondaの最初のプロダクトは、本田宗一郎さんが奥さまに楽しんでもらいたいと思って自転車にエンジンをつけたものです。このような世のため人のための純粋な気持ちこそが会社の出発点であり、この気持ちこそ我々が変わらず持ち続けている思いでもあります」(四竈氏)
【TOYOTA×NISSAN×Hondaトークセッション】ソフトウェアの楽しさとは?
ここからは加藤氏がモデレーターとなり、登壇者全員によるトークセッションが行われた。
ソフトウェアの楽しさとは?
加藤:ソフトウェアの楽しさは、人により概念が変わると思います。皆さんはそれぞれどのように捉えているかを、お聞かせください。
村田:チャレンジ的なところが楽しいと捉えています。ソフトウェアといってもクルマにおいては、いろいろ種類があります。例えば、8ビットマイコンで、アクチュエーターを動かすようなことから、64ビット級のSoCマルチコアで、IOもたくさんついていて、GPUのアクセラレータも搭載しているマシーンを使いこなす場合もあるからです。
組み込みソフトウェアでありながら、パソコンでやっているような体験ができるのも、面白いと感じています。私は以前家電業界にいたのですが、自動車業界であれば組み込みの技術に加え、品質や安全性がさらに求められます。
IT系のソフトウェア知識だけではなかなか難しい、組み込みソフトウェアは日本の伝統工芸的な面もありますから、やりがいや誇りにもなっているとともに、やっぱり楽しみでもありますね。
村松:自分たちで組んだソフトウェアがクルマというハードウェアに搭載され、実際に動く。そこがコアな面白みとしてあります。また、クルマにおけるソフトウェア開発費は年々増加していて、現在は全体のコストの約半数を占めており、ソフトウェア開発者の重責が高くなってもいます。
四竈:ハードウェアとは異なり、簡単に動作を試すことができ、実際に動かすことができる点が面白いと思っています。ソフトウェアであれば、間違っていた場合は間違った動きをし、正しければ正しい動きをしてくれます。
Webやクラウドエンジニアなど、組み込みソフトウェア以外の活躍
加藤:極論を言えば、ソフトウェアは1分後に、新しいバージョンに変えることもできますからね。ところで、クルマ業界は組み込みソフトウェアとのイメージがありますが、Webやクラウド系のソフトウェアエンジニアの活躍状況は、需要も含めていかがでしょう?
村松:当社ではコネクテッドカー向けのクラウドシステムの開発と運用、モバイルアプリケーションの同じく開発運用といった業務があり、モバイルアプリ開発においてはほぼ100%内製化しています。
クラウド関連では大きく分けて2つのインスタンスがあり、1つは内製化しており、このような業務や領域にIT業界からの人材などを迎え入れ、内製開発しているのが実態です。
加藤:内製開発以外で委託する場合、委託先は自動車業界以外もあるのですか?また、内製開発においては、バック・フロントエンドエンジニアなど、いわゆるWeb系エンジニアも活躍している状況なのでしょうか?
四竈:ありますね。実際、エンジニアリング会社や海外の企業などもあると思います。
村松:従来のトラディショナルなサプライヤーとは異なる先にもお願いしますね。
村田:大手町にある当社のオフィスでも、ソフトウェアエンジニアがバリバリコードを書いています。メンバーはプロパーもいますが、委託先のソフトウェア会社の方もいますし、従来の部品仕入れ先の会社からの方もいたりと、さまざまです。
内製化率においてはコネクティッド系の領域で半分以上となっており、コンテナベースのクラウドネイティブな環境で、毎日のようにデプロイしているような状況です。
加藤:AIや機械学習に強いエンジニアについてはどうですか。
村田:以前より増えていますし、実際に活躍しています。ただ、まだまだ足りないというのが正直なところです。データサイエンティストと呼ばれる、学習やモデル作成に強いエンジニアだけでなく、データエンジニアがいてこそだと思うので、データスキルを備えたエンジニアも同様です。
さらには、ビジネスではどうしてもQCDが重要です。研究室レベルの知識や技術ではなく、例えば機械系の知識も備えていて、メカ系のエンジニアともコミュニケーションが取れるような人材ですね。そのようなエンジニアも、増えてきている印象を持っています。
村松:もちろん求めていますし、実際に最近は学生時代に機械学習を学んだ新卒のメンバーなども、機械学習関連の業務に就きたいと希望して入社してくるケースも増えてきました。ただそれだけではボリュームが足りないので、外部の技術も活用する。現在はハイブリッド型になっている状況です。
四竈:当社ももちろん求めています。ただ持っているAIスキルをクルマに適用する際にはさまざまな制約があるので、そのような制約も乗り越えることができる人。あるいは、学ぶことで乗り越えることのできるスキルを身につけることができる人。そういった人材が欲しいですね。
加藤:業界的には、パソコンで動いている世界を組み込みの世界に落とし込むことで、クルマが動くことになる。そして、それを実現できるエンジニアが必要だということですね。求めるエンジニア像のイメージを、改めて聞かせてもらえますか。
四竈:先ほど議論があったように、AIに特化しているなど、専門領域に強い人材は当然必要です。いわゆるエキスパート人材です。一方で、組み込みではシステムレイヤーの観点なども必要となってくるため、システム設計スキルも求められます。
ただ、両者はタイプが異なるため、結論としては多様な人材が必要であり、優先度とかはなく、様々なレイヤーにおける様々なタイプの人材が欲しいですね。
村松:クラウド領域であれば、フルスタックエンジニアが必要だと考えています。実際、さまざまな場面で活躍するからです。ただプログラミングができるだけでなく、システムレベルまで組み込むことができる。さらに、そのシステムでクルマはどう動くのか。そこまで思いを馳せられるエンジニアが必要ですね。
村田:当社も多領域のレイヤーの仕事があるので、さまざまなエンジニアを求めています。自分にプログラムを書かせたら、パイプラインは止まらないといった気概を持った方がいいですね。個人的には思ったように動かなかった際に、ロジアナ(ロジック・アナライザ)を持ってきて調べるようなエンジニアが好きです。
村松:要件定義をしっかりと理解した上で、プログラミングスキルも備えたソフトウェアエンジニアが欲しいですよね。
村田:これは実際に最近の傾向でもありますが、プロトタイプをすぐに作ってくれる。修正対応も速い。このようなエンジニアがいると助かりますし、そのようなエンジニアに活躍してほしいとも思っています。
四竈:まさしくハードウェアとの違い、ソフトウェアの本質ですからね。
村田:もちろん我々は自動車業界なので、その上で品質もしっかり担保すると。
加藤:仕様書を最初に書くことはIT業界でも同じだと思いますが、自動車業界の場合は携わるメンバーが多いため、なかなか変えることが難しいですよね。
一方、一般的なソフトウェア開発は人数がそれほど多くないので、いわゆるアジャイルですぐに変えることができています。このような文化について、自動車業界はどのように捉えていますか。
村田:現在はハードウェアとソフトウェアの分離開発が進んでいるので、アジャイル開発は大分実践されていますし、手の内開発も同じく浸透するなど、以前と比べるとかなり変わったと思います。
村松:ただし、クルマという巨大なシステムにインテグレートする必要があるため、根幹の仕様はやはり必要だと思います。一方で、根幹に関わらないような一部の機能は、アジャイル開発で進める。現在はハイブリッド型になっていると捉えています。
ミリタリースペック以上のものをコンシューマイプライスで開発する
加藤:他業界のエンジニアが自動車業界に入った際のインセンティブは何だと思いますか。
村田:やっぱりモノが動くことですよね。ワクワクすると同時に責任感も芽生えますが、やはり大きなやりがいだと思います。
村松:クルマのソースコードが多いのは不要なものが多いという意見もあります。もちろん中にはムダなもの、リファクタリングが必要なソースコードもあるでしょう。一方で、クルマは空とは異なり、認識物が多い道路を走っています。
そのような状況下でミリタリースペック以上の製品を、コンシューマプライスで開発している。とても大変な状況ではありますが、だからこそ、そこにソフトウェア開発の醍醐味があると思っています。
四竈:実際、過去にHondaでは無人飛行機自動の検証ロジックを検討しましたが、クルマの自動運転の方が難しいという結果でしたね。
加藤:私は大学で学生とコミュニケーションしているのですが、IT業界は開発したものがすぐに世に出るからという理由で、就職先として選ぶ学生が多いと感じています。対して、クルマの開発サイクルは長いですよね。実際にものが動くというやりがいは、どれくらいのスパンで感じることができるでしょうか。
四竈:車の挙動に関わるものが市場に出るまでという観点だと、現状はかなりかかっていますが、アーキテクチャをうまく設計すること、検証を自動でまわすなどの仕組みとセットで実現しようとしている。このような世界が実現すれば1カ月、さらにはものによっては2週間ほどで実現できるかもしれません。もちろん認可等の課題もあるので、感覚としては長いものでも半年くらいでないと厳しいですかね。まさに今、我々トライしていることでもあります。
村松:クラウドやモバイルアプリ領域では、毎月アップデートしています。一方で、クルマに近づくにつれて、どうしても長くなる傾向にあります。国交省の許可も必要になってくるからです。
村田:ブレーキの制御ソフトウェアをチューンナップしようというワークショップを実施したことがあります。実際にチューンナップしたクルマをその場のテストコースで走らせるのですが、ビフォアアフターを1日で体験できました。
加藤:最後にメッセージをお願いします
村田:後世に名前が残るようなプロダクトに携わることもできますので、自分は優秀なソフトウェアエンジニアだという気概をお持ちの方に、ぜひとも自動車業界に加わっていただきたいと思います。
村松:自動車業界はグローバルです。自分が開発したソフトウェアを搭載したクルマが世界中で走り回っている。そのようなイメージを持ちながらチャレンジできる人材にぜひ来ていただきたいと思います。
四竈:さまざまなタイプや領域の仕事が、自動車開発にはあります。それらの仕事の融合こそが、エンジニアの成長や価値に寄与すると思いますし、実際、自分はITエンジニアだから、クラウドエンジニアだからといった考え方も変わってきています。モビリティ業界での活躍の場が十分用意されていて、可能性は広がっていくと思います。
トヨタ自動車株式会社
https://global.toyota/
トヨタ自動車の採用情報
https://global.toyota/jp/careers/
日産自動車株式会社
https://www.nissan.co.jp/
日産自動車のキャリア採用情報
https://www.nissan.co.jp/RECRUIT/
本田技研工業株式会社
https://www.honda.co.jp/
本田技研工業のキャリア採用情報
https://www.honda-jobs.com/
おすすめイベント
関連するイベント