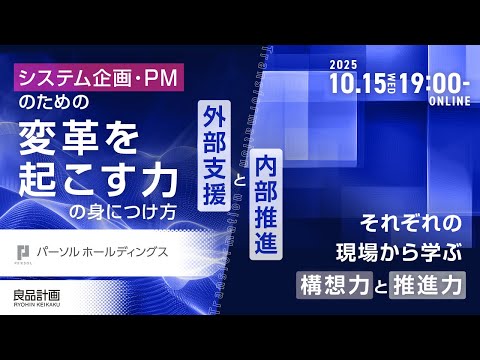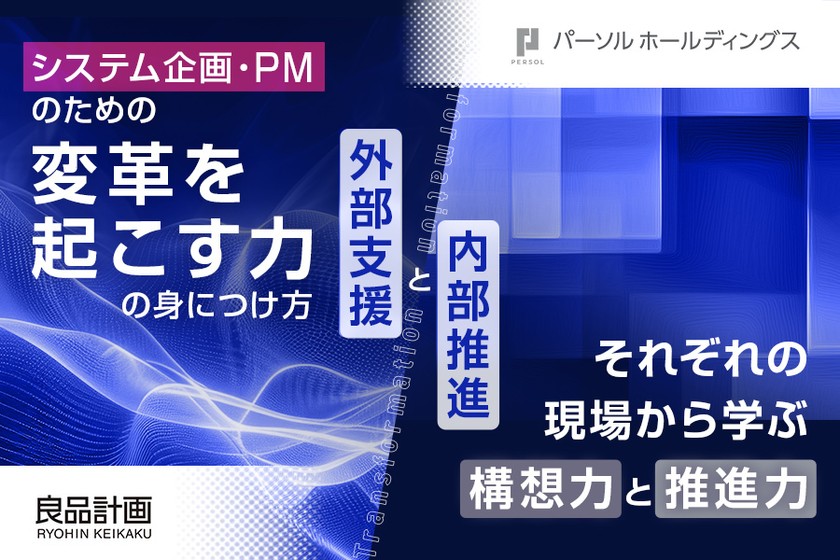ITエンジニア1,600人+他職種900人調査から考える ─ニューノーマル時代に活躍できる組織のつくり方とは?
パーソル総合研究所は、ITエンジニア1600名を対象にエンジニアの組織戦略やエンジニアの働き方に関する調査を実施した。その調査結果をもとに、AIスタートアップのエクサウィザーズ代表の石山洸氏、技術と経営の問題解決を手がけるレクター代表であり、日本CTO協会代表理事でもある松岡剛志氏、パーソルホールディングスCIOの古川昌幸氏、パーソル総研の小林祐児氏がトークセンションから、ニューノーマル時代にITエンジニアが活躍できる組織のつくり方を考える。(プロフィール)

株式会社パーソル総合研究所
上席主任研究員 小林 祐児氏
上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年入社。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・中高年のキャリア・パート・アルバイトのマネジメントなど多岐。

パーソルホールディングス株式会社
執行役員CIO 古川 昌幸氏
1986年野村総合研究所(NRI:当時は野村コンピュータシステム)に入社。大手証券会社の基幹システムのグランドデザインを担当し、その経験を踏まえてシステムコンサルタントに。NRI主席コンサルタントとしてさまざまな企業に対して、経営戦略を実現するためのITの活用方法について提言活動を行う一方、食品大手企業に出向して情報企画部長を務めたこともある。経営企画部長として、自社の経営戦略策定にも携わってきた。2020年7月にパーソルホールディングスに移り、執行役員CIOに就任。

株式会社レクター
代表取締役 松岡 剛志氏
ヤフー株式会社の新卒第一期生エンジニアとして複数プロダクトやセキュリティに関わる。その後、株式会社ミクシィで複数のプロダクトを作成の後、取締役CTO兼人事部長へ。B2Bスタートアップ1社を経て、技術と経営の課題解決を行う株式会社レクター をCTO経験者4名で設立し、代表取締役に就任。2018年、株式会社うるる 社外取締役に就任。2019年9月より「日本を世界最高水準の技術力国家にする」ことを目標とした一般社団法人日本 CTO協会を設立し、代表理事を務める。経済産業省 Society 5.0時代 デジタル・ガバナンス検討会委員。

株式会社エクサウィザーズ
代表取締役社長 石山 洸氏
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻修士課程修了。2006年4月、株式会社リクルートホールディングスに入社。同社のデジタル化を推進した後、新規事業提案制度での提案を契機に新会社を設立。事業を3年で成長フェーズにのせ売却した経験を経て、2014年4月、メディアテクノロジーラボ所長に就任。2015年4月、リクルートのAI研究所であるRecruit Institute of Technologyを設立し、初代所長に就任。2017年3月、デジタルセンセーション株式会社取締役COOに就任。2017年10月の合併を機に、現職就任。静岡大学客員教授、東京大学政策ビジョン研究センター客員准教授。
【調査概要】ITエンジニアの採用・定着・仕事・キャリア観を他職種と比較
まずは、パーソル総合研究所の小林祐児氏が登壇し、パーソル総合研究所が実施した「ITエンジニアの人的資源管理に関する定量調査」の目的・考察について発表を行った。調査の目的は、なかなか採用ができない、かつすぐ辞めてしまう「ITエンジニア人材の組織マネジメントをどうするか」である。
ITエンジニアの採用・定着・仕事観・キャリア構築感の実態や特徴を、他職種との比較を通して明らかにすべく、ITエンジニア1600名(内製38.4%、客先常駐なし受託型28.9%、客先常駐あり受託型29.8%、その他2.9%)、他職種900名の計2500名を対象に実施された。

【賃金】ITエンジニアは他職種よりも年収ギャップを感じている
ITエンジニアにおいては、希望年収が763.7万円に対し、現状の年収は613.6万円と150.1万円のギャップが見られた。一方、その他職種では希望年収が769.4万円に対し、現状は約628.0万円と、141.4万円のギャップがあった。
どちらの職種でも理想と現実のギャップがあることは想定していたが、「ITエンジニアの方が他職種よりも年収ギャップが大きいこと、賃金に対して敏感である」傾向がみられる。
ITエンジニアは他職種とは異なり、年収ギャップが大きくなるにつれ、視線が外に向くようになる。つまり、転職意向が高まることもわかった。一方、他職種の場合は管理職意向が下がる傾向は見られたが、それによって転職意向が高まることはないようだ。

【転職】社内外の相対的なポジショニングに敏感である
転職意向について比較すると、ITエンジニアと他職種の間で意識の違いは、それほどないようだ。そこで、組織に対する疑念や批判的な考えや感情を抱く「組織シニシズム」に着目してみた。
すると、次のような結果が得られた。ITエンジニアは社内外どちらにおいても、以下のような働く環境も含めた、社内外の相対的なポジションが心地よくないと感じたときに、組織シニシズムを抱くことがわかった。
・無理難題を押しつけられる
・ビジネスサイドに比べ、ポジションが弱い
・クライアント先で営業やビジネスサイドが守ってくれない
・残業時間が長い

さらにITエンジニアが組織シニシズムを感じるのは、いわゆる老舗企業や非IT企業で多い傾向も見られた。

【考察】ITエンジニアをメンバーシップ型に迎え入れることが解決の基軸案
今回の調査結果から、ITエンジニアは現在、内部市場と外部市場の中間に位置していると考察している。内部市場とは、正規で長期雇用を行うメンバーシップ型の企業を指す。 一方、外部市場はアメリカ型、欲しい人材を相応の給与を支払うことで獲得する、いわゆる「buy」の世界であり、対して内部市場は「make」の世界と言える。

では今回のテーマである、ITエンジニアが活躍できる組織にするにはどうしたらよいのか。第一次世界大戦前後の雇用環境が参考になる。
実は今から100年以上前にも、ITではなく機械エンジニアとの違いはあったが、エンジニアと非エンジニアとの間で、労働市場が分かれていた時代があった。内部市場は大卒のエリート、いわゆるホワイトカラーである。一方、外部市場は渡り職工と呼ばれるエンジニアで、まさに字のごとく現場や工場を渡り歩く、流動的な働き方をしていた。
このような状況がどう変わっていったのか。ここからは重要なポイントとなるのだが、両者を「混ぜた」のだ。具体的には、外部市場のエンジニアを内部市場側に、つまり渡り職工を長期雇用し、ジョブローテーションを行い、エンジニア以外の仕事も担当させるなど、メンバーシップ型雇用にシフトしていった。いわゆる日本の老舗企業の組織体制であり、エンジニア、非エンジニアどちらも共通の目的に向かい、協力するとの組織文化が醸成されていったのである。
そんな折、第一次世界大戦という共通のパーパスが勃発する。その結果、内部市場は充実し、その後の経済の隆盛ならびに安定につながっていく。この「混ぜる」を、現在中途半端な位置付けにいるITエンジニアに行うことが、ひとつの解決案であると同時に、基本路線でもあると小林氏は強調する。
逆に、外部市場はどうか。ジョブ型の人事制度にメンバーシップシップ型を取り込むのは、全従業員がエンジニアなど、よほど先端のグローバル企業でない限り、従来のメンバーシップ型人材の意識改革の点などから、難しいと考えていという。

【トークセッション】エンジニアが活躍できる組織とDX戦略のつくり方
ここからは石山洸氏がモデレーターとなり、4名によるトークセションが行われた。

石山:第一次世界大戦の職工身分制度から今のIT業界を考察するという発想は、さすが社会学者の小林さんならではだと感心しました。非常に興味深かったです。実際、台湾のデジタル担当大臣のオードリー・タン氏は、まさに小林さんが発言された「混ぜる」と「目指す(パーパス)」を実施し、新型コロナウイルスを封じ込めましたからね。
私はエンジニアであり、マネジメントする立場でもあります。松岡さんはエンジニアど真ん中。パーソルの古川さんは現場でDXを進めている責任者。そして、社会学者の小林さん。本日はこのような多様なメンバーで、エンジニアが活躍できる組織のつくり方ならびに、その先にあるDXも含めた経営戦略の課題解決について、考えていきたいと思います。
まずは松岡さん、CTO協会で出されている本日のテーマの回答に近いガイドライン「DX Criteria」について、ご紹介をお願いします。
松岡:DX Criteriaはその名の通り、DXの推進状況を把握するための「基準」です。各社が自己診断を通して現状を把握し、指針を立てたり、ベンチマークした企業との違いを数値で把握したりすることが可能となります。このDX Criteriaでは「2つのDX」が必要不可欠だと定義しています。ひとつはいわゆる「企業のデジタル化(Digital Transformation)」、デジタル技術を用いてどれだけビジネスを変革するか。もう一つは「Developer Experience(開発者体験)」で、技術者がスムーズに価値創造に取り組める環境・体験(文化・組織・システム)が整備されているかです。
DX Criteriaでは次の5つをポイントとしており、全部で320の質問があり、「はい/いいえ」で答えていくことで、エンジニアを受け入れやすく、超高速な事業仮説検証能力を得られる環境であるかが判断できます。

石山:すぐに使えそうなガイドラインですね。実際、使う場合にはどうしたらいいですか。
松岡:GitHubで公開していますので、誰でも無料でご使用いただけます。ビジネスでも活用していただけたらと思っており、実際に数社からDX Criteriaを軸とした診断ツールを作成されたなど、お話を伺っています。
石山:パーソルではどのようなDXを、特に、Developer Experienceを高めるために心がけていますか。
古川:今まさに取り組んでいる最中でして、心理的安全性を担保することが重要だと考えています。具体的には「壁打ち」です。悩みを抱えている若手や中堅メンバーに、上司や先輩がその悩みを、まさに壁打ちのように聞いたり相談に乗っていて、コーチングに近いマネジメントとも言えます。
松岡:DX Criteriaは5つのテーマ、8つのカテゴリから構成されていますが、項目のひとつにチームがあります。心理的安全性もカテゴリとして設けてあり、チェックリストに答えることで現状の目安となります。
たとえば、1on1をやっているか、メンバーの行動に感謝しているか、などです。心理的安全性は論文でも多く登場しますし、グーグルでも意識しているなど、キーファクターであり重要なトピックだと思います。
石山:当社でも毎クオーターチェックしていますが、心理的安全性が高まると業績がアップするとの結果が実際に出ていますし、グローバルの調査を見ても同様ですよね。

いかに「混ぜる」か──共通のプロトコルを作る
石山:エンジニアと非エンジニア、具体的にはどのように混ぜる、コミュニケーションするべきでしょうか。
古川:まず大事なことは、事業部門とIT部門が委託・受注と上下関係になっている状態では、コミュニケーションは発展しません。非エンジニアとしては、専門用語が分からないなどの問題もありますから、共通のプロトコルを早く見つけるといいと思います。たとえば当社では、Teamsで両者がコミュニケーションしていることもあり、長い文章ではなく、チャットでやり取りすることで、コミュニケーションを深めようとしています。
石山:実際に混ざる、融合するものなのか。それとも分断もあり得るのでしょうか。
松岡:両方あるでしょう。ただし業種によって異なり、BtoBでは分断、BtoCでは融合するケースが多いように思います。融合としては「フィーチャーチーム」という概念が最近注目されています。従来の○○部門というコンポーネントごとのチームではなく、機能に対して職能を持っている人材が横断して集まるチームです。
どのような商品やサービスが当たるか不確実な昨今では、企業が生き残るためには、従来の受注型からコラボレーション型に変わり、スピード感を持って繰り返しトライすることが必要です。
ただし、このような概念は特に新しいわけではありません。経営学者の野中郁次郎先生が1990年代に提唱されていた「新しい企画やイノベーションを生むには、色々な職能の人が大部屋に集まり、コミュニケーションすることが重要」との考えと同じだからです。
このようなトレンドが、今まさにソフトウェア業界でも起きており、だからこそアジャイルやフィーチャーチームといった横断が注目されているのだと思います。
石山:実際、当社でも介護士とエンジニアが一緒に社会課題を解決するようなワークがあります。パーソルではどうでしょうか。
古川:BtoB、BtoCどちらのサービスも展開していますが、特にサービスライン増やす業務では分断しやすい傾向にありますが、私としては融合型を目指したいと考えています。
小林:テレワークに関する調査で、興味深い結果があります。活躍しているチームのマネジャーの特徴を分析すると、他部門や他職種との調整がうまい、ということです。実はオフライン、リアルな職場では偶発的な形で、他部門同士のコミュニケーションがありました。他部門とのコミュニケーションや利害調整をオンラインでも意図的に行うことで、パフォーマンスが高まると考察できます。
100%は目指すが、75%の達成で良しとする
石山:エンジニアにとって働きやすい環境について、長期化するテレワーク環境の整備なども踏まえ、行っている施策やビジョンがあればお聞きたいしたいです。
古川:アジャイルスクラム型のチームを増やしていることもあり、以前のように100%の成果を出すことが難しくなってきました。しかしそこで批判せずに「75%の達成、凄い!」とポジティブに評価するようにしています。
加えて、個人が自発的に学ぶことが重要だと考えており、実現できる機会や環境を整備・提供しています。具体的には、社外に出ての学びの機会創出などです。そうして学びで実行してみたいことが思いついたら、アンラーニング(学びほぐし)する。現状持っている3つの何かを捨て、身軽になってから飛び込む。このような意識や文化をパーソルでは大切にしています。
松岡:75%で良いとの取り組みは、とても素晴らしいと思います。最近注目されているフレームワーク「OKR(※)」の目標設定においても、高い目標を設定し、結果として7割が達成できる状況をつくることは、モチベーションの理論としても優秀であるとされています。
また先ほど2つのDXでお話しさせていただいた、エンジニアにとって働きやすい環境「開発者体験(Developer eXperience)」について、この数値が高い企業は低い企業と比較して、KPI達成率が2倍程度高いことがDORAのレポートでも報告されています。
石山:パーソルではOKRは導入しているのですか?
古川:似たような意識や発想での取り組みの検討も一部進めておりますが、現状導入はしていません。
小林:MBO(※)もそうですが、重要なのはOKRのようないわゆる流行り言葉ではなく、目標を公開することだと思っています。上司であれば、自分の目標を明示した上で、部下に指示を出すのが当たり前のようにも思えますが、実際には多くの職場で部下は上司の目標を知らないまま働いている。また他部門のマネジャーの目標を知ることで、より他部門間の調整や協力がスムーズになれば、両者にとって喜ばしい結果となるでしょう。
※OKR(Objectives and Key Results)、MBO(Management by Objectives):目標の設定・管理方法
グループではなくチームをつくることが重要
石山:内製化はどこまで行うべきか、そのレベル感はどう考えていますか。
松岡:企業のコアコンピタンスとなるプロダクトにおいては、内製化は必須であると考えます。内製化することによってエンジニアの事業への理解が深まり、コミュニケーションの効率が上がり、開発出力が向上します。ただ例外もあり、事業の不確実性が高い場合は準委任契約のエンジニアが増える傾向にあります。これらを踏まえて経営としてどのように判断するかが重要です。
古川:要件定義をビジネサイドが行い、エンジニアは受け身で仕事を進める。このような環境は内製化とは言えないと考えています。エンジニアがイニシアチブを持ち仕事に臨む環境が、本来の内製化だと思うからです。そしてこのような環境こそ、エンジニアが働く醍醐味であると同時に、我々のビジョン「はたらいて、笑おう」の実現につながるとも考えています。
石山:SIerなどから事業会社に転職しても活躍できる、エンジニアのタイプについてはいかがでしょう。
松岡:マインドチェンジできるかどうかが重要です。SIerのビジネスモデルは、要件に対していかにしっかりとしたシステムを納品できるか、QCD(※)が重要視されます。一方で事業会社は、納入したシステムでいかにKPIを上げていくかが求められます。数字は人の行動を変え、振る舞いはマインドにも影響を与えます。これを切り替えられるひとは、転職されても活躍できると思います。
※QCD:Quality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)
石山:最後にこれから取り組んでいきたいことをお聞かせください。
古川:パーソルグループにはさまざまな仕事があるので、グループした人材に適所で活躍いただきたいと考えています。まさに適所適材の考えです。その結果、ラグビーのスクラムのような、一人ひとりのメンバーが明確な役割を持っているからこそ、チームとしての質が高まる。何をしていいのか分からない人が集まっているグループとは違う、本物のチームを作りたいと考えています。
松岡:日本が世界最高水準の技術力国家になるためには、国内企業のDX推進が必須であり、その推進は開発者体験、すなわちエンジニアにとって働きやすい環境作り=各社の採用力強化にも繋がります。日本CTO協会ではDX Criteriaを多くの企業・団体で活用いただけるよう拡散していくと同時に、その結果やノウハウ、課題を共有いただける仲間を増やしていきたいと考えています。ご関心のある方は、ぜひ日本CTO協会のHPをご覧ください。
【Q&A】参加者から寄せられた質問を紹介
Q:心理的安全性を高めるために、1on1ではどのようなことを意識して行っているか
松岡:無限にありますが、1on1を開始する前が重要であると考えています。それは、普段からマネージャーとして一貫性のある態度を取り、善行を積んでいるのかということです。そうでないと、どんなテクニックを使っても部下は上司に対して心を開いてくれません。
石山:当社では1on1の内容をAIで分析していて、ガイドラインも設けています。笑顔でいる割合は30%以上、上司ではなくメンバーが話す割合が7割以上などで、サーバーントリーダシップの構築を目指しています。
古川:自分の意見を押し付けるのではなく、傾聴。相手に話してもらうよう努めています。また何かをしてもらったときには誰に対しても「ありがとう」との言葉を発することも意識しています。
小林:ITエンジニアがパフォーマンスを発揮できる状況を分析した結果、まさに松岡さんがコメントした「善行を積む」がポイントだと分かりました。いくら笑顔で話していても、日常の行動が伴っていないと、メンバーは納得しないということです。
Q:非エンジニアがITエンジニアに、ジョブチェンジをすることは可能か
松岡:医師であった方がGoogleに入社した事例があるように、可能ではあります。ただし人によると思います。適正を調べるには、iOSのアプリを自分で開発してみることをおすすめします。その上で本当に興味があると感じたら、オンライン、YouTube、大学院など、学ぶ場はいくらでもありますから、改めて本腰を入れてスキルを磨くことをお勧めします。
古川:可能だと思います。もちろん向き、不向きはあるでしょうから、そこは実際にプログラミングしてみると良いと思います。またIT業界は2~3年で新しい技術に入れ換わっていきますから、ジョブチェンジする機会は増えていると思います。
小林:ITエンジニアは常に学び続ける職種ですが、日本人の非エンジニアの多くは現場仕事に追われ、職場外の勉強をする機会がほとんどありません。その落差というか、学習習慣の違いを乗り越えられるかがポイントだと思います。
Q:エンジニアが一緒に働きたいと思う非エンジニアのタイプは?
松岡:まずは、特定ドメインのスペシャリストであること。言い方を変えると、その分野に関しては怖いと思えるほど熱中しているタイプです。もうひとつは、お客様に限ったことではありませんが、困っている人や社会課題を何とかして解決したい、助けたいと思っている方と一緒に働きたいと、私は思っています。
おすすめイベント
関連するイベント