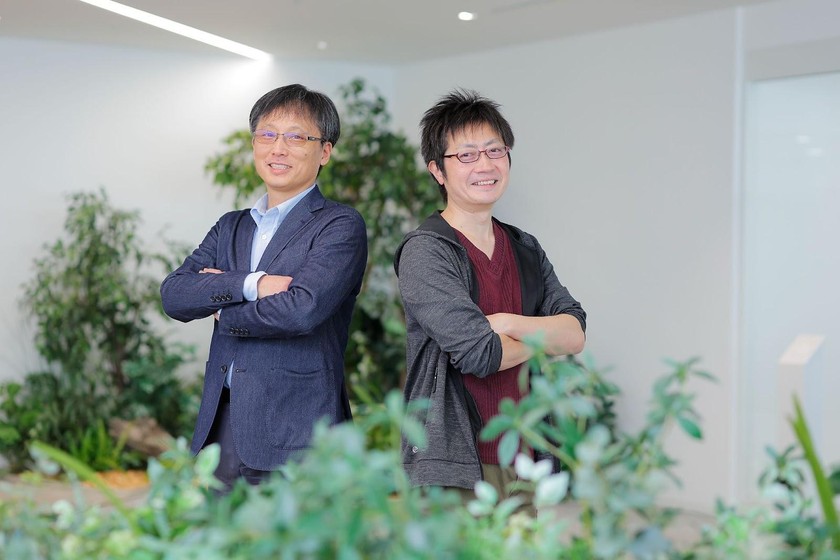Hondaが挑戦するUX起点のプロダクトづくり――シリコンバレー流を取り入れ、顧客体験をアップデートする『The Garage』UX改革とは
2024年4月に、Hondaが天王洲に倉庫をオフィス化した新しい拠点『The Garage』を構え、「顧客体験のアップデートが加速するUX起点でのモノづくり」に取り組む。具体的にはどのようなプロジェクトなのか。今回はシリコンバレーに本社をおくDrivemodeのCEOである古賀洋吉氏をスペシャルゲストに、HondaのモノづくりへのアプローチとUX起点でのデジタルプロダクト開発の最前線に迫る。アーカイブ動画
Hondaの顧客起点の開発──データドリブン・UX起点でプロダクトを磨き上げる

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター BEV企画統括部 UX企画部 部長
シニアチーフエンジニア 宮下 拓也氏
最初に登壇したのは、2013年に入社後、ビッグデータを活用したリチウムイオン電池の開発やデータサイエンティストの専門集団のリードを経て、HondaのDX推進に貢献してきた宮下拓也氏だ。現在は、UX企画部の部長ならびにシニアチーフエンジニアとして、HondaのUX起点の開発を推進している。
宮下氏はまずは、Hondaが考えるUX起点のものづくりについて、具体的なプロセスを説明した。大きくはスライドで示したように4つのフェーズで進めている。

まずはフェーズ①では、顧客がプロダクトを使っていて感じた不満やペインポイントを明確化する。続いてフェーズ②では、なぜそのような不満が生じているのか、原因を究明する。
そしてここからがまさにUX起点のものづくりになるが、どのようなUXを描くことができれば、顧客は不満を解消するだけでなく、幸せになるのかを探っていく。

宮下氏はHondaの創業者である本田宗一郎氏の創業エピソードと重ね、「本田宗一郎さんが開発した製品も、まさにユーザー起点で作られた製品です」と述べ、具体的な事例を紹介した。
毎日自転車の移動で疲れている妻に、快適に移動してもらいたいという想いから開発した自転車に簡易的なエンジンを載せたバイク「バタバタ」である。ここで重要なのは、本格的なバイクではなく、妻と同じような悩みを持っている人たちの多くが手に入れられるよう、あえて自転車とすることで価格を抑えたことだ。
「Hondaは『人間を研究するところだ』と、本田宗一郎さんは言っています 」(宮下氏)
宮下氏は創業時から現在まで脈々と受け継がれるHondaの哲学を述べる一方で、「顧客を観察し、背景にある事柄を洞察して分析した上でプロダクトを開発することは、一筋縄ではいきません。しかし、そのような苦労を乗り越えることで、これまで数多くのヒット製品を生み出してきました」と、続けた。

一方で、「これまでのUX起点のものづくりは、アナログな感が否めなかった」と、宮下氏は指摘する。そこで、改めてデータドリブンなUX起点の開発を進めるべく、宮下氏らが所属するUX企画部の設立に至る。
具体的には、シリコンバレー流のスキルを導入し、元々Hondaが持っているアナログでの顧客分析スキルをかけ合わせることで、顧客体験がより高まるプロダクトを世に送り出していくことだ。
最終的には「データを活用して顧客との対話のサイクルをまわしていくことで、UXを継続的に改善していく開発体制にしたい」と宮下氏は述べ、ファーストセッションを締めた。
『The Garage』を拠点に、Honda✕Drivemode社で爆速開発を推進

本田技研工業株式会社/グローバルUXオフィサー (日本)
Drivemode, Inc./CEO (シリコンバレー) 古賀 洋吉氏
続いて登壇したのは、シリコンバレーでDrivemode社を起業した後、2019年にHondaに売却。以降はグローバルUXオフィサーとして、Hondaのデジタル戦略とUXの責任者を担う古賀洋吉氏だ。

Drivemode社は現在もシリコンバレーに本社を置くITスタートアップだ。2015年に東京オフィスを開設したのを機にHondaと交流、協業するようになっていった。そして、運転をより楽しくするためのアプリを開発しており、300万ダウンロードという大ヒットを記録する。
以降、両社の関係性はさらに深まり、正式にHondaのグループ企業となってからは、Honda製品のソフトウェア開発はもちろん、シリコンバレー流の開発スキルやスタートアップの文化なども提供している。
正式にHondaグループの一員となってから約5年が経ち、古賀氏は共同拠点の開設を考えるようになる。そこで浮かんだのが、Drivemode社を設立した当時の記憶だ。
まさにシリコンバレーらしいガレージでの創業であり、「AppleやGoogleも最初にスタートしたのはガレージ」と古賀氏。ガレージにこだわったオフィスの設立に意欲を見せる。

このような古賀氏の想いから生まれたのが、イベント開催場所でもある天王洲に設けられた『The Garage』だ。実車が置けるガレージがある他、両社が協力して開発したアプリなどを体験することもできる。
「トップクラスのIT企業からトップクラスの人材を集めて大規模プロジェクトを実行すると、だいたい失敗する」と古賀氏。しかし「それが、いい」と続けるとともに、とにかくプロトタイプを作り、市場からフィードバックをもらい、バックログを作成する。
さらに失敗箇所を一つずつ潰していくことで、結果としてUXが良くなるとともに「Hondaのような大企業も変わっていける」と、続けた。
「我々の仕事は、Hondaの強みとシリコンバレーのソフトウェアの強みを組み合わせて、爆速で従来のシステムをぶっ壊して、どんどん再構築していくことです。実際、いろいろなプロダクトが生まれていますし、学びも得ています」(古賀氏)

いわゆるスタートアップと大企業のカルチャーの違いについても「ギャップは感じています」と話しながらも宮下氏が述べたように、「本田宗一郎氏のベンチャー魂が現在でも受け継がれており、度量が広い」と古賀氏は述べた。
今後も両社が切磋琢磨しながら開発を続けていくことを誓い、次のメンバーにバトンを渡した。
Hondaをリードする新たなソフトウェア、UX起点のプロダクト開発とは

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター BEV企画統括部
UX企画部 UXソリューション企画課 チーフエンジニア 三戸 翔太氏
続いて登壇したのは、2007年に入社し、オーディオ・インフォテイメントシステムの設計を担当。四輪新機種の戦略企画などを経て、デジタルサービス領域のUX/UI企画グループのチームリーダーを務める三戸翔太氏だ。
三戸氏がリーダーを務めるUX/UIチームの役割は、クルマを購入してから日々利用するシーンやディーラーでの、メンテナンスである。さらには次のクルマに乗り換えるまでの顧客体験すべてをデザインすると同時に、顧客が潜在的に抱える問題の解決を、Web・アプリ・リアルなディーラーサービスなどを通して、企画・プロトタイピングしていく。

Hondaでは「人間のためのスペースは最大に、機械のためのスペースは最小限に」という、人を中心としたM・M思想がクルマづくりの哲学・原点としてある。また、バイク、クルマはもちろん、F1や航空機などあらゆる分野において、「世界一になる」というHondaイズムも根付く。
もちろん、このような哲学はソフトウェア領域でも該当し、「世界トップのモビリティソフトウェア企業を目指しています」と、三戸氏は力強く語った。

では、具体的にどのようなアプローチでモビリティソフトウェア企業として世界一を実現するのか。三戸氏は、「単に良い製品やサービスを作ればいいわけではなく、仕事や組織から根本的に見直しています」と述べた。
キーワードとなるのは、ソフトウェアで価値を最大化する「ソフトウェアデファインド」である。従来のようにハードウェア=クルマを中心とした、販売したら終わりといったものづくりではなく、顧客起点でプロダクトを開発する。そして販売後も、製品やサービスを提供し続ける開発アプローチへの変革だ。
ハードウェアの開発経験もある三戸氏は、「ソフトウェアをデザインしてから、ハードウェアを決める。従来とはまったく逆の開発アプローチに、今まさにチャレンジしている最中です」と、現状を語った。

開発体制においては先ほど登壇した古賀氏のようなIT企業を参考に、部門を横断するチームを結成し、データを活用したUX/UI起点で、顧客ニーズに応えるプロダクトに磨き上げていく。
具体的なプロダクト開発においては、顧客の解像度を上げ、どのような課題を持っているのかピックアップしていく。その課題を解決するためにデータを活用しながら、どのようなプロダクトであれば、多くの顧客の課題解決に貢献するのか検討する。
つまり、マーケットバリューも兼ね備えているのか。このような視点を持ちながら、ブラッシュアップを重ねていく。
逆に良くない例は、企業側のアイデアから始めるアプローチであり「お客さまの課題解決を問い続けることが重要です」と、三戸氏は語った。

「今まさに進めている最中です」という、具体的な開発実例も示した。まずは「ユーザー理解」が起点となる。その際にポイントとなるのが、繰り返しになるが、データ活用である。
下記スライドの実例では、アプリや「IVI(In-vehicle Infotainment)」から得た顧客の実用データならびに、ユーザーへの調査などで顧客が抱える課題を理解する。次のステップでは、複数ある課題の中からワークショップなどを行い、解決する課題の優先順位を決める。
その後はそれぞれの課題を解決するプロダクトのプロトタイプを作成すると共に、ユーザー検証を行う。課題を解決するプロダクトだと判断された場合には、仕様書作成や開発メンバーとの議論を重ね、実際のプロダクト開発に臨む。

現在、三戸氏のチームでは、このようなプロダクト開発を課題解決の数だけ並行して取り組んでいる。また、ユーザー検証、開発メンバーとの議論、リリース後の検証などにおいてもブラッシュアップを重ねることで、顧客の課題をしっかり解決できているのか、徹底的に確認している。
三戸氏は最後に「SPEED」と大きく書かれたスライドを示し、次のように述べ、セッションを締めた。
「我々の組織もチームも、取り組んでいるプロセスも、プロトタイピングだと思っています。とにかく爆速で突き進み、お客さまの声に鍛えられることで、力のあるソフトウェア開発を実現していきたいと考えています」(三戸氏)

Honda製品の体験とつながるクルマの価値を高めるデジタルサービス

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター BEV企画統括部
UX企画部 デジタルラボ スタッフエンジニア 清水 克真氏
続いて登壇したのは、2019年に新卒で入社し、スポーツカー向けロガーアプリ「Honda LogR 2.0」の開発管理などを担当する清水克真氏だ。清水氏はApple CarPlayやAndroid Auto、さらにはCIVIC TYPE Rに特化した「Honda LogR 2.0」といったアプリの担当を経て、現在は同じくクルマ関連のアプリ「RoadPerformance」のプロジェクトリーダーを務める。
「Honda LogR 2.0」はクルマが今、どのような状態なのかを車載モニターやスマホで可視化する機能を備えたアプリだ。さらには公道で、加速状況などの走行状態を採点することもできる。また、サーキットでの利用も想定しており、ラップを計測する機能も併せ持つ。
「RoadPerformance」は「Honda LogR 2.0」の採点機能のみをスマホアプリ用に汎用化したものであり、Honda以外のクルマでも利用可能だ。

「Honda LogR 2.0」は、車載・スマホの両アプリがあり、清水氏は当初スマホアプリのみの担当であった。そこで感じた車載・スマホアプリ開発の違いを「文化が異なる」と述べるとともに、具体的にどのように異なるのか、違いにより生じた問題なども併せて紹介した。
クルマの開発はいわゆる従来のウォーターフォール型であり、年単位で進む。搭載される車載組み込みアプリも同様だ。そのため一般的なスマホアプリやソフトウェアとは異なり、リリース当初からバグが出ないように、完璧な状態までの仕上がりに取り組む。

クルマならびに車載アプリの開発のめどが立ってからは、サーバーやスマホアプリの開発が始まる。当然だがスケジュールは厳しく、UIなどを車載アプリに準じたものにデザインすることが求められる。

一方で、「ゲームらしいデザイン」など、スマホアプリならではの仕様も求められた。
「仕様バグが頻繁に起きたり、車載と表記が異なっていたりなど、さまざまな問題が起きました」と、清水氏は開発の苦労を振り返った。

しかし、「得られたこともあった」と、清水氏は語る。CIVICオーナー以外やサーキット走行をしないユーザーからのニーズであり、清水氏はまさしくUX起点のプロジェクト開発スキームである、プロダクトの体験会を実施する。
そして、体験会で得た仮説の検証やさらなるニーズを組み入れたスマホアプリの開発に挑む。そのアプリが、「RoadPerformance」である。

開発においては三戸氏が紹介したように、ユーザー調査、プロトタイプの作成、ユーザー検証、これらの取り組みを繰り返すトライアルを経て、アイデア出しから1年弱でリリースに至った。そして現在も、さらなる改善フィードバックループを展開している。

清水氏はこのような取り組みを経て、クルマなどの製品とつながるスマホアプリを開発した。つながる際には、「クルマなどの製品で体験したUXがハッピーになるような、アプリの開発を目指している」と述べた。
具体的には、クルマ自体にスマホアプリを直接ダウンロードできたり、クルマで得たデータを活用できたりするアプリだ。そして次のように述べ、セッションを締めた。
「現在は、Honda製品の体験とつながるデジタルサービスを、『The Garage』というデジタルオフィスを拠点に、次々と開発している状況です」(清水氏)

現実世界とデジタル世界を”ゆるく”つなぐ、Apple Vision Proアプリ開発の舞台裏

本田技研工業株式会社
電動事業開発本部 BEV開発センター BEV企画統括部
UX企画部 UXソリューション企画課
アシスタントチーフエンジニア 大坪 浩司氏
続いて登壇したのは、モバイルアプリのエンジニアとして15年ほどのキャリアを誇る大坪浩司氏だ。Hondaに入社したのは、2022年。現在は内製ソフトウェア開発グループにて、バイク向けのコンパニオンアプリ「Honda RoadSync」や、Apple Vision Pro向けアプリ「with Emile」のテックリードを務める。

大坪氏はまず、自身が所属する内製ソフトウェア開発部門の体制を紹介した。大坪氏やアプリケーションエンジニアの他、サーバーエンジニア、データエンジニアなど多様なメンバーがプロダクトごとにアサインされ、アジャイルでスピーディーな開発を継続している。
自身が開発、ローンチに携わっているアプリも紹介した。清水氏が携わる「RoadPerformance」の他、「Honda RoadSync」、この後紹介するApple Vision Pro向けのアプリ「with Emile」などだ。「プロダクトによっては1~2週間でアップデートしています」と、述べた。

「with Emile」とは、Apple Vision Pro に映し出されるドライブ好きの相棒Emile(エミル)というキャラクターが、現実世界のクルマとデジタル世界をシームレスに、“ゆるい”つながりが体験できるアプリである。
例えば、ドライブ好きのエミルは日本中を旅しており、バーチャルモードを起動することで、エミルがどこを走っているのかをユーザーは共有できる。

Apple Vision Proを選定した理由はいくつかある。1つ目は、現実とバーチャルのバランスが取れたXRデバイスであること。2つ目は、ゆるいつながりを実現するに当たって重要な要素である、複数のアプリが同時に起動できる機能が備わっていたことだ。
開発当初は、Apple Vision Proはまだ発売されていなかった。加えて、新たな価値の検証や生活体験にチャレンジする、アーリーアダプター像がHondaと重なったことなどがあったからだ。
「チームのモチベーションが高まるだろうという期待もありました」(大坪氏)

ユーザーのペルソナは、パートナーがクルマで通勤するテック系在宅ワーカーをイメージしたという。
開発においては実機がまだ発売されておらず、手元にない状態であったため、実機に触ることのできるApple Vision Proのラボを訪問した上で、シミュレーターによる技術検証を行った。
その後、米国で発売されると現地に赴き2台購入し、実機での検証に移行した。本格的な開発を経て、こちらも清水氏が開発したアプリと同様、構想から1年を経たずしてのリリースを実現させる。
UX起点、ユーザーの体験においても調査を行った。具体的にはApple Vision Proを使うことで、どのようなイマーシブ(没入感)が得られるのか。その中から、どのようなアイデアが実行可能かといった内容だ。

その1つが、バーチャル上の街をエミルと共に走る体験だ。この時点では実機がなかったため、iPhoneでARを表示して体験を検証した。
また、ゲーム開発のメジャーツール、Unityで開発する必要があったが、こちらも当時はApple Vision Proで適切に表示できるライブラリが存在していないなど、いくつかの壁にぶち当たった。
その他にも、Look Around機能が使えないかなど、技術的な検証も含めてさまざまなフィジビリティ(実行可能性)を継続した。

ペルソナにマッチした体験を提供するために、ユーザーが地図を見なくとも、エミルの存在を感じられるように、一目でどのような状態かが分かるような工夫も行った。
そして、ここでもゆるいつながりを大切にするために、地図には走行ルートのみを表示することとした。
大坪氏は先ほどの開発スケジュールを再掲し、この時点でドライバー側のアプリを用意すべきかどうかという、大きく3つの課題が生じていたことを明かした。
当初は、リリース日を遅らせてアプリを開発するという選択肢もあった。だが、Apple Vision Proの日本での発売日に、同時リリースしたいというチームメンバーのモチベーションが高かったことから、ドライバー側のアプリはリリース後に実装することとした。

ただし、車両側の情報は必要であったため、Xと連携してスタッフによるイベント配信というかたちで代行することとした。そして、そのようなスタッフと双方向のコミュニケーションが取れるように、ハートのスタンプを送れる機能も追加した。

最後に大坪氏は次のように述べ、セッションを締めた。
「リリースは無事間に合いましたが、見送った項目はフィジビリティも含め、現在も取り組んでいます。その他のXRサービスも鋭意開発取り組み中ですので、今後にご期待ください」(大坪氏)
【Q&A】参加者からの質問に登壇者が回答
セッション後は、イベント参加者からの質問に登壇者が回答した。抜粋して紹介する。
Q.爆速開発を進めるソフトウェア側と、ハードウェア側との擦り合わせについて
宮下:Hondaはこれまで、安全第一のクルマ開発をしてきました。アジャイル開発の有無も含め、このような安全の担保はこれまでと変わりません。その上で、どこを爆速開発するのか。切り分けが極めて難しいテーマであり、現在模索しながら慎重に進めています。
古賀:プロダクトからリアルタイムデータを得られるところは、アジャイル開発で進めています。一方、販売データから予測できるものはウォーターフォール開発でと考えています。ただし正解はないので開発を進めながら、丁寧にブレイクダウンすることで解決や正解に近づくと考えています。
実現に向けては、テストの方法を調整しています。少しずつロールアウトする。アーキテクチャやコンポーネントの選定、組織、戦略などの調整なども必要だと考えています。
Q.従来の開発手法からIT業界の手法に変えていく際に、苦労・工夫したことは?
宮下: Hondaの99%の社員は、既存の手法で開発を行っています。まず、ここをリスペクトします。一方で、プロダクト起点の開発は分けて考え、進めていきます。そして新しい開発手法がかたちとなったところから、移管していく。そのような流れを意識しています。
古賀:正直コンフリクトもありますが、大事なことは、ゴールは同じだということです。また、Hondaは元々アジャイル的なコンセプトを持っていました。そこで何度も質問を投げ続け、丁寧に一つずつ課題をブレイクダウンしていくことで、実現させられると考えています。
三戸:自己紹介でも述べたように、私は元々ハードウェアの業務に携わっていたので、ソフトウェアのアジャイル開発プロセスをハードウェアに導入した瞬間、コンフリクトが起きることは理解しています。
一方で、お客さまの体験を良くしたいという想いは、皆が思っていることです。そこで組織改革なども含め、常に毎日あれこれと考えながら、改革に臨んでいるところです。
Q.古賀さんはHondaにどう受け入れられているのか?
宮下:古賀さんのようなユニークなキャラクターとは異なりますが、Hondaの人たちも一癖や二癖ある人が多いため、コンフリクトすることは結構あります。
一方で、目指すべきゴールは同じですし、Hondaの人たちは懐が深く、さっぱりしているタイプも多いので、僕自身も受け入れていますし、会社全体を見ても全然問題ないと思っています。
古賀:僕自身もHondaの文化を受け入れていますし、今ここにいることが、受け入れられている証だと思っています。
Q.イノベーションを推進するための Hondaならではの取り組みや工夫は?
宮下:大きく2つあります。1つ目は会社側の施策で、従業員のイノベーションやアイデアを刺激する、スタートアップのような仕組みを整備していることです。もう一つは、従業員のやる気を後押しする文化や風土があるところです。
古賀:経営層の考え方が柔軟なことですね。プロダクト開発に対する情熱を持つ人が多い点です。こうした環境のため、どうしても解決したい課題があり、それを実現できるプロダクトを開発したいとした際は、本来のルール上はNGであったとしても、上層部の謎のサポートで開発ができたりします(笑)。
清水:しっかりと“かたち”にしたい人が多いと思います。また、自分の意見も同じくしっかりと言う人が多いと感じています。そのため意見がまとまらないこともありますが(笑)。
大坪:私も一人ひとりのプロダクトにする熱量は高いと感じています。そして同じく、スピーディーに“かたち”としてリリースしていく姿勢も、Hondaならではの“らしさ”だと感じています。
三戸:以前の開発で大失敗したことがありました。ただリカバリーに懸命にチャレンジしたところ、よく頑張る人だという謎の評価を得たことがありました(笑)。当時はおかしな会社だと思いましたが、今ではチャレンジが報われる。素晴らしい会社だと思っています。
本田技研工業株式会社
https://www.honda.co.jp/
本田技研工業のキャリア採用情報
https://www.honda-jobs.com/
本田技研工業の採用情報
https://global.honda/jp/jobs/?from=navi_footer_www
本田技研工業のSDV事業開発統括部 ブランドサイト
https://software.honda-jobs.com/
おすすめイベント
関連するイベント