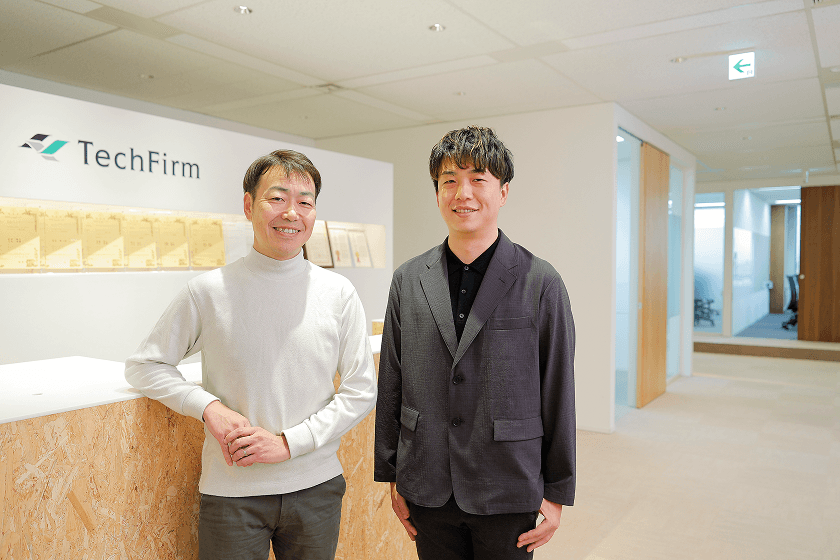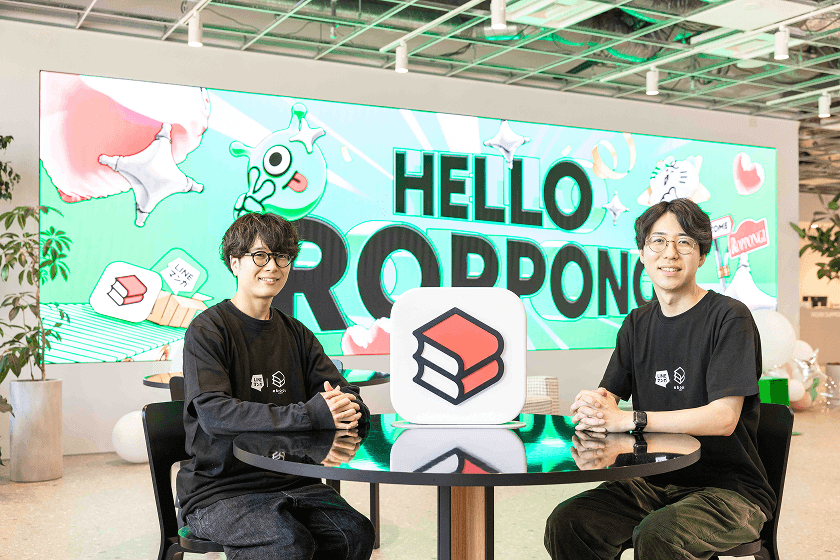ハードウェア
イベント

マガジン
技術ブログ
背景と目的 VMwareがBroadcomに買収されたことを契機に、VMware製品のライセンス体系やコスト構造が大きく変化し、既存の仮想化基盤を継続利用するか、あるいは別の選択肢へ移行するかの検討を迫られるケースが増えています。そのような状況の中で、オープンソースであるKVMは有力な選択肢となります。 VMwareからKVMへの移行を検討する際、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークといったリソース面の違いに加えて、可用性(High Availability:HA)をどのように確保するかは、特に重要な検討事項となります。多くの場合、vSphere HAを標準機能として利用しており
MathJax={tex:{inlineMath:[['$','$']],displayMath:[['$$','$$']],processEscapes:true}}; こんにちは、Insight Edgeでデータサイエンティストをしている新見です。 cuTile Pythonとは 背景 特徴 従来のCUDA(SIMT)との違い 文法 TileGymで行列積ベンチマーク 倍精度行列積エミュレーション Ozaki Schemeについて 分解(Split) 行列積の計算 素朴な実装と初回結果 最適化 Fast Mode(GEMMの削減) Fused Split Kernel(分割の融合) 最適化後の結果 dによる精度/速度トレードオフ まとめ 参考文献 今回はNVIDIAが発表したばかりの「cuTile Python」を試してみました。普段は、GPUカーネルを業務で書くことはありませんが、cuTileはPythonで書かれていて、文法もシンプルなようなので、GPUプログラミングの勉強の意味も含めて記事にしました。 cuTile Pythonとは cuTile Pythonは、NVIDIA GPU向けの新しい並列プログラミングモデル「cuTile」をPythonから使うためのDSL(ドメイン固有言語)です。 背景 GPU上で高速に動作する処理を自前で記述したい場面は増えていますが、CUDA C++の習得コストは依然として高いのが実情です。 PyTorchやcuBLASといった高レベルAPIで日常的な開発は十分カバーできるものの、LLM推論の最適化など低レイヤへの介入が求められる局面も増えてきました。NVIDIA Ampere世代以降のGPUではTensor CoreやTMA(Tensor Memory Accelerator)といったハードウェア機能が追加されており、これらを十分に活用するにはより踏み込んだプログラミングが必要になります。 しかし、ハードウェアを意識したコードを書く難易度は上がり続けています。メモリ階層ひとつ取っても、共有メモリ、レジスタ、Blackwell世代で追加されたTensor Memoryなど、用途に応じて使い分ける必要があり、それぞれの特性に合わせたデータ配置や転送の制御が求められます。 さらに、特定のアーキテクチャに最適化したコードは新しい世代のGPUが登場した途端に書き直しが必要になることも多く、保守コストも無視できません。 こうした背景から、ハードウェアの詳細を抽象化しつつ高い性能を引き出すDSLへの需要が高まっています。OpenAIの gpt-oss リポジトリでもTritonという同様のDSLが採用されており、この手のアプローチは業界でも広く注目されています。 特徴 GPUプログラミングには、cuBLASやPyTorchのような高レベルライブラリか、CUDA C++やPTXといった低レベルなスレッド制御か、という二極化がありました。cuTileはこの中間に位置する「Tileレベル」のプログラミングモデルです。 抽象レベルについて(動画[1]より) 以下、動画[1]で紹介されていた特徴になります。 CUDAプラットフォームにネイティブ統合 : OpenAI Tritonなどサードパーティ製DSLとは異なり、cuTile(Tile IR)はCUDAドライバに組み込まれています。既存のプロファイラやデバッガがそのまま使えます。 Tile IRへのコンパイル : Pythonで書いたカーネルは「Tile IR」という仮想ISAに変換され、ドライバが実行時にターゲットGPUに合わせた最適なマシンコード(SASS)を生成します。 技術スタックの階層構造、TileIRはPTXを置き換えるのではなく共存する(動画[1]より) 従来のCUDA(SIMT)との違い 従来のCUDA(SIMT: Single Instruction, Multiple Threads)とcuTileでは、プログラマが何を書いて何をシステムに任せるかが大きく異なります。 特徴 従来のCUDA (SIMT) cuTile (Tile-based) 実行単位 スレッド単位でデータ処理を記述。WarpやBlockの構成を意識する必要がある データの塊(タイル)と単一の実行単位(ブロック)で思考。スレッドへの分解はシステムが行う データ処理 個々のスレッドへのデータ分配(ストライディングなど)を手動で計算・管理 タイル(配列全体の一部)を一つの単位としてロード・演算・ストア メモリ管理 共有メモリの確保、同期(バリア)、バンクコンフリクト回避などをユーザーが管理 システムが管理。共有メモリの利用や同期は自動化され、ユーザーからは隠蔽 ハードウェア活用 Tensor Coreなどを使うには複雑なPTX命令や特定のレイアウトを意識する必要がある ct.load や演算子を書くだけでTMAやTensor Coreを自動的に活用 文法 cuTile Pythonは、Pythonのデコレータと専用の型システムを使って記述します。詳しくは公式ドキュメント[2]を参照してください。 主な特徴: @ct.kernel デコレータ : Python関数をGPUカーネルとしてマーク。関数内ではcuTile Pythonの文法に従う。 イミュータブルなタイル : カーネル内では、タイルが操作対象となる。タイルは「値」として扱われ、変更不可。演算すると新しいタイルが生成されます Array (Global Memory): 引数から取得、ミュータブル。 ct.load / ct.store でアクセス Tile (Local/Register): イミュータブルで演算対象 以下、ベクトル加算のコード例です。 import cuda.tile as ct # タイルサイズはコンパイル時定数 TILE_SIZE = 16 @ ct.kernel def vector_add_kernel (a, b, result): # 1. 現在のブロックIDを取得 (スレッドIDではない!) block_id = ct.bid( 0 ) # 2. グローバルメモリ(Array)からタイルとしてデータをロード # システムが自動的に最適なメモリ転送(TMA等)を行う a_tile = ct.load(a, index=(block_id,), shape=(TILE_SIZE,)) b_tile = ct.load(b, index=(block_id,), shape=(TILE_SIZE,)) # 3. タイル同士の演算 (要素ごとの加算が一括で行われる) result_tile = a_tile + b_tile # 4. 結果をグローバルメモリにストア ct.store(result, index=(block_id,), tile=result_tile) # ホスト側からの実行 # ct.launch(stream, grid_dim, kernel_func, args) ブロックごとに同一のカーネルが実行され、各ブロックはIDで指定されたデータを担当範囲として、処理を行います。タイル演算は、感覚としてはnumpyの処理に似ています。 TileGymで行列積ベンチマーク 実際に動かします。cuTileはCUDA Toolkit13.1以降が必要で、これはBlackwell世代以降の比較的最新のGPUでしか動かないようです。私は手元に最新のGPUがないので、クラウドサービスを利用したいと思います。今回は、 Modal と呼ばれるGPU特化のクラウドサービスを利用しました。 Modalは関数ベースでGPUインスタンスを立ち上げられるサービスになります。使い勝手がよく、便利です。実行時間に応じた従量課金制で、今回の検証のような少しGPUを試してみたい場合に適しています。 今回は、公式のサンプルレポジトリTileGym[3]をベースに、行列積のコードの実行をしてみます。Modalで走らせる実行コードを以下に示します。imageでDockerイメージを作成し、TileGymのレポジトリをクローン、ライブラリインストールを行います。Modalの詳細は ドキュメント を参照してください。今回対象のGPUはB200です。 # run-tilegym.py import modal image = ( modal.Image.from_registry( "nvidia/cuda:13.1.0-devel-ubuntu24.04" , add_python= "3.13" ) # CUDA 13.1開発環境イメージ .apt_install( "git" ) .run_commands( "pip install --pre torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130" ) # PyTorchインストール、比較のため .run_commands( "git clone https://github.com/NVIDIA/TileGym.git && cd TileGym && pip install -e ." ) # cuTile, TileGymインストール .entrypoint([]) ) app = modal.App( "tilegym-test" ) @ app.function (gpu= "B200" , image=image, timeout= 600 ) def run_mma_bench (): import os os.chdir( "/TileGym" ) os.system( "python tests/benchmark/bench_matrix_multiplication.py" ) @ app.local_entrypoint () def main (): run_mma_bench.remote() 上のコードをrun-tilegym.pyとして保存し、 modal run run-tilegym.py で実行します。問題なければ結果は、以下のように出力されるはずです。 matmul-performance-float16-TFLOPS: M N K CuTile PyTorch 0 1024.0 1024.0 1024.0 271.056760 473.522850 1 2048.0 2048.0 2048.0 1129.688506 1199.365877 2 4096.0 4096.0 4096.0 1235.696555 1401.341171 3 8192.0 8192.0 8192.0 1483.030888 1253.946946 4 16384.0 16384.0 16384.0 1356.600018 1536.098446 5 32768.0 32768.0 32768.0 1254.836929 1306.057063 matmul-performance-float8_e5m2-TFLOPS: M N K CuTile 0 1024.0 1024.0 1024.0 277.309352 1 2048.0 2048.0 2048.0 1154.454102 2 4096.0 4096.0 4096.0 2769.415226 3 8192.0 8192.0 8192.0 2981.168986 4 16384.0 16384.0 16384.0 2935.864636 5 32768.0 32768.0 32768.0 2658.604232 CuTileとPyTorchの行列積のベンチマークが出ています。float16とfloat8_e5m2の両方で行列積を実行していますが、PyTorchでは、後者の行列積が未対応のようです。PyTorchは裏側でcuBLASを呼び出しているので実質cuBLASとの比較です。float16では、CuTileはPyTorchに近い性能、一部のサイズでは、PyTorchを上回る性能が出ています。float8_e5m2では、行列サイズが4096以上でfloat16の約2倍の性能が出ています。 以下が TileGym/src/tilegym/ops/cutile/matmul.py の行列積のカーネルコードの抜粋です。 @ ct.kernel (num_ctas=ct.ByTarget(sm_100= 2 )) def matmul_kernel (A, B, C, TILE_SIZE_M: ConstInt, TILE_SIZE_N: ConstInt, TILE_SIZE_K: ConstInt): # 担当タイルのインデックス計算(L2キャッシュ局所性のためswizzle) bidx, bidy = swizzle_2d(A.shape[ 0 ], B.shape[ 1 ], TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N, GROUP_SIZE_M= 8 ) num_tiles_k = ct.num_tiles(A, axis= 1 , shape=(TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_K)) # FP32アキュムレータの初期化(FP16入力でも精度維持のためFP32で累積) accumulator = ct.full((TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N), 0 , dtype=ct.float32) # FP32→TF32変換(Tensor Coreを利用するため) dtype = ct.tfloat32 if A.dtype == ct.float32 else A.dtype # K方向にタイル単位でループ for k in range (num_tiles_k): a = ct.load(A, index=(bidx, k), shape=(TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_K), padding_mode=ct.PaddingMode.ZERO).astype(dtype) b = ct.load(B, index=(k, bidy), shape=(TILE_SIZE_K, TILE_SIZE_N), padding_mode=ct.PaddingMode.ZERO).astype(dtype) accumulator = ct.mma(a, b, accumulator) # 行列積計算・累積 # 出力型に変換して結果を書き出し ct.store(C, index=(bidx, bidy), tile=ct.astype(accumulator, C.dtype)) A:MxK @ B:KxN -> C:MxN の行列積で、M方向、N方向単位でバッチに切り分けCの部分タイルごとに並行して実行されます。K方向にも部分分割して、順次読み込み(load), 行列積計算(mma), 結果の保存(store)を行っています。cuTile側でメモリの種類やMMA命令の選択は書く必要がなく、コンパイル時に自動的に最適化されます。 このように簡潔に書いても、ゴリゴリにチューニングしているcuBLASに匹敵した性能を出しているというのがcuTileの売りなようです。 ベンチマークを動かしただけでは面白くないので、型の精度を少し上げて同様の計算をしてみます。F32演算の場合、上記コードでは行列をTF32に変換してから計算しています。それと合わせるため、PyTorch側も以下のようにTF32を有効化します。 # TileGym/tests/benchmark/bench_matrix_multiplication.py # Enable TF32 for PyTorch to match Tensor Core behavior torch.backends.cuda.matmul.allow_tf32 = True torch.backends.cudnn.allow_tf32 = True また、FP64演算にあたり、累積の型がFP32では精度が足りないため、cutileコード側で累積の型をFP64に変更する処理を追加しています。 # Initialize an accumulator for the current output tile (TILE_SIZE_M x TILE_SIZE_N). # Use float64 for float64 inputs, otherwise float32 for higher precision accumulation. acc_dtype = ct.float64 if A.dtype == ct.float64 else ct.float32 accumulator = ct.full((TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N), 0 , dtype=acc_dtype) 以下が修正後のベンチマーク結果です。 matmul-performance-float32-TFLOPS: M N K CuTile PyTorch 0 1024.0 1024.0 1024.0 208.295471 294.114105 1 2048.0 2048.0 2048.0 665.976324 648.103430 2 4096.0 4096.0 4096.0 698.961883 747.326296 3 8192.0 8192.0 8192.0 783.858756 761.237840 4 16384.0 16384.0 16384.0 856.688401 742.126004 matmul-performance-float64-TFLOPS: M N K CuTile PyTorch 0 1024.0 1024.0 1024.0 0.855789 26.687611 1 2048.0 2048.0 2048.0 1.063844 33.830530 2 4096.0 4096.0 4096.0 1.124713 35.400544 3 8192.0 8192.0 8192.0 1.124824 35.438650 FP32では、PyTorchに近い性能が出ています。一方、FP64では、cuTile側での最適化がまだ不十分なようで、PyTorchに大きく劣る結果となっています。TILE_SIZEをより小さく設定することで、1.6 TFLOPS程度には改善しましたが、まだ大きく劣っています。 原因としては、cuTileの ct.mma がFP64演算に対して効率的な命令へマッピングできていない可能性が高いです。cuBLAS(PyTorch)はFP64 Tensor Coreを含むハードウェアリソースを最大限に活用した成熟した実装を持っており、この差が性能差に直結しています。 ここで、FP64演算の性能を向上させるために、Ozaki Schemeと呼ばれる倍精度行列積エミュレーション手法を試してみます。 倍精度行列積エミュレーション Ozaki Schemeについて Ozaki Schemeは、FP64の行列積をFP64演算なしで高精度にエミュレートする手法です[4][5]。詳しくは元の論文を読んでほしいのですが、概要を説明します。基本的なアイデアは、FP64行列を複数の低精度行列に分解し、Tensor Coreで高速に行列積を計算するというものです。行列の分解、行列の計算、結果の累積の3段階で構成されます。 分解(Split) 論文に従い、以下の型を定義します。 Type1 (FP64): 元の行列の精度。仮数部 $m_{\text{Type1}} = 53$ ビット Type2 : 分解先の低精度型(BF16, FP16, FP8等)。仮数部 $m_{\text{Type2}}$ ビット(隠れビット含む) Type3 (FP32): Tensor Coreの累積精度。仮数部 $m_{\text{Type3}} = 24$ ビット Type1の行列 $\boldsymbol{x}$ を、残差 $\boldsymbol{x}^{(p)}$ がゼロになるまで再帰的にType2スライス $\bar{\boldsymbol{x}}^{(p)}$ に分解します。$\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}$ として、各ステップ $p$ で以下を行います。 $$c_x^{(p)} = \left\lceil \log_2 \left( \max_i \left| x_i^{(p)} \right| \right) \right\rceil \tag{1}$$ $$\sigma = 0.75 \cdot 2^{\rho + c_x^{(p)}} \tag{2}$$ $$v_i = \text{fl}_{\text{Type1}} \left( \left( x_i^{(p)} + \sigma \right) - \sigma \right) \tag{3}$$ $$x_i^{(p+1)} = \text{fl}_{\text{Type1}} \left( x_i^{(p)} - v_i \right) \tag{4}$$ $$\bar{x}_i^{(p)} = \text{cvt}_{\text{Type2}} \left( \text{fl}_{\text{Type1}} \left( 2^{-c_x^{(p)}} v_i \right) \right) \tag{5}$$ ここで $\rho$ は精度パラメータ(Type1, Type2, Type3の仮数部ビット数と内積次元 $k$ から決定)です。$\sigma$ を足して引く操作(式3)がVeltkamp分割の核心で、上位 $m_{\text{Type2}}$ ビットを正確に抽出します。式4で残差を更新し、式5で $2^{c_x^{(p)}}$ で正規化してType2スライスを得ます。 この結果、$\boldsymbol{x}$ は $s_x$ 個のスライスに分解されます。 $$\boldsymbol{x} = \sum_{p=1}^{s_x} 2^{c_x^{(p)}} \cdot \bar{\boldsymbol{x}}^{(p)} \tag{9}$$ $c_x^{(p)}$ が指数部、$\bar{\boldsymbol{x}}^{(p)}$ が仮数部に対応します。スライス数 $s_x$ は $\boldsymbol{x}^{(p)} = 0$ になるまでの反復回数で決まり、理論的には $\lceil m_{\text{Type1}} / m_{\text{Type2}} \rceil$ ステップですが、行列要素のスケールのばらつきにより多くなることがあります。 PyTorchでの実装は以下の通りです。 def ozaki_split_to_type2_slices (x, k, type2, max_slices= 20 ): # 仮数部ビット数(隠れビット含む) m_fp64, m_fp32 = 53 , 24 m_type2 = - int (math.log2(torch.finfo(type2).eps)) + 1 # 精度パラメータ ρ の計算 gamma = math.ceil(m_fp64 - (m_fp32 - math.log2(k)) / 2 ) xi = m_fp64 - m_type2 rho = max (gamma, xi) slices = [] residual = x.clone().to(torch.float64) for _ in range (max_slices): max_abs = residual.abs().max().item() if max_abs == 0 or max_abs < 1e-300 : break c_x = math.ceil(math.log2(max_abs)) # 式(1) sigma = 0.75 * math.ldexp( 1.0 , rho + c_x) # 式(2) v = (residual + sigma) - sigma # 式(3) Veltkamp分割 residual = residual - v # 式(4) 残差更新 scale = math.ldexp( 1.0 , c_x) slice_type2 = (v / scale).to(type2) # 式(5) 正規化 + Type2変換 slices.append((slice_type2, scale)) return slices # [(Type2スライス, 2^c_x), ...] 行列積の計算 行列 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ をそれぞれ分解すると、行列積は以下のように展開できます。 $$\boldsymbol{x}^T \boldsymbol{y} = \sum_{p=1}^{s_x} \sum_{q=1}^{s_y} 2^{c_x^{(p)} + c_y^{(q)}} \cdot \bar{\boldsymbol{x}}^{(p)T} \bar{\boldsymbol{y}}^{(q)} \tag{10}$$ 各 $\bar{\boldsymbol{x}}^{(p)T} \bar{\boldsymbol{y}}^{(q)}$ はType2行列同士の積であり、Tensor CoreのGEMMで計算できます。Ozaki Schemeではρパラメータにより、このGEMMのType3(FP32)での累積が丸め誤差なしで成立するよう設計されています。 $$\bar{\boldsymbol{x}}^{(p)T} \bar{\boldsymbol{y}}^{(q)} = \text{fl}_{\text{Type3}} \left( \bar{\boldsymbol{x}}^{(p)T} \bar{\boldsymbol{y}}^{(q)} \right) \tag{11}$$ 式10の分解自体は数学的な恒等式として厳密に成立します。実装上は、外側の累積(スケール乗算と加算)をType1算術で行うことでType1精度を達成できます。 cuTileでの行列積カーネルの実装は以下の通りです。tilegymのmatmulカーネルとベースは同じで2つのスライス分のouter-loopが追加されています。 @ ct.kernel (num_ctas=ct.ByTarget(sm_100= 2 )) def ozaki_matmul_fused_kernel ( A_slices, # (s_a, M, K) Type2スライス B_slices, # (s_b, K, N) Type2スライス Combined_scales, # (s_a, s_b) 2^{c_x(p)+c_y(q)} のスケール行列 C, # (M, N) FP64 出力 TILE_SIZE_M: ConstInt, TILE_SIZE_N: ConstInt, TILE_SIZE_K: ConstInt, ): # タイルインデックス計算(L2キャッシュ局所性のためswizzle) bidx, bidy = swizzle_2d(M, N, TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N, GROUP_SIZE_M= 8 ) num_tiles_k = ct.cdiv(K, TILE_SIZE_K) # FP64最終アキュムレータ(式10の外側の累積) accumulator = ct.full((TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N), 0.0 , dtype=ct.float64) # 全スライスペア (p, q) をループ for p in range (num_slices_a): for q in range (num_slices_b): # FP32中間アキュムレータ(式11: Type3での丸め誤差なし計算) slice_acc = ct.full((TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N), 0.0 , dtype=ct.float32) # K方向のタイルループ for k in range (num_tiles_k): a_tile = ct.load(A_slices, index=(p, bidx, k), ...) b_tile = ct.load(B_slices, index=(q, k, bidy), ...) slice_acc = ct.mma(a_tile, b_tile, slice_acc) # Type2 Tensor Core MMA # スケーリングしてFP64で累積(式10) scale = ct.load(Combined_scales, index=(p, q), shape=( 1 , 1 )) accumulator = accumulator + ct.astype(slice_acc, ct.float64) * scale ct.store(C, index=(bidx, bidy), tile=accumulator) 素朴な実装と初回結果 上記のようにOzaki Schemeを実装してみます。スライス分割はホスト側のpythonで行い、各ペアのGEMMを順次実行する方式です。以下、2種類のType2で行列積を計算した結果です。 スライス数はA・Bそれぞれの分割数($s_a \times s_b$)、GEMMsはその組み合わせで実行したGEMM回数です。TFLOPSはFP64換算のスループット、Rel ErrorはPyTorch FP64結果を基準とした相対誤差です。 TYPE2 = FP16 行列サイズ スライス数 GEMMs Split(ms) Kernel(ms) 合計(ms) TFLOPS Rel Error 1024 10×10 100 1.48 0.62 2.64 0.81 1.58e-15 2048 12×12 144 2.57 2.66 5.75 2.99 1.98e-15 4096 12×12 144 8.69 21.59 30.70 4.48 6.31e-15 8192 14×14 196 36.00 192.32 231.76 4.74 7.28e-15 16384 14×14 196 135.21 1737.14 1884.24 4.67 3.35e-15 TYPE2 = FP8 (E4M3) 行列サイズ スライス数 GEMMs Split(ms) Kernel(ms) 合計(ms) TFLOPS Rel Error 1024 15×16 240 2.22 1.11 4.03 0.53 1.64e-15 2048 16×16 256 3.48 3.11 7.33 2.34 2.27e-15 4096 16×17 272 12.30 19.17 30.86 4.45 5.69e-15 8192 17×17 289 45.64 179.99 226.64 4.85 8.88e-15 FP16はスライス数が少ない分GEMMも少なくなりますが、FP8はTensor Coreのスループットが高いため、GEMMs数が多いにも関わらず類似の性能が出ています。いずれの型でもcuTile FP64直接計算(約1 TFLOPS)を上回っていますが、PyTorchの性能には大きく劣後しています。Split処理の時間も無視できず、特に小さな行列サイズでボトルネックになっています。また、参照した論文に記載されている必要なGEMM数(スライス数)よりも多くなっている点は気になりましたが、原因はわからずでした。 最適化 初回結果を踏まえ、いくつか改善を試みました。その中で効果があった方法が以下になります。 Fast Mode(GEMMの削減) スライス数が $s$ の場合、全組み合わせで $s^{2}$ 回のGEMMが必要です。しかし、スライスインデックスが大きい組み合わせ($i + j \geq d$)は寄与が小さいため、スキップできます。 [5]で提案されたFast Mode(Algorithm 3)では、確率的誤差限界 $|fl(AB) - AB| \leq 2\sqrt{k} \cdot u_{\text{FP64}} \cdot |A||B|$ を満たす最小の閾値 $d$ を自動決定します。 BF16の場合、典型的には $d = 9$ 程度で、GEMMは49回から39回に削減できます。さらに max_d パラメータで手動上限を設定すれば、精度とのトレードオフで計算量を調整できます。 実装としては、前述の行列積カーネルのスライスペアループに i + j >= D の条件を追加するだけです。 for i in range (num_slices_a): for j in range (num_slices_b): if i + j >= D: # Fast Mode: 寄与の小さい組み合わせをスキップ continue # ... K方向ループでMMA計算 ... Fused Split Kernel(分割の融合) 元の実装では、各スライスの計算ごとに max().item() でGPU→CPU同期が発生していました(BF16で7スライス = 7回の同期)。 改善後は、初回の max_abs 計算で1回だけ同期し、全スライスの $\sigma$ と $2^{-c_i}$(逆スケール)をCPU側で事前計算します。その後、単一カーネルで全スライスを一括計算します。 @ ct.kernel (occupancy= 4 ) def _veltkamp_split_all_slices_kernel ( x_in, # (M, N) FP64 input slices_out, # (num_slices, M, N) TYPE2 output slices sigmas, # (num_slices,) FP64 pre-computed sigma values inv_scales, # (num_slices,) FP64 pre-computed 1/scale values num_slices: ConstInt, TILE_SIZE_M: ConstInt, TILE_SIZE_N: ConstInt, ): bid = ct.bid( 0 ) # ... (タイルインデックス計算) ... # 入力タイルをロード residual = ct.load(x_in, index=(tile_m, tile_n), shape=(TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N), padding_mode=ct.PaddingMode.ZERO) # 全スライスをループで計算 for i in range (num_slices): sigma_tile = ct.load(sigmas, index=(i,), shape=( 1 ,)) inv_scale_tile = ct.load(inv_scales, index=(i,), shape=( 1 ,)) # Veltkamp分割 v = (residual + sigma_tile) - sigma_tile slice_tile = ct.astype(v * inv_scale_tile, slices_out.dtype) ct.store(slices_out, index=(i, tile_m, tile_n), tile=ct.reshape(slice_tile, ( 1 , TILE_SIZE_M, TILE_SIZE_N))) residual = residual - v 最適化後の結果 Fast Mode + Fused Split Kernelを適用した結果です。 TYPE2 = BF16 行列サイズ スライス数 GEMMs Split(ms) Kernel(ms) 合計(ms) TFLOPS Rel Error 1024 7×7 39 0.20 0.25 1.57 1.37 5.75e-15 2048 7×7 39 0.24 0.75 2.16 7.94 1.30e-14 4096 7×7 39 0.43 5.32 7.22 19.04 1.16e-14 8192 7×7 39 1.16 38.93 42.60 25.81 2.39e-14 16384 7×7 39 3.96 323.10 327.78 26.84 2.21e-14 TYPE2 = FP8 (E4M3) 行列サイズ スライス数 GEMMs Split(ms) Kernel(ms) 合計(ms) TFLOPS Rel Error 1024 14×14 130 0.25 0.61 2.99 0.72 3.48e-13 2048 14×14 130 1.27 1.60 6.80 2.52 3.57e-13 4096 14×14 130 2.13 9.31 15.88 8.65 3.41e-13 FP8はスライス数が多く(14×14)GEMMsも130回と多いものの、Fast ModeによるGEMM削減とFused Splitの効果で素朴な実装(4096で4.45 TFLOPS)から改善が見られます。ただしBF16と比較すると、仮数部が4ビットと少ないためスライス数が増え、GEMMs数の差(130 vs 39)がFP8のスループット優位を打ち消しており、BF16の方が総合的に有利になりました。 素朴な実装と比較すると、最適化の効果は顕著です。 Fused Split Kernel : Split時間が大幅短縮(素朴なFP16版 8192: 36.00ms → BF16最適化版: 1.16ms、約31倍) Fast Mode : GEMMsを49→39に削減(BF16の全組み合わせ比) BF16がTYPE2として最適である理由は、Tensor CoreのFP32アキュムレータとの相性にあります。BF16の仮数部は8ビットなので、2つのBF16値の積は16ビットに収まります。FP32の仮数部は24ビットあるため、TILE_SIZE_K=128個の積和(16 + log2(128) = 23 ≤ 24)が 丸め誤差なし で正確に計算できます。一方FP16(11ビット仮数部)では積が22ビットとなり、128個の累積(22 + 7 = 29 > 24)でFP32精度を超えるため、丸め誤差が発生します。 この性質により、BF16では1e-14というFP64に近い精度を維持しつつ、Tensor Coreの高いスループットを活用できています。 上記以外にも、タイルサイズの調整や、カーネル内のsplitループ方向のCTA分散も試みましたが、効果はありませんでした。本来は、プロファイラ(NVIDIA Nsight Compute)を使って、メモリ利用等解析するのが効果的ですが、Modal上ではNsightは使えないようなので断念しました。 dによる精度/速度トレードオフ d パラメータを変えて、16384×16384行列での性能と精度の変化を測定しました。BF16の結果です。 d GEMMs 合計(ms) TFLOPS Rel Error vs PyTorch FP64 9 (default) 39 327.78 26.84 2.21e-14 0.75x 8 34 298.76 29.44 2.31e-14 0.83x 7 28 238.94 36.81 3.50e-13 1.03x 6 21 189.59 46.40 4.39e-11 1.30x 5 15 136.34 64.52 4.51e-09 1.81x PyTorch FP64(cuBLAS)は同サイズで35.62 TFLOPSです。Rel ErrorはPyTorch FP64の結果を基準として計算しています。 d=7 でcuBLASと同等の速度を精度1e-13で達成し、 d=5 では1.8倍の高速化を1e-9精度で実現しています。なお、FP64 GEMM自体も浮動小数点演算の性質上、行列サイズに応じた丸め誤差は避けられないため、 d=8 (2.31e-14)程度の偏差であれば実用上十分でしょう。 まとめ cuTile Pythonの簡単な紹介とOzaki Schemeの実装を通じて、FP64行列積の高速化を試みました。BF16 Ozaki Schemeの最適化後、16384×16384行列で最大26.84 TFLOPS(d=9)を達成しました。dを調整することで精度と速度のトレードオフが可能で、d=7ではcuBLAS FP64(35.62 TFLOPS)と同等の36.81 TFLOPSを精度1e-13で達成し、d=5では64.52 TFLOPS(cuBLASの1.8倍)を1e-9精度で実現しています。 CUDAカーネルをPythonライクに書ける点で、GPUプログラミングの敷居が低くなったと感じます。 一方で、より高度な最適化やチューニングが必要な場合は、cuTile Pythonは抽象化してハード側の詳細を隠蔽している分、制約があるように感じました。今回は、行列積の例でしたが、tilegymにはtransformerの実装例があるので、次回はそちらも試してみたいと思います。 参考文献 [1] Lecture 89: cuTile (from friends at NVIDIA) [2] NVIDIA cuTile Documentation . cuTile Python. [3] NVIDIA TileGym . GPU Tile kernel development examples using cuTile. [4] Markus Höhnerbach, Paolo Bientinesi (2025). "DGEMM without FP64 Arithmetic" . arXiv:2508.00441. [5] Daichi Mukunoki, Katsuhisa Ozaki, Takeshi Ogita, and Toshiyuki Imamura (2020). "DGEMM using Tensor Cores, and Its Accurate and Reproducible Versions". ISC High Performance 2020, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12151. Springer, 230–248. doi:10.1007/978-3-030-50743-5_12
本ブログは 2025 年 6 月 13 日に公開された AWS Blog “ How to create post-quantum signatures using AWS KMS and ML-DSA ” を翻訳したものです。 量子コンピューティングの能力が進化し続ける中、AWS は、公開鍵暗号に対する新たな脅威にお客様が先手を打てるよう取り組んでいます。本日 (2025 年 6 月 13 日)、 FIPS 204: ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Standard) の AWS Key Management Service (AWS KMS) でのサポート開始を発表します。デジタル署名に使用している既存の AWS KMS API ( CreateKey 、 Sign 、 Verify オペレーションなど) を通じて、ML-DSA キーの作成と使用が可能になりました。この新機能は一般提供されており、米国西部 (北カリフォルニア) および欧州 (ミラノ) の AWS リージョンで ML-DSA を使用できます。残りの商用リージョンも数日以内に対応予定です。今回のリリースは、先日の ブログ記事 で紹介した、AWS のより広範なポスト量子暗号移行計画の一環です。この記事では、AWS KMS を使用して ML-DSA キーを作成し、ポスト量子署名を生成する手順を説明します。 多くの組織が AWS KMS を使用して、ファームウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション、その他のアーティファクトにデジタル署名を行っています。AWS KMS で ML-DSA をサポートしたことにより、FIPS 140-3 レベル 3 認定の HSM 内でポスト量子キーを生成し、署名・検証処理に使用できるようになりました。ML-DSA 署名を今から導入しておけば、暗号解読能力を持つ量子コンピュータ (CRQC) が利用可能になった場合でも、システムの運用期間全体を通じてセキュリティを維持できます。これは、長期間有効な信頼の基点を製造段階でデバイスに組み込むメーカーにとって特に重要です。ハードウェアに直接組み込む場合でも、長期間オフラインのままになる可能性のあるデバイスに組み込む場合でも同様です。いずれの場合も、出荷後にデジタル署名を簡単に更新することはできないため、システムの運用期間全体にわたるポスト量子対応が不可欠です。 新機能 AWS KMS では、3 つの新しい AWS KMS キースペック ( ML_DSA_44 、 ML_DSA_65 、 ML_DSA_87 ) が利用可能になりました。これらは新しいポスト量子 SigningAlgorithm である ML_DSA_SHAKE_256 と組み合わせて使用します。他の署名アルゴリズムと同様に、この名前には、署名スキーム内で署名または検証の前にメッセージをダイジェストするために使用されるハッシュ関数が含まれています。ここで使用されるハッシュ関数は、NIST が FIPS 202 で標準化した SHA-3 ファミリーに属する SHAKE256 です。 表 1 に、各キースペックの詳細 (NIST セキュリティカテゴリおよび対応するキーサイズ (バイト単位) など) を示します。各 ML-DSA キースペックは、セキュリティ強度とリソース要件のバランスが異なります。ML-DSA-44 は従来の 128 ビット暗号化に匹敵するセキュリティが必要なアプリケーションに適しています。一方、ML-DSA-65 と ML-DSA-87 はそれぞれ従来の 192 ビットおよび 256 ビット暗号化に相当する、より強力なセキュリティレベルを提供します。セキュリティレベルが上がるにつれてキーと署名のサイズも大きくなるため、セキュリティ要件とエンジニアリング上の制約に応じて最適なキースペックを選択できます。 Key spec NIST security Level Public key (B) Private key (B) Signature (B) ML_DSA_44 1 (128 ビットセキュリティ相当) 1,312 2,560 2,420 ML_DSA_65 3 (192 ビットセキュリティ相当) 1,952 4,032 3,309 ML_DSA_87 5 (256 ビットセキュリティ相当) 2,592 4,896 4,627 AWS KMS Sign API を RAW MessageType で使用する場合、署名対象のメッセージは 4,096 バイトに制限されます。4,096 バイトを超えるメッセージに署名するには、KMS Sign API への入力サイズを削減するために、AWS KMS の外部でメッセージを前処理して µ (mu) を作成する必要があります。この external mu プロセスでは、ML-DSA 署名キーペアの公開鍵を使用してメッセージをプリハッシュし、メッセージサイズを 64 バイトに縮小します。今回のリリースに合わせて、KMS Sign API に新しいメッセージタイプ EXTERNAL_MU を追加しました。これは ML-DSA の署名または検証の呼び出しで使用でき、AWS KMS に送信する前にメッセージが µ (mu) を使用して前処理済みであることを示します。 以降のセクションでは、external mu の作成方法を詳しく説明し、ML-DSA を使用した AWS KMS の基本的な操作を紹介します。キーの作成、署名の生成と検証について、 RAW と EXTERNAL_MU の両方の署名モードを取り上げます。なお、同じメッセージと署名キーを使用した場合、 RAW と EXTERNAL_MU のどちらで生成しても ML-DSA 署名は同一になります。 ML-DSA キーの作成 まず、 AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用して、以下のコマンドで非対称 AWS KMS キーを作成します。 aws kms create-key --key-spec ML_DSA_65 --key-usage SIGN_VERIFY このコマンドは、以下のようなレスポンスを返します。 { "KeyMetadata": { "Origin": "AWS_KMS", "KeyId": " 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ", "MultiRegion": false, "Description": "", "KeyManager": "CUSTOMER", "Enabled": true, "SigningAlgorithms": [ "ML_DSA_SHAKE_256" ], "CustomerMasterKeySpec": "ML_DSA_65", "KeyUsage": "SIGN_VERIFY", "KeySpec": "ML_DSA_65", "KeyState": "Enabled", "CreationDate": 1748371316.734, "Arn": " arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ", "AWSAccountId": " 111122223333 " } } レスポンスに含まれる KeyId または Arn の値を控えておいてください。以降の署名操作でキーを参照する際に必要になります。このレスポンスから、 SIGN_VERIFY オペレーション用に ML_DSA_65 キーが作成され、署名オペレーションには ML_DSA_SHAKE_256 署名アルゴリズムが使用されることを確認できます。 署名 このセクションでは、Web における認可処理において当事者間のクレーム受け渡しに広く使われている JSON Web Token (JWT) を例に、ML-DSA による署名と検証の方法を紹介します。2021 年には、従来の非対称暗号アルゴリズムである楕円曲線デジタル署名アルゴリズム (ECDSA) を使用した JWT の署名と検証の方法を紹介しました (「 How to verify AWS KMS signatures in decoupled architectures at scale 」を参照)。以下の例では、AWS KMS で管理される ML-DSA プライベートキーで JWT に署名し、AWS KMS 内または OpenSSL を使用して外部で検証します。 署名対象の JWT コンテンツは、 RFC7519 のセクション 3.1 に基づいています。JWT ヘッダーは以下のとおりです。 {"typ":"JWT", "alg":"ML-DSA-65"} JWT クレームセットは以下のとおりです。 {"iss":"joe", "exp":1748952000, "http://example.com/is_root":true} ヘッダーとペイロードを Base64URL エンコードすることで、署名対象の JWT メッセージを生成できます。 echo -n -e '{"typ":"JWT",\015\012 "alg":"ML-DSA-65"}' | \ basenc --base64url -w 0 | \ sed 's/=//g' ; echo -n "." ; echo -n -e '{"iss":"joe",\015\012 "exp":1748952000,\015\012 "http://example.com/is_root":true}' | \ basenc --base64url -w 0 | sed 's/=//g' ; echo "" このコマンドは、ML-DSA で署名する対象となる以下の Base64 文字列を出力します。 eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ 以下の例では、AWS KMS で管理される ML-DSA プライベートキーを使用してメッセージの ML-DSA 署名を生成し、バイナリ形式で出力します。JWT で使用するには Base64URL に変換する必要がありますが、この署名はさまざまなデータ暗号化および署名形式で利用できます。具体的には、Cryptographic Message Syntax (CMS)、CBOR Object Signing and Encryption (COSE)、UEFI や Open Titan のイメージ署名エンコーディングなどが挙げられます。バイナリからこれらの形式への変換は容易ですが、本記事の執筆時点では、一般的な暗号ライブラリの実装において新しいアルゴリズムのサポートがまだ利用できない場合があります。 RAW モードでの ML-DSA 署名 4,096 バイト未満のメッセージに AWS KMS で ML-DSA 署名を行うには、以下のように AWS CLI を使用します。 aws kms sign \ --key-id <1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab> \ --message ' eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ' \ --message-type RAW \ --signing-algorithm ML_DSA_SHAKE_256 \ --output text \ --query Signature | base64 --decode > ExampleSignature.bin target-key-id の値 <1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab> を実際の KeyId に置き換えてください。このコマンドは署名を生成し、 ExampleSignature.bin としてディスクに書き込みます。 署名を生成したら、以下のコマンドでヘッダー、ペイロード、署名から構成される完全な JWT を作成できます。 echo -n "eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ." ; \ basenc --base64url -w 0 ExampleSignature.bin | \ sed 's/=//g' ; echo "" このコマンドは、 RFC 7519 で要求される形式に準拠した、AWS KMS で署名済みの JWT を出力します。 eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ. <base64url of the signature as per RFC7519> external mu モードでの ML-DSA 署名 AWS KMS では、Sign API 使用時のレスポンスレイテンシーを最小限に抑えるため、RAW メッセージのサイズを 4,096 バイトに制限しています。署名対象のメッセージが 4,096 バイトを超える場合や、external mu のプリハッシュによるパフォーマンス上のメリットを活用したい場合は、 RAW の代わりに EXTERNAL_MU メッセージタイプを使用する必要があります。 AWS KMS Sign API で EXTERNAL_MU メッセージタイプを使用するには、事前にローカルでメッセージのプリハッシュ計算を行う必要があります。まず、以下のコマンドで AWS KMS から公開鍵を取得し、DER 形式に変換します。下記の例のキー ID は、実際の AWS アカウントの有効なキー ID に置き換えてください。 aws kms get-public-key \ --key-id <1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab> \ --output text \ --query PublicKey | base64 --decode > public_key.der external mu ダイジェストの作成手順は以下のとおりです。 メッセージプレフィックス (M`) を作成します M` = (domain separator || context length || context || Message) この例では、ドメインセパレータの値とコンテキスト長をゼロに設定します。これにより、署名で使用されるコンテキストが空文字列 (デフォルト) になります。 公開鍵をハッシュし、メッセージプレフィックスの先頭に付加します (SHAKE256(pk) || M') ハッシュして 64 バイトの mu を生成します Mu = SHAKE256(SHAKE256(pk) || M') OpenSSL 3.5 では、以下の単一コマンドでダイジェストを作成できます。 { openssl asn1parse -inform DER -in public_key.der -strparse 17 -noout -out - 2>/dev/null | openssl dgst -provider default -shake256 -xoflen 64 -binary; printf '\x00\x00'; echo -n "eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ" } | openssl dgst -provider default -shake256 -xoflen 64 -binary > mu.bin これで、AWS KMS を呼び出して 64 バイトのダイジェストに署名し、ML-DSA 署名をファイル ExampleSignature.bin に出力できます。 MessageType は EXTERNAL_MU に設定してください。 aws kms sign \ --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ --message fileb://mu.bin \ --message-type EXTERNAL_MU \ --signing-algorithm ML_DSA_SHAKE_256 \ --output text \ --query Signature | base64 --decode > ExampleSignature.bin 最終的に署名された JWT トークンは、前述の RAW モードで生成されたものと同一です。 AWS KMS を使用した署名検証 このセクションでは、AWS KMS またはローカル環境で ML-DSA 署名を検証する方法を説明します。ここでは、AWS KMS 内のプライベートキーを使用して JWT コンテンツに対して生成された ML-DSA 署名が ExampleSignature.bin に格納されており、 KEY_ARN で識別されることを前提とします。 以下の例では、AWS KMS から直接取得した公開鍵を使用した署名検証を示していますが、これらの原則はプライベート PKI などの証明書ベースのシステムにも適用できます。プライベート PKI では、公開鍵は署名者のエンドエンティティ証明書に埋め込まれています。このようなシナリオでは、検証者はまず証明書チェーンが信頼されたルート証明書に結びついていることを検証して署名者の身元を確認し、次にエンドエンティティ証明書の公開鍵を使用してコンテンツの ML-DSA 署名を検証します。 IETF は、RFC ドラフト draft-ietf-lamps-dilithium-certificates を通じて、X.509 証明書での ML-DSA の使用を標準化しています。 RAW モードでの ML-DSA 検証 AWS KMS を使用して署名を検証するには、以下のコマンドを実行します。例の key-id は、署名時に使用したものと同じキー ID に置き換えてください。 aws kms verify \ --key-id <1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab> \ --message "eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ" \ --message-type RAW \ --signing-algorithm ML_DSA_SHAKE_256 \ --signature fileb://ExampleSignature.bin 以下のようなレスポンスが返されます。 { "KeyId": " arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ", "SignatureValid": true, "SigningAlgorithm": "ML_DSA_SHAKE_256" } 検証結果は SignatureValid フィールドで確認できます。 external mu モードでの ML-DSA 検証 JWT コンテンツの external mu ダイジェストが mu.bin に格納されており、署名と対応するキーペアが AWS KMS にある場合、メッセージ全体にアクセスしたりダイジェストを再計算したりすることなく、このダイジェストを使用して検証できます。 aws kms verify \ --key-id <1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab> \ --message fileb://mu.bin \ --message-type EXTERNAL_MU \ --signing-algorithm ML_DSA_SHAKE_256 \ --signature fileb://ExampleSignature.bin メッセージと公開鍵から external mu mu.bin を再生成する方法については、前述の 「external mu モードでの ML-DSA 署名」セクション を参照してください。 OpenSSL 3.5 を使用したローカル署名検証 ML-DSA 署名の生成には AWS KMS で生成・保管されたキーのセキュリティを維持しつつ、API の呼び出しコストを削減し、API クォータの使用をより細かく制御したい場合は、AWS KMS の外部でローカルに ML-DSA 署名を検証できます。 この例では、OpenSSL 3.5 を使用して ExampleSignature.bin の署名を検証します。まず、 「external mu モードでの ML-DSA 署名」 セクションで示したように、AWS KMS から DER エンコードされた公開鍵を取得し、ファイル public_key.der に保存する必要があります。OpenSSL 3.5 では、この公開鍵を使用してメッセージの署名を検証できます。 echo -n "eyJ0eXAiOiJKV1QiLA0KICJhbGciOiJNTC1EU0EtNjUifQ.eyJpc3MiOiJqb2UiLA0KICJleHAiOjE3NDg5NTIwMDAsDQogImh0dHA6Ly9leGFtcGxlLmNvbS9pc19yb290Ijp0cnVlfQ" | \ openssl dgst -verify public_key.der -signature ExampleSignature.bin 検証が成功すると、 Verified OK と出力されます。 まとめ 本日 (2025 年 6 月 13 日) の AWS KMS における ML-DSA サポートの開始は、ポスト量子暗号に対する AWS の取り組みにおける重要なマイルストーンです。3 段階のセキュリティレベルと RAW・external mu の 2 つの署名モードにより、量子コンピューティング時代を見据えたセキュリティ要件に柔軟に対応できます。既存の AWS KMS API とシームレスに統合できるため、量子コンピュータに耐性のある署名を今すぐアプリケーションに組み込むことが可能です。この実装は、以下のようなユースケースで特に効果を発揮します。 ポスト量子暗号の使用時に FIPS 140-3 準拠要件を満たす必要がある場合 コード、アーティファクト、ドキュメントなどに対して、暗号解読能力を持つ量子コンピュータ (CRQC) が実現した後も長期間にわたって検証可能な署名を付与する必要がある場合 AWS KMS のような承認済みの暗号サービスを活用し、アプリケーション開発プロセスの一環としてポスト量子暗号のテストを開始する場合 ポスト量子暗号 全般、および AWS の ポスト量子暗号への移行計画 の詳細についてはリンク先をご覧ください。 Jake Massimo Jake は AWS Cryptography チームの Applied Scientist です。国際会議、学術研究、標準化団体への積極的な参加を通じて、Amazon とグローバルな暗号コミュニティの橋渡し役を担っています。クラウド規模でのポスト量子暗号技術の導入推進に取り組んでおり、現在は AWS 暗号ライブラリにおいて、最適化され形式的に検証されたポスト量子アルゴリズムの開発をリードしています。 Panos Kampanakis Panos はサイバーセキュリティ、応用暗号、セキュリティ自動化、脆弱性管理に関する豊富な経験を持っています。長年にわたり、技術イベントでさまざまなセキュリティトピックに関するトレーニングやプレゼンテーションを行ってきました。サイバーセキュリティに関する出版物を共同執筆し、セキュリティ情報共有、暗号、PKI のための共通の相互運用可能なプロトコルや言語を提供するさまざまなセキュリティ標準化団体に参加しています。 Mayank Ambaliya Mayank は AWS Key Management Service (AWS KMS) の Software Development Manager です。AWS KMS の暗号 API およびカスタムキーストアの開発をリードしています。AWS CloudHSM のお客様向け暗号 API および暗号 SDK の開発経験があり、最近では AWS KMS でのポスト量子アルゴリズムサポートや新しい暗号 API の追加に取り組んでいます。 本ブログは Security Solutions Architect の 中島 章博 が翻訳しました。